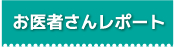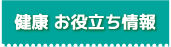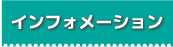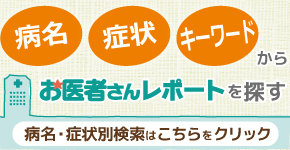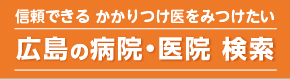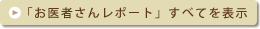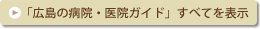広島の頼れるかかりつけ医&病院・医院・クリニックに出会える健康情報サイト
(この記事は2013年2月14日時点の情報です)
なかむら内科クリニック
【住所】 広島市中区大手町1丁目1−20 相生橋ビル9階
【TEL】 082-545-1199

私たちの体のために、毎日頑張ってくれている肝臓。脂肪肝で苦しめてないですか?
お酒の飲み過ぎや高カロリー食が原因と言われる脂肪肝ですが、最近はお酒を飲まない人でもかかる「非アルコール性脂肪性肝疾患」が増えていて、怖いタイプの脂肪肝もあるそうです。
今回のレポートは、肝臓専門医として多数のウイルス性肝炎、肝硬変、肝臓がんの治療に携わってきた「なかむら内科クリニック」の院長、中村利夫先生に肝臓の病気についてお話いただきました。B型肝炎についても、分かりやすく説明しています。
脂肪肝になる原因は、食べ過ぎ、お酒の飲み過ぎ、肥満・糖尿病、運動不足など。いわゆる生活習慣病のひとつと言えます。男性でしたら、青年から中高年までと患者さんの年齢は幅広く、高齢の方もたくさんおられます。女性は若い世代には少ないのですが、更年期以降は増加傾向にあり、閉経が影響していると思われます。
脂肪肝からの合併症としては、糖尿病、高血圧、動脈硬化、高脂血症などがあります。
検査では、エコーやCTを使って肝臓への脂肪の沈着の程度を調べたり、採血を行ってB型肝炎・C型肝炎の疑いがないか検査します。問診では、食生活や飲酒歴についてお尋ねしますが、「お酒を飲むかどうか」は脂肪肝のタイプを見極めるうえでとても重要なポイントとなります。
●アルコール性疾患・・・お酒の大量摂取が要因
●非アルコール性疾患・・・お酒以外の様々な要因
1、単純性脂肪肝・・・脂肪肝のみ
2、NASH(非アルコール性脂肪肝炎)・・・脂肪肝+肝炎
単純性脂肪肝と診断されても、単純性脂肪肝の約10%にNASHがあると考えられています。NASHの診断には肝生検を行いますが、これは肝臓の組織を採取して顕微鏡で細かく観察する検査となるため入院が必要です。患者さんの体にも負担がかかるため、全ての方が検査できるわけではありません。発見されにくい病気であることも、NASHの怖いところと言えます。当院でも採血でNASHの可能性が高いと疑われた場合には、肝生検が受けられる大きい病院を速やかに紹介しています。
脂肪肝は誰もがなり得る現代病ですが、中には進行型の恐ろしいタイプがあることを覚えておいてください。
お酒を飲みすぎている方は、お酒を控えるように意識して頂き、太った方には減量の指導を行っていきます。ただ「我慢しましょう」では、なかなか続きませんので、どうやったら健康的な生活になるかをチェックして自然に減量するように導いていきます。たとえば,食事の量は減らさずに、肉より魚、魚より野菜を食べるようアドバイスします。そのためにも食事の記録を付けてもらい、体重をグラフ化して、ご自分の生活の歪みに気が付いてもらいます。食行動のダイアグラムをチェックして、太りやすい人の食行動のデータをとり、生活習慣を改善していきます。
B型肝炎ウィルス(HBV)は、出産時や幼少時に周りの人からウイルスをもらうことが多いのですが、多くの方は大人になるまでに自然に安定した状態になります。ところが、一部の方は慢性肝炎に移行します。慢性肝炎が進行すると肝臓の線維化が進み、肝硬変や肝がんが発生する可能性があります。
一方、大人になってからかかる場合はほとんどが急性のB型肝炎で、一時的な症状はあるものの一定期間の治療で治り、慢性肝炎に移行することはまれです。
どちらもB型肝炎の治療薬としてとても優れたお薬ですが、やはりデメリット面もあります。インターフェロンは種々の副作用が生じやすいです。核酸アナログは効果が高いうえ副作用の心配も少ないのですが、中止が困難です。どのお薬を使うかは、患者さんの状態や主治医の判断により異なります。
B型慢性肝炎の治療法は、35歳を基準にしたガイドラインがあり、自然治癒の期待ができる35歳未満であれば主にインターフェロン療法、35歳以上なら主にバラクルードが用いられます。インターフェロン療法もバラクルードも、肝硬変や肝臓がんに移行するのを防ぐための治療です
たとえば、血液検査をしてHBe抗体が陽性だった場合は、B型肝炎ウィルスが非活動期になったことを示すので、肝炎が治ったように思われるのですが、一年後に肝機能検査をしてみると、ウイルスが増加し肝機能が悪化している場合があります。また、ウィルスの量が多くても肝機能検査の数値には異常が見られないこともあり、患者さんご本人は元気だけど知らないうちに肝硬変が進行していたケースもありますので注意が必要です。
B型肝炎ウィルスが多いと肝臓がんにかかる危険度は高くなります。以前はウィルス量を正確に測定するのは難しかったのですが、この10年で技術や知識が急速に進化したことで、より正確なウィルス量の測定が可能になりました。ウィルス量を調べると、自分がどれだけ危険なのか確認できます。以前よりも検査項目が増え、病気に対する考え方や治療方法も年々変わってきていますので、だいぶん前に検査をして「大丈夫ですよ」と言われた方でも、もう一度新たな目で検査を受けていただきたいと思います。
肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、病気になっていても初期症状がないものが多いため見逃しがちです。1年に一度は採血したり、人間ドックに行ったりして、肝機能のチェックをすることを心掛けてほしいと思います。
また、肝臓の病気で1番多いのは脂肪肝ですが、それ以外のB型肝炎、C型肝炎、その他珍しい肝炎もあるので、肝機能が悪い人は専門医を受診することをおすすめします。
脂肪肝に限らず、適切な運動というのはガンにもなりにくく体に良いことですので、体を動かす習慣を生活の中で見つけてほしいですね。
● 双三中央病院勤務(現在の三次中央病院)
● 広島大学医学部第一内科勤務
● 広島大学医学部大学院
● 広島記念病院勤務
広島記念病院肝臓内科医長
広島大学医学部臨床助教授
‐所属学会‐
日本肝臓学会専門医
日本消化器病学会専門医
日本内科学会認定医
日本内科学会
日本消化器病学会
日本肝臓学会
日本消化器内視鏡学会
日本糖尿病学会
日本肥満学会
日本高血圧学会
趣味は映画鑑賞
(広島映画サークル協議会の会員)
中村利夫 先生(内科)
肝臓のこと、知りましょう!「脂肪肝」と「B型肝炎」はこんな病気です
なかむら内科クリニック
【住所】 広島市中区大手町1丁目1−20 相生橋ビル9階
【TEL】 082-545-1199

肝臓の病気が気になる方は、肝臓専門医である中村利夫先生にご相談を
私たちの体のために、毎日頑張ってくれている肝臓。脂肪肝で苦しめてないですか?
お酒の飲み過ぎや高カロリー食が原因と言われる脂肪肝ですが、最近はお酒を飲まない人でもかかる「非アルコール性脂肪性肝疾患」が増えていて、怖いタイプの脂肪肝もあるそうです。
今回のレポートは、肝臓専門医として多数のウイルス性肝炎、肝硬変、肝臓がんの治療に携わってきた「なかむら内科クリニック」の院長、中村利夫先生に肝臓の病気についてお話いただきました。B型肝炎についても、分かりやすく説明しています。
肝臓はどのような臓器ですか?
肝臓は、栄養の代謝・貯蔵・解毒・タンパクの合成など、人が生きていくうえで欠かせない様々な役割を担う臓器です。肝臓に関わる疾患として、脂肪肝、肝炎(急性肝炎、慢性肝炎)、肝硬変、肝臓がんといったものがあげられます。その中でも、日本人の1000万人がかかっていると推定されている「脂肪肝」と、100〜150万人がかかっていると推定されている「B型肝炎」がどういった病気かについてお話をしましょう。まず、脂肪肝とはどんな病気なのか教えてください。
肝臓には中性脂肪を分解してエネルギー源として送り出す役割がありますが、食べ過ぎたり飲み過ぎたりすると、肝臓の処理能力が追い付かなくなってしまい、中性脂肪が肝臓にたまってしまいます。脂肪肝はひとことで言うと、肝臓の細胞の中に中性脂肪が沢山たまった状態です。脂肪肝の人の肝臓を顕微鏡でのぞくと、白い油滴の穴が沢山あります。脂肪肝はCTでは黒く描出されます。脂肪肝になる原因は、食べ過ぎ、お酒の飲み過ぎ、肥満・糖尿病、運動不足など。いわゆる生活習慣病のひとつと言えます。男性でしたら、青年から中高年までと患者さんの年齢は幅広く、高齢の方もたくさんおられます。女性は若い世代には少ないのですが、更年期以降は増加傾向にあり、閉経が影響していると思われます。
脂肪肝からの合併症としては、糖尿病、高血圧、動脈硬化、高脂血症などがあります。
脂肪肝になったらどんな自覚症状がありますか?
自覚症状がないため、脂肪肝は自分では気付きにくい病気です。定期的に健診を受けることが、早期発見のカギとなります。検査では、エコーやCTを使って肝臓への脂肪の沈着の程度を調べたり、採血を行ってB型肝炎・C型肝炎の疑いがないか検査します。問診では、食生活や飲酒歴についてお尋ねしますが、「お酒を飲むかどうか」は脂肪肝のタイプを見極めるうえでとても重要なポイントとなります。
脂肪肝にもいろんなタイプがあるのですか?
大きく分けて「アルコール性脂肪肝」と「非アルコール性脂肪性肝疾患」があります。「アルコール性脂肪肝」は文字通りお酒の飲み過ぎが原因で起きる脂肪肝のことで、一方「非アルコール性脂肪性肝疾患」とは、お酒とは関係ない様々な要因が引き金となる脂肪肝のことです。さらに、「非アルコール性脂肪性肝疾患」は、肥満などが原因の生活習慣病である「単純性脂肪肝」と「非アルコール性脂肪肝炎(NASH)」に分類されます。近年ではお酒を飲まない人の脂肪肝が増えている傾向にあり、このNASHが問題視されています。●アルコール性疾患・・・お酒の大量摂取が要因
●非アルコール性疾患・・・お酒以外の様々な要因
1、単純性脂肪肝・・・脂肪肝のみ
2、NASH(非アルコール性脂肪肝炎)・・・脂肪肝+肝炎
脂肪肝のなかでもNASHが問題となる理由とは?
NASHとは、アルコールを原因としない脂肪肝から発生する肝炎です。なぜ問題かと言いますと、進行性の病気だからです。NASHになると、肝臓の炎症や線維化が進んで肝硬変を引き起こすことがあります。進行の速度は早くて、発症後5年〜10年で5〜20%の確率で肝硬変に変わってしまうと言われています。また、肝臓がんへ移行するケースもあり、重症だと死に至ることもある恐ろしい病気です。単純性脂肪肝と診断されても、単純性脂肪肝の約10%にNASHがあると考えられています。NASHの診断には肝生検を行いますが、これは肝臓の組織を採取して顕微鏡で細かく観察する検査となるため入院が必要です。患者さんの体にも負担がかかるため、全ての方が検査できるわけではありません。発見されにくい病気であることも、NASHの怖いところと言えます。当院でも採血でNASHの可能性が高いと疑われた場合には、肝生検が受けられる大きい病院を速やかに紹介しています。
脂肪肝は誰もがなり得る現代病ですが、中には進行型の恐ろしいタイプがあることを覚えておいてください。
脂肪肝の治療についてお聞かせください。
NASHという怖い脂肪肝もあるというお話をしましたが、脂肪肝は生活習慣を改善していけば治りうる病気です。体重が減っていけば、肝臓についた脂肪も取れていきますので、食事や運動によって病気を改善することができます。お酒を飲みすぎている方は、お酒を控えるように意識して頂き、太った方には減量の指導を行っていきます。ただ「我慢しましょう」では、なかなか続きませんので、どうやったら健康的な生活になるかをチェックして自然に減量するように導いていきます。たとえば,食事の量は減らさずに、肉より魚、魚より野菜を食べるようアドバイスします。そのためにも食事の記録を付けてもらい、体重をグラフ化して、ご自分の生活の歪みに気が付いてもらいます。食行動のダイアグラムをチェックして、太りやすい人の食行動のデータをとり、生活習慣を改善していきます。
次に、B型肝炎とはどのような病気ですか?
B型肝炎には慢性型と急性型があります。B型肝炎ウィルス(HBV)は、出産時や幼少時に周りの人からウイルスをもらうことが多いのですが、多くの方は大人になるまでに自然に安定した状態になります。ところが、一部の方は慢性肝炎に移行します。慢性肝炎が進行すると肝臓の線維化が進み、肝硬変や肝がんが発生する可能性があります。
一方、大人になってからかかる場合はほとんどが急性のB型肝炎で、一時的な症状はあるものの一定期間の治療で治り、慢性肝炎に移行することはまれです。
B型肝炎の治療についてお聞かせください。
近年、B型肝炎の治療は目覚ましく進歩して、効果の高い治療薬が使われるようになりました。治療を助けるお薬としては、ウイルスを減少させ肝機能を正常化させるバラクルード(エンテカビル)、抗ウイルス作用や免疫増強作用のあるインターフェロンが主に用いられます。どちらもB型肝炎の治療薬としてとても優れたお薬ですが、やはりデメリット面もあります。インターフェロンは種々の副作用が生じやすいです。核酸アナログは効果が高いうえ副作用の心配も少ないのですが、中止が困難です。どのお薬を使うかは、患者さんの状態や主治医の判断により異なります。
B型慢性肝炎の治療法は、35歳を基準にしたガイドラインがあり、自然治癒の期待ができる35歳未満であれば主にインターフェロン療法、35歳以上なら主にバラクルードが用いられます。インターフェロン療法もバラクルードも、肝硬変や肝臓がんに移行するのを防ぐための治療です
治療面だけでなく診断面も、ここ10年で大きく進歩しているのですね。
C型肝炎に比べてB型肝炎は、私たち専門医同士でも治療について意見交換し合うことが多い、理解・判断の難しい疾患です。たとえば、血液検査をしてHBe抗体が陽性だった場合は、B型肝炎ウィルスが非活動期になったことを示すので、肝炎が治ったように思われるのですが、一年後に肝機能検査をしてみると、ウイルスが増加し肝機能が悪化している場合があります。また、ウィルスの量が多くても肝機能検査の数値には異常が見られないこともあり、患者さんご本人は元気だけど知らないうちに肝硬変が進行していたケースもありますので注意が必要です。
B型肝炎ウィルスが多いと肝臓がんにかかる危険度は高くなります。以前はウィルス量を正確に測定するのは難しかったのですが、この10年で技術や知識が急速に進化したことで、より正確なウィルス量の測定が可能になりました。ウィルス量を調べると、自分がどれだけ危険なのか確認できます。以前よりも検査項目が増え、病気に対する考え方や治療方法も年々変わってきていますので、だいぶん前に検査をして「大丈夫ですよ」と言われた方でも、もう一度新たな目で検査を受けていただきたいと思います。
最後に「広島ドクターズ」の読者にアドバイスをお願いします
私は父をB型肝硬変で亡くしたこともあり、肝臓専門医の道を選びました。ですから、広島から肝臓の病気で苦しむ人を減らしたい、救いたいという思いが強く、患者さんの健康を少しでも応援したいと考えています。肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、病気になっていても初期症状がないものが多いため見逃しがちです。1年に一度は採血したり、人間ドックに行ったりして、肝機能のチェックをすることを心掛けてほしいと思います。
また、肝臓の病気で1番多いのは脂肪肝ですが、それ以外のB型肝炎、C型肝炎、その他珍しい肝炎もあるので、肝機能が悪い人は専門医を受診することをおすすめします。
脂肪肝に限らず、適切な運動というのはガンにもなりにくく体に良いことですので、体を動かす習慣を生活の中で見つけてほしいですね。
医師のプロフィール
中村利夫先生
● 広島大学医学部卒業● 双三中央病院勤務(現在の三次中央病院)
● 広島大学医学部第一内科勤務
● 広島大学医学部大学院
● 広島記念病院勤務
広島記念病院肝臓内科医長
広島大学医学部臨床助教授
‐所属学会‐
日本肝臓学会専門医
日本消化器病学会専門医
日本内科学会認定医
日本内科学会
日本消化器病学会
日本肝臓学会
日本消化器内視鏡学会
日本糖尿病学会
日本肥満学会
日本高血圧学会
趣味は映画鑑賞
(広島映画サークル協議会の会員)
■□■□ 2025年12月によく読まれた記事をCHECK! □■□■
命にかかわる病気ではありませんが、経過観察と言われたら生理の変化に気を付けて。過多月経や月経痛がひどくなるなどの場合は早めに産婦人科に相談しましょう。
実は10代、20代の女性の死因上位に挙げられる摂食障害。
人の価値や美しさは、体型や体重で決まるものではありません。
適切なカウンセリングで過度な痩せ願望やストレスから自分の体を守りましょう。
幼児や児童に感染することが多く、発症すると喉の痛み、熱、発疹などといった風邪と似た症状が起こります。また、痛みはないのですが、舌の表面に赤いぶつぶつができることがあります。
尋常性疣贅は、「ヒト乳頭腫ウイルス」というウイルスの一種が皮膚に感染してできます。手あれや髭剃り後など、目に見えないくらいの小さな傷からでもウイルスが侵入します。どこの部位にもできる可能性があるのです。
咽喉頭異常感症は心理的要因が大きいといわれています。
喉がイガイガする、圧迫感がある、引っ掛かったり、絡んだような感じがするなど
考えれば考えるほど、喉に違和感を抱き、そのストレスが引き金になって症状を引き起こすことも多いようです。
「不安障害」とはその名の通り、不安な気持ちが強くなる病気です。
ある特定の状況や場所で非常に強い不安に襲われ、身体のいろいろな部分に様々な症状が現われたり、不安を避けようとする「回避行動」をとるようになったり、また安心を得るために無意味な行動を反復してしまうといったことが起こり、人によってはそれが原因で社会生活に支障をきたすこともあります。