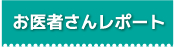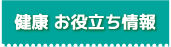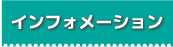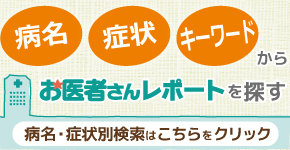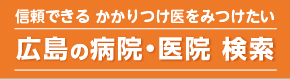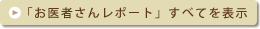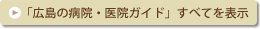広島の頼れるかかりつけ医&病院・医院・クリニックに出会える健康情報サイト
(この記事は2013年4月1日時点の情報です)
もみじクリニック
【住所】広島市中区白島北町17−2
【TEL】 082-502-8100

お手洗いはどこかしら? 人前で漏らしてしまったらどうしよう…。
「おしっこ」のことばかり考えている人はいませんか? 誰かに相談したり受診するのが恥ずかしくて、おしっこの悩みをガマンしている人も多いようですが、「過活動膀胱」という改善できる病気が原因かもしれませんよ。
今回は、「もみじクリニック」の院長・山本理哉先生に、過活動膀胱について詳しく説明して頂きました。誰でも自宅で簡単にできる「骨盤底筋体操」も紹介しています。
山本先生の記事をきっかけに、トイレを気にしない有意義な毎日を過ごせる人が増えますように!
確かに慢性の膀胱炎や前立腺炎などの感染症が引き金となって、過活動膀胱になるケースはありますし、それらの病気と同時に存在することもあるのですが、細菌感染が原因である病気とは全く異なるカテゴリーの病気と言えます。
過活動膀胱は原因がはっきり分からない突発性のものが大半ですが、膀胱炎、前立腺炎、糖尿病、脳梗塞、骨盤内の手術が原因で、脳と膀胱をつなぐ神経回路に障害が起こり、正常な排尿コントロールがなされないことで起きる場合もあります。また、ストレスによって交感神経が緊張して膀胱の異常収縮が起こり、過活動膀胱を引き起こすこともあります。
細菌感染が原因でないという点で、類似する病気に「間質性膀胱炎」というものがありますが、これは間質に炎症が起こることで膀胱の萎縮が生じるもので、膠原病やリウマチのような疾患だと思ってください。症状が似ていることから、診断の際は両者の鑑別が重要となります。
頻尿があると、外出先ではいつもトイレが心配で、仕事や買い物に集中できないなど、日常生活でも不便なことが多いと思います。また日中だけでなく、夜中に何度もトイレに起きる「夜間頻尿」によって、十分な睡眠がとれないこともあります。朝方の目覚める前に何回か続けてトイレに行くといった方はまだいいのですが、2時間おきに睡眠が中断されてトイレに行くことが毎晩続けば、慢性的な睡眠不足を引き起こしかねません。睡眠障害による全身の不調も懸念されます。
夜間多尿とは夜間の尿量が増加する状態をいい、多量の水分摂取が関係している場合もありますが、病気や加齢でホルモン分泌のバランスが崩れてしまうことにより夜間多尿が起こることもあります。
本来、おしっこは午前中に多く作られ、夜になるにつれて尿量は少なくなるのですが、心不全など心臓に疾患があると、起きている状態よりも寝ている時の方が血液を送り出す心臓のポンプが機能して、腎臓への血液循環が良くなり尿量が増えることがあります。
夜間頻尿が夜間多尿から起こっている場合、もしかしたら多尿の原因は心臓の病気から来ているのかもしれません。問診ではおしっこの回数だけでなく、一回の尿量についても患者さんから詳しく聞き、排尿トラブルの裏に大きな病気が潜んでいないか、慎重に診ていく必要があります。
「腹圧性尿失禁」は、くしゃみや咳をした時、重いものを持った時、大声で笑った時など腹圧がかかった時に起こる尿失禁で、女性に多く見られるものです。出産や年齢にともない、骨盤底筋群の筋肉が緩むことで尿道の閉まりが悪くなり、尿が漏れやすくなるものです。
逆に男性に多いのが、2つ目の「溢流性尿失禁」です。これは前立腺肥大症などの尿が出にくくなる排尿障害によって、膀胱内いっぱいに溜まった尿が溢れるように流れ出る状態が起きるものです。いつも残尿感があり、患者さんにとっては辛い症状と言えます。高齢の人に多くみられるものです。
過活動膀胱に関係するのが、3つ目の「切迫性尿失禁」です。これは突然強い尿意を感じ、トイレまで我慢できずに漏らしてしまうといったものです。自分の意思とは関係なく膀胱が過敏に反応してしまうため、排尿コントロールが上手く機能せず、尿意を感じたらすぐにおしっこが出てしまうこともあります。切迫性尿失禁は性別を問わずみられる症状です。
おしっこをした後に出し切れていない残尿がある場合は、基本的には過活動膀胱とは言いませんから、残尿測定などの検査を行ったり、患者さんに排尿日誌を付けてもらうことでより正確な診断を行います。
お薬で膀胱を収縮させる異常伝達を抑制させると、尿意に対して鈍感になり、これまで尿が少したまっただけでトイレに行きたくなっていたのが、ある程度尿がたまるまで我慢できるようになります。尿をためる機能が高まることで一回のおしっこの量が増え、頻尿や切迫感が改善されます。
また、骨盤底筋を鍛えることで尿トラブルが軽減できますから、尿漏れの改善・予防のために、「骨盤底筋体操」を推奨しています。
まずは、ピンポン球を1つ用意してください。立った姿勢でお尻の上の方にピンポン球をはさみ、落ちないようにお尻をグッと閉めます。しばらくその状態で保ったあと、お尻の筋肉を緩めてポトンと落としてください。この時、お尻を突き出さないように注意してくださいね。ピンポン球を乗せる、落とすを繰り返すことで、尿道が締り、緩まり、括約筋が鍛えられます。排尿障害の種々な症状を改善・予防することができますので、ご自宅で是非やってみてください。
過活動膀胱は治療せずに放置したからといって、死に至るような病気ではありませんが、トイレのことが気になって旅行や映画を楽しめない、外出するのが億劫になる、というのでは生活の質も下がってしまいます。過活動膀胱は治療によって十分改善できる病気なので、少しでも多くの方に病気の存在を知ってもらい、専門医を受診してもらって、おしっこの悩みから解放できるよう、啓蒙活動を行っていく必要があると考えています。
昔は、「泌尿器科」=「性病をメインに治療するところ」といったイメージが強かったかもしれませんが、実は泌尿器科の診療は幅広く、副甲状腺の病気なども取り扱っていて、頚部の手術も行うことがあります。全身管理ができないといけない科なのですよ。
泌尿器科に行きづらいと感じる患者さんに配慮して、あえて医院名に「泌尿器科」を入れなかったのですが、当院では循環器科専門医として副院長が内科診療も一緒に行っていますので、どなたでも楽な気持ちで受診して頂けたらと思います。
おしっこの悩みは生涯毎日のこと。気になる状態のままで暮らすのは、すごくもったいないことだと思います。適切な治療で改善される症状も多いですから、おしっこのことで1人でずっと悩んできたという方、尿の不調は年齢のせいだと諦めていた方は、思い切って泌尿器科の門をくぐってみませんか? 「相談して良かった」と、きっと思いますよ!
●東京大学泌尿器科入局
●東京都立駒込病院
●東京大学医学部附属病院助手」
●日赤医療センター
●岡山大学泌尿器科
●広島市民病院
山本理哉 先生(泌尿器科)
さっき行ったのにまたトイレ?! 多くの方が悩んでいる「過活動膀胱」
もみじクリニック
【住所】広島市中区白島北町17−2
【TEL】 082-502-8100

丁寧な問診を行うことで、正確な診断と患者に安心できる医療を提供することを心がける山本院長
お手洗いはどこかしら? 人前で漏らしてしまったらどうしよう…。
「おしっこ」のことばかり考えている人はいませんか? 誰かに相談したり受診するのが恥ずかしくて、おしっこの悩みをガマンしている人も多いようですが、「過活動膀胱」という改善できる病気が原因かもしれませんよ。
今回は、「もみじクリニック」の院長・山本理哉先生に、過活動膀胱について詳しく説明して頂きました。誰でも自宅で簡単にできる「骨盤底筋体操」も紹介しています。
山本先生の記事をきっかけに、トイレを気にしない有意義な毎日を過ごせる人が増えますように!
「過活動膀胱」は「膀胱炎」と同じような病気ですか?
「膀胱」という文字が入っているので「膀胱炎」と同じ病気かと思われるかもしれませんが、膀胱炎とは関係ない病気です。膀胱炎は細菌感染によって膀胱に炎症が生じ、様々な排尿トラブルが起こる病気ですが、過活動膀胱(OAB)というのは、脳と膀胱の神経伝達異常により膀胱が過敏に反応し、膀胱の筋肉が自分の意思に関係なく収縮してしまうことで、尿が少ししかたまっていないのに強い尿意を感じたり、トイレまで我慢できずに漏らしてしまうといった症状が起こるものです。確かに慢性の膀胱炎や前立腺炎などの感染症が引き金となって、過活動膀胱になるケースはありますし、それらの病気と同時に存在することもあるのですが、細菌感染が原因である病気とは全く異なるカテゴリーの病気と言えます。
過活動膀胱では主にどんな症状が現れますか?
過活動膀胱は、読んで字のごとく「膀胱が過剰に活動する」状態で、主症状は【頻尿】【尿意切迫感】【失禁】の3つです。過活動膀胱は原因がはっきり分からない突発性のものが大半ですが、膀胱炎、前立腺炎、糖尿病、脳梗塞、骨盤内の手術が原因で、脳と膀胱をつなぐ神経回路に障害が起こり、正常な排尿コントロールがなされないことで起きる場合もあります。また、ストレスによって交感神経が緊張して膀胱の異常収縮が起こり、過活動膀胱を引き起こすこともあります。
細菌感染が原因でないという点で、類似する病気に「間質性膀胱炎」というものがありますが、これは間質に炎症が起こることで膀胱の萎縮が生じるもので、膠原病やリウマチのような疾患だと思ってください。症状が似ていることから、診断の際は両者の鑑別が重要となります。
トイレに行く回数がどれくらいだと頻尿?
人の1日のおしっこの回数は平均5〜7回と言われていますので、トイレに行く回数が1日2ケタという人は、過活動膀胱に限らず一度専門医にご相談された方がいいですね。頻尿があると、外出先ではいつもトイレが心配で、仕事や買い物に集中できないなど、日常生活でも不便なことが多いと思います。また日中だけでなく、夜中に何度もトイレに起きる「夜間頻尿」によって、十分な睡眠がとれないこともあります。朝方の目覚める前に何回か続けてトイレに行くといった方はまだいいのですが、2時間おきに睡眠が中断されてトイレに行くことが毎晩続けば、慢性的な睡眠不足を引き起こしかねません。睡眠障害による全身の不調も懸念されます。
夜間にも頻尿が起こるのですね。
「夜間頻尿」も過活動膀胱の症状の1つですが、「夜間多尿」から起こるケースもあり、日中の頻尿と分けてみていく必要があります。夜間多尿とは夜間の尿量が増加する状態をいい、多量の水分摂取が関係している場合もありますが、病気や加齢でホルモン分泌のバランスが崩れてしまうことにより夜間多尿が起こることもあります。
本来、おしっこは午前中に多く作られ、夜になるにつれて尿量は少なくなるのですが、心不全など心臓に疾患があると、起きている状態よりも寝ている時の方が血液を送り出す心臓のポンプが機能して、腎臓への血液循環が良くなり尿量が増えることがあります。
夜間頻尿が夜間多尿から起こっている場合、もしかしたら多尿の原因は心臓の病気から来ているのかもしれません。問診ではおしっこの回数だけでなく、一回の尿量についても患者さんから詳しく聞き、排尿トラブルの裏に大きな病気が潜んでいないか、慎重に診ていく必要があります。
尿意切迫感とはどんな症状ですか?
尿意切迫感とは、突然何の前触れもなく我慢できないほどの尿意を催す症状です。尿意切迫感は大なり小なり過活動膀胱でみられる症状で、過活動膀胱の診断の際は尿意切迫感が必須条件とされています。尿失禁の症状についてお聞かせください。
尿失禁は大きく分けると、「腹圧性尿失禁」「溢流性尿失禁」「切迫性尿失禁」の3つに分類されます。「腹圧性尿失禁」は、くしゃみや咳をした時、重いものを持った時、大声で笑った時など腹圧がかかった時に起こる尿失禁で、女性に多く見られるものです。出産や年齢にともない、骨盤底筋群の筋肉が緩むことで尿道の閉まりが悪くなり、尿が漏れやすくなるものです。
逆に男性に多いのが、2つ目の「溢流性尿失禁」です。これは前立腺肥大症などの尿が出にくくなる排尿障害によって、膀胱内いっぱいに溜まった尿が溢れるように流れ出る状態が起きるものです。いつも残尿感があり、患者さんにとっては辛い症状と言えます。高齢の人に多くみられるものです。
過活動膀胱に関係するのが、3つ目の「切迫性尿失禁」です。これは突然強い尿意を感じ、トイレまで我慢できずに漏らしてしまうといったものです。自分の意思とは関係なく膀胱が過敏に反応してしまうため、排尿コントロールが上手く機能せず、尿意を感じたらすぐにおしっこが出てしまうこともあります。切迫性尿失禁は性別を問わずみられる症状です。
過活動膀胱の診断はどのように行うのですか?
過活動膀胱が疑われる時は、「過活動膀胱症状質問票(OABSS)」という問診票を使って、症状の程度や頻度をみていきます。問診を行えば、過活動膀胱であるかどうかが大方分かりますが、実際の症状と患者さん自身の感覚がずれていたり、間違って記憶していたり、中には過活動膀胱とまったく同じ症状がみられる他の病気もありますから、問診票に当てはまるからと言って過活動膀胱と決めつけることはできません。決め手となる症状がないため、過活性膀胱の診断では他の病気との鑑別が重要となります。おしっこをした後に出し切れていない残尿がある場合は、基本的には過活動膀胱とは言いませんから、残尿測定などの検査を行ったり、患者さんに排尿日誌を付けてもらうことでより正確な診断を行います。
治療についてお聞かせください。
過活動膀胱の治療では、抗コリン薬、β3作動薬といったお薬を使う薬物療法で、症状を軽減させるのが一般的です。お薬で膀胱を収縮させる異常伝達を抑制させると、尿意に対して鈍感になり、これまで尿が少したまっただけでトイレに行きたくなっていたのが、ある程度尿がたまるまで我慢できるようになります。尿をためる機能が高まることで一回のおしっこの量が増え、頻尿や切迫感が改善されます。
また、骨盤底筋を鍛えることで尿トラブルが軽減できますから、尿漏れの改善・予防のために、「骨盤底筋体操」を推奨しています。
「骨盤底筋体操」とはどんなことをするのですか?
骨盤底筋体操とは、尿道や肛門を閉める働きをしている骨盤底筋肉群を鍛える体操です。女性なら膣を閉めるという動作があるので、尿道を閉める感覚は分かりやすいと思いますが、男性だとどこに力を入れたらいいのか難しいんですよね。骨盤底筋体操にはいろんなやり方がありますが、男性でも簡単にできる方法があるのでご紹介しましょう。まずは、ピンポン球を1つ用意してください。立った姿勢でお尻の上の方にピンポン球をはさみ、落ちないようにお尻をグッと閉めます。しばらくその状態で保ったあと、お尻の筋肉を緩めてポトンと落としてください。この時、お尻を突き出さないように注意してくださいね。ピンポン球を乗せる、落とすを繰り返すことで、尿道が締り、緩まり、括約筋が鍛えられます。排尿障害の種々な症状を改善・予防することができますので、ご自宅で是非やってみてください。
過活動膀胱の患者はどれぐらいいるのですか?
昔は「神経因性頻尿」と呼ばれていて、「過活動膀胱」という言葉が一般の方に知られるようになったのはここ最近のことです。過活動膀胱の人は日本で810万人とも言われていますが、そのうち受診されている方は1/4足らずで、低い割合となっています。過活動膀胱は治療せずに放置したからといって、死に至るような病気ではありませんが、トイレのことが気になって旅行や映画を楽しめない、外出するのが億劫になる、というのでは生活の質も下がってしまいます。過活動膀胱は治療によって十分改善できる病気なので、少しでも多くの方に病気の存在を知ってもらい、専門医を受診してもらって、おしっこの悩みから解放できるよう、啓蒙活動を行っていく必要があると考えています。
最後に、診療を通じて感じていることはありますか?
「恥ずかしい」「抵抗がある」という気持ちがあって、泌尿器科に行きにくいと感じている方が多いようです。女性は特にそうなんでしょうね。実は私の母も泌尿器科に進みたいと話した時に、複雑そうな顔をしたのを覚えています。昔は、「泌尿器科」=「性病をメインに治療するところ」といったイメージが強かったかもしれませんが、実は泌尿器科の診療は幅広く、副甲状腺の病気なども取り扱っていて、頚部の手術も行うことがあります。全身管理ができないといけない科なのですよ。
泌尿器科に行きづらいと感じる患者さんに配慮して、あえて医院名に「泌尿器科」を入れなかったのですが、当院では循環器科専門医として副院長が内科診療も一緒に行っていますので、どなたでも楽な気持ちで受診して頂けたらと思います。
おしっこの悩みは生涯毎日のこと。気になる状態のままで暮らすのは、すごくもったいないことだと思います。適切な治療で改善される症状も多いですから、おしっこのことで1人でずっと悩んできたという方、尿の不調は年齢のせいだと諦めていた方は、思い切って泌尿器科の門をくぐってみませんか? 「相談して良かった」と、きっと思いますよ!
医師のプロフィール
山本理哉先生
●順天堂大学医学部卒業●東京大学泌尿器科入局
●東京都立駒込病院
●東京大学医学部附属病院助手」
●日赤医療センター
●岡山大学泌尿器科
●広島市民病院
■□■□ 2025年12月によく読まれた記事をCHECK! □■□■
命にかかわる病気ではありませんが、経過観察と言われたら生理の変化に気を付けて。過多月経や月経痛がひどくなるなどの場合は早めに産婦人科に相談しましょう。
実は10代、20代の女性の死因上位に挙げられる摂食障害。
人の価値や美しさは、体型や体重で決まるものではありません。
適切なカウンセリングで過度な痩せ願望やストレスから自分の体を守りましょう。
幼児や児童に感染することが多く、発症すると喉の痛み、熱、発疹などといった風邪と似た症状が起こります。また、痛みはないのですが、舌の表面に赤いぶつぶつができることがあります。
尋常性疣贅は、「ヒト乳頭腫ウイルス」というウイルスの一種が皮膚に感染してできます。手あれや髭剃り後など、目に見えないくらいの小さな傷からでもウイルスが侵入します。どこの部位にもできる可能性があるのです。
咽喉頭異常感症は心理的要因が大きいといわれています。
喉がイガイガする、圧迫感がある、引っ掛かったり、絡んだような感じがするなど
考えれば考えるほど、喉に違和感を抱き、そのストレスが引き金になって症状を引き起こすことも多いようです。
「不安障害」とはその名の通り、不安な気持ちが強くなる病気です。
ある特定の状況や場所で非常に強い不安に襲われ、身体のいろいろな部分に様々な症状が現われたり、不安を避けようとする「回避行動」をとるようになったり、また安心を得るために無意味な行動を反復してしまうといったことが起こり、人によってはそれが原因で社会生活に支障をきたすこともあります。