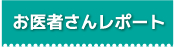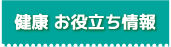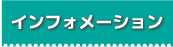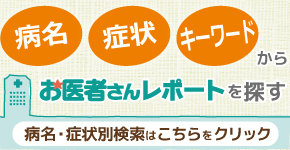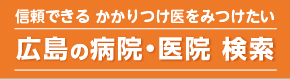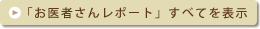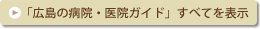広島の頼れるかかりつけ医&病院・医院・クリニックに出会える健康情報サイト
(この記事は2013年10月1日時点の情報です)
泌尿器科すみいクリニック
【住所】広島市佐伯区五日市駅前3-4-21
【TEL】 082-921-8068

経験したことがある人は、尿路結石の痛さについて「想像を絶する痛さ」と表現します。難産に匹敵する痛さとも言われ、しかも症状は前ぶれもなく突然現れることがほとんど。夜中に七転八倒して救急車で搬送される人もいるそうです。
今回は、「泌尿器科すみいクリニック」の院長、角井徹先生に尿路結石の症状や原因、治療についてお話を伺いました。
食生活の乱れから、若い男性に多いと言われる尿路結石。予防や再発防止のためには食生活でどのようなことに気を付けたら良いかアドバイスも頂きました。
中には、じわじわ詰まったような慢性的な鈍痛であったり、痛みを感じないこともあります。また、血尿が出ることもあります。石が尿管を傷つけて出血し尿に混じって出るんですね。石によって尿が積止められるため、濁った尿が出ることもあります。
「石が尿路でゴロゴロ転がるから痛いの?」と質問される方もいらっしゃいますが、そうではなくて、石が尿路に降りることで尿の流れを悪くしてしまうんですね。ダムの水がせき止められるように、尿の通りを塞いでしまう状態になるんです。そうすると腎臓が腫れて、腎臓を包んでいる膜が緊張し、それが突発的な痛みとして現れるのです。
大きな石だと徐々に詰まるのであまり痛みは感じません。石があっても気付かないままの人も中にはいます。細い管に小さな石が詰まった時に、突然の激しい痛みが現れるのです。
汗をたくさんかいた後などは尿量が減るので過飽和状態になりやすく、尿路結石の症状が夏場に現れやすいのはそのためです。また、就寝中は体内に水分補給されずに尿が濃くなりますから、夜中眠っていたら急に痛くなったというケースも多いですね。
尿酸値が異常に高くなる高尿酸血症というのがあって、これは痛風の患者さんに多いのですが、腎臓から尿酸がたくさん排出されるために、尿酸結石ができやすくなります。
それと食生活が大いに関係します。動物性タンパク質を過剰摂取すると、尿中のシュウ酸、尿酸、カルシウム排泄を増加させるため、結石ができ形成されやすくなります。男性に尿路結石が多いのも、女性の方が食事に気を付けている人が多いからだと思います。
年齢的には、20代30代の若い方に多いですね。10人のうち1人が一生の間に尿路結石になるというデータもあるほど頻度の高い病気ですから、規則正しい食生活を意識して予防に取り組んで頂けたらと思います。
石が動いて下の方で詰まるとまた痛くなるのですが、小さい結石であれば鎮痛剤や利尿剤を用いて自然に体外に排出されるのを待つことになります。
残念ながら、石を小さくする特効薬というのはありません。尿酸結石では尿をアルカリ化することで結石の形成を抑えることができるのですが、最も多いシュウ酸結石に対しては有効なお薬は存在しません。
昔は入院が必要な手術が多く、確か泌尿器科医になって初めて経験した手術が尿路結石の手術でしたが、今では通院治療が主流です。石に直接衝撃波を当てて砂状にし体外に排出させる体外衝撃波結石破砕術が導入されてより、入院が不要になった症例が多くなりました。
ほうれん草のお浸しを頂く時に、かつお節やちりめんじゃこをかけて食べるでしょ。あれは、美味しい食べ方というだけでなく、シュウ酸を体内に吸収させないための工夫なんです。
カルシウムを含む食品と一緒に食べることで、シュウ酸が体内に吸収される前に、腸内でシュウ酸とカルシウムが結合してシュウ酸カルシウムになります。シュウ酸カルシウムは水には溶けない性質なので、尿中のシュウ酸が増えることがないんです。昔からある食品の組み合わせには、そういう知恵が自然にあったんですね。
せっかく石がなくなっても、食生活を改善しなければ尿路結石は再発してしまいます。尿路結石の予防と再発防止のために、動物性たんぱく質の摂取をひかえたバランスの良い食生活と水分補給を心がけてください。
水分を過度に取り過ぎるとそれが原因で頻尿になったり、夜中に何度もトイレに行って睡眠不足につながり、体調不良を引き起こすこともあります。もちろん水分を摂らないよりも、しっかり摂った方が良いのですが、それも程度の問題です。尿路結石には水分補給が有効だとお話しましたが、適度な範囲で水分補給を心掛けて頂けたらと思います。
診療に来られたら必ず検尿して、糖や血液やタンパクが出ていないかを調べるのですが、その際に糖尿病など泌尿器科で扱う以外の病気が見つかることも多いです。おしっこは健康状態や病気など、様々なことを教えてくれます。皆さんもご自分のおしっこの状態を観察する癖をつけて、「量が少ないな」「回数が多いな」「ちょっとおかしいな」と思うことがありましたら、気軽に泌尿器科に相談して下さい。
泌尿器科を受診する際には、排尿回数や、1回の尿量がどのくらいで、1日でどのくらいおしっこが出ているかを記録したものを見せてもらえると、その後の診断がスムーズです。「紙コップ1杯分」といった大まかな目安で構いません。ご自分の排尿状況を把握するためにも、排尿日誌をつけて欲しいですね。
●同付属病院勤務
●厚生連尾道総合病院
●広島大学病院
●広島大学 医学博士号取得
●厚生連広島総合病院
‐資格・所属学会‐
・日本泌尿器科学会
・専門医性感染症学会
・認定医性機能学会
角井徹 先生(泌尿器科)
想像を絶する痛さに七転八倒。バランスの良い食生活で尿路結石を予防しよう!
泌尿器科すみいクリニック
【住所】広島市佐伯区五日市駅前3-4-21
【TEL】 082-921-8068

泌尿器診療全般のほか、ED(勃起障害)治療や性感染症を専門に扱う角井院長
経験したことがある人は、尿路結石の痛さについて「想像を絶する痛さ」と表現します。難産に匹敵する痛さとも言われ、しかも症状は前ぶれもなく突然現れることがほとんど。夜中に七転八倒して救急車で搬送される人もいるそうです。
今回は、「泌尿器科すみいクリニック」の院長、角井徹先生に尿路結石の症状や原因、治療についてお話を伺いました。
食生活の乱れから、若い男性に多いと言われる尿路結石。予防や再発防止のためには食生活でどのようなことに気を付けたら良いかアドバイスも頂きました。
尿路結石にはどんな症状があるのですか?
尿路結石とは、尿路つまり尿の通り道に石が詰まってしまうことにより起きる症状のことです。症状で最も多いのは痛みですね。尿路結石を経験された方の多くは、七転八倒してのたうち回る猛烈な痛みに襲われたと話されるほど、腰背部・側腹部・下腹部に激痛が起こるのが典型的な特徴です。何の前触れもなく突然現れる痛みに、救急車で搬送される方もいるほどです。中には、じわじわ詰まったような慢性的な鈍痛であったり、痛みを感じないこともあります。また、血尿が出ることもあります。石が尿管を傷つけて出血し尿に混じって出るんですね。石によって尿が積止められるため、濁った尿が出ることもあります。
激しい痛みが起こるのはなぜですか?
石は腎臓で作られるのですが、腎臓に石があっても腎臓が痛くなることはありません。それが尿管や尿道に降りてきて、引っかかったり詰まったりすることで痛みの症状が現れるのです。「石が尿路でゴロゴロ転がるから痛いの?」と質問される方もいらっしゃいますが、そうではなくて、石が尿路に降りることで尿の流れを悪くしてしまうんですね。ダムの水がせき止められるように、尿の通りを塞いでしまう状態になるんです。そうすると腎臓が腫れて、腎臓を包んでいる膜が緊張し、それが突発的な痛みとして現れるのです。
大きな石だと徐々に詰まるのであまり痛みは感じません。石があっても気付かないままの人も中にはいます。細い管に小さな石が詰まった時に、突然の激しい痛みが現れるのです。
どうして石ができるのですか?
シュウ酸や尿酸がカルシウムと結合して、結石が形成されます。シュウ酸や尿酸は尿の中に溶け込んでいるのですが、尿の濃度が過飽和状態になると結晶が現れ、結晶が塊になり結石へと成長していきます。汗をたくさんかいた後などは尿量が減るので過飽和状態になりやすく、尿路結石の症状が夏場に現れやすいのはそのためです。また、就寝中は体内に水分補給されずに尿が濃くなりますから、夜中眠っていたら急に痛くなったというケースも多いですね。
尿酸値が異常に高くなる高尿酸血症というのがあって、これは痛風の患者さんに多いのですが、腎臓から尿酸がたくさん排出されるために、尿酸結石ができやすくなります。
どんな人が尿路結石になりやすいですか?
尿路結石は水分摂取不足で発生しやすいので、汗をかきやすい人や水分をあまり摂らない人は注意が必要です。それと食生活が大いに関係します。動物性タンパク質を過剰摂取すると、尿中のシュウ酸、尿酸、カルシウム排泄を増加させるため、結石ができ形成されやすくなります。男性に尿路結石が多いのも、女性の方が食事に気を付けている人が多いからだと思います。
年齢的には、20代30代の若い方に多いですね。10人のうち1人が一生の間に尿路結石になるというデータもあるほど頻度の高い病気ですから、規則正しい食生活を意識して予防に取り組んで頂けたらと思います。
治療はどのように行うのでしょうか?
対処療法として、痛みを取り除く処置を行います。尿路がふさがれているために痛いのですから、尿管を弛緩させるお薬を使って緊張を取り除き、尿路を再開することで痛みを抑えることができます。石が動いて下の方で詰まるとまた痛くなるのですが、小さい結石であれば鎮痛剤や利尿剤を用いて自然に体外に排出されるのを待つことになります。
残念ながら、石を小さくする特効薬というのはありません。尿酸結石では尿をアルカリ化することで結石の形成を抑えることができるのですが、最も多いシュウ酸結石に対しては有効なお薬は存在しません。
昔は入院が必要な手術が多く、確か泌尿器科医になって初めて経験した手術が尿路結石の手術でしたが、今では通院治療が主流です。石に直接衝撃波を当てて砂状にし体外に排出させる体外衝撃波結石破砕術が導入されてより、入院が不要になった症例が多くなりました。
食生活で注意することはありますか?
ほうれん草、タケノコ、春菊などアクのある野菜には、シュウ酸が多く含まれます。だからと言って、「ほうれん草を食べるな」ということではなく食材を上手に組合せて、シュウ酸が体内に吸収されにくい食べ方をするようにしましょう。ほうれん草のお浸しを頂く時に、かつお節やちりめんじゃこをかけて食べるでしょ。あれは、美味しい食べ方というだけでなく、シュウ酸を体内に吸収させないための工夫なんです。
カルシウムを含む食品と一緒に食べることで、シュウ酸が体内に吸収される前に、腸内でシュウ酸とカルシウムが結合してシュウ酸カルシウムになります。シュウ酸カルシウムは水には溶けない性質なので、尿中のシュウ酸が増えることがないんです。昔からある食品の組み合わせには、そういう知恵が自然にあったんですね。
カルシウムを多く摂取するのも良くないんですか?
結石の形成にはカルシウムが関係しますが、カルシウム摂取をひかえる必要はありません。むしろ腸内で結合するカルシウムが少ないとシュウ酸が体内吸収されやすくなり、尿路結石になるリスクが高くなってしまいますから、カルシウム不足にならないように気を付けて頂きたいですね。せっかく石がなくなっても、食生活を改善しなければ尿路結石は再発してしまいます。尿路結石の予防と再発防止のために、動物性たんぱく質の摂取をひかえたバランスの良い食生活と水分補給を心がけてください。
最後に「広島ドクターズ」の読者にアドバイスをお願いします。
健康をテーマにしたテレビ番組などで、「○○を食べると体に良い」といったことを聞くと、自分もやってみようと思いますよね。「水分をしっかり補給しましょう」といった呼びかけを耳にすると、「いっぱい水を飲むぞ!」と頑張ってしまう方もおられますが、「程々に」ということを忘れないでもらいたいのです。水分を過度に取り過ぎるとそれが原因で頻尿になったり、夜中に何度もトイレに行って睡眠不足につながり、体調不良を引き起こすこともあります。もちろん水分を摂らないよりも、しっかり摂った方が良いのですが、それも程度の問題です。尿路結石には水分補給が有効だとお話しましたが、適度な範囲で水分補給を心掛けて頂けたらと思います。
診療に来られたら必ず検尿して、糖や血液やタンパクが出ていないかを調べるのですが、その際に糖尿病など泌尿器科で扱う以外の病気が見つかることも多いです。おしっこは健康状態や病気など、様々なことを教えてくれます。皆さんもご自分のおしっこの状態を観察する癖をつけて、「量が少ないな」「回数が多いな」「ちょっとおかしいな」と思うことがありましたら、気軽に泌尿器科に相談して下さい。
泌尿器科を受診する際には、排尿回数や、1回の尿量がどのくらいで、1日でどのくらいおしっこが出ているかを記録したものを見せてもらえると、その後の診断がスムーズです。「紙コップ1杯分」といった大まかな目安で構いません。ご自分の排尿状況を把握するためにも、排尿日誌をつけて欲しいですね。
医師のプロフィール
角井徹先生
●広島大学医学部 卒業●同付属病院勤務
●厚生連尾道総合病院
●広島大学病院
●広島大学 医学博士号取得
●厚生連広島総合病院
‐資格・所属学会‐
・日本泌尿器科学会
・専門医性感染症学会
・認定医性機能学会
■□■□ 2025年12月によく読まれた記事をCHECK! □■□■
命にかかわる病気ではありませんが、経過観察と言われたら生理の変化に気を付けて。過多月経や月経痛がひどくなるなどの場合は早めに産婦人科に相談しましょう。
実は10代、20代の女性の死因上位に挙げられる摂食障害。
人の価値や美しさは、体型や体重で決まるものではありません。
適切なカウンセリングで過度な痩せ願望やストレスから自分の体を守りましょう。
幼児や児童に感染することが多く、発症すると喉の痛み、熱、発疹などといった風邪と似た症状が起こります。また、痛みはないのですが、舌の表面に赤いぶつぶつができることがあります。
尋常性疣贅は、「ヒト乳頭腫ウイルス」というウイルスの一種が皮膚に感染してできます。手あれや髭剃り後など、目に見えないくらいの小さな傷からでもウイルスが侵入します。どこの部位にもできる可能性があるのです。
咽喉頭異常感症は心理的要因が大きいといわれています。
喉がイガイガする、圧迫感がある、引っ掛かったり、絡んだような感じがするなど
考えれば考えるほど、喉に違和感を抱き、そのストレスが引き金になって症状を引き起こすことも多いようです。
「不安障害」とはその名の通り、不安な気持ちが強くなる病気です。
ある特定の状況や場所で非常に強い不安に襲われ、身体のいろいろな部分に様々な症状が現われたり、不安を避けようとする「回避行動」をとるようになったり、また安心を得るために無意味な行動を反復してしまうといったことが起こり、人によってはそれが原因で社会生活に支障をきたすこともあります。