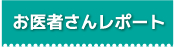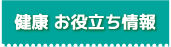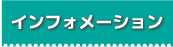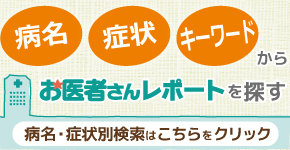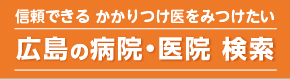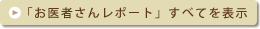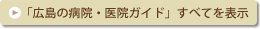広島の頼れるかかりつけ医&病院・医院・クリニックに出会える健康情報サイト
(この記事は2014年9月4日時点の情報です)
おだ内科クリニック
【住所】広島県広島市中区幟町13-4 広島マツダビル2F
【TEL】 082-502-1051

海外滞在中に、最も気を付けたいのは感染症です。国内で感染者が出て話題になっているデング熱も注意したい感染症のひとつで、海外で健康に過ごすためには感染症に対する予防と、事前に渡航先の情報を確認しておくことが大切です。
そんな海外渡航者の強い味方になってくれるのが、渡航外来(トラベルクリニック)です。ワクチン予防接種をはじめ感染症流行情報の提供など、渡航者の健康をサポートしてくれる医療です。
今回は、中区幟町にある「おだ内科クリニック」の小田健司院長に、海外でかかりやすい感染症をいくつか教えて頂き、予防のためのアドバイスを伺いました。渡航予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
海外では時差や気候だけでなく、衛生状態や医療事情も日本とは大きく異なります。また日本では見られない感染症もたくさんあり、渡航する際は予防接種を受けるなど、感染症から身を守る予防策も考えねばなりません。
渡航外来(トラベルクリニック)では、日本渡航医学会、日本旅行医学会の資格を持つ専門医が、海外渡航者を対象に、渡航前相談、渡航前予防接種の提供、予防薬の処方、英文診断書・証明書の作成、情報提供などを行っています。
日本とは環境が違う外国で、健康で安全に過ごせるよう、適切なアドバイスと予防医療を提供しています。
国や地域別に推奨するワクチンについては、検疫所のホームページでも調べることができますが、たくさんある予防ワクチンの中から自分に有効なものを選ぶのは難しいです。
同じ国でも都市部と農村部を訪れるのとでは衛生環境が違ってくるし、滞在が長期に渡ればそれだけ感染症にかかるリスクが高くなります。スポーツや仕事で行かれる場合は、渡航先でケガをする可能性もありますから、傷口や輸血が感染経路となる疾患に対しての予防も考えなければなりません。
トラベルクリニックでは、渡航先、滞在期間、渡航目的を考慮して、その人に合った予防接種や予防薬の種類を判断し、スケジュールを立てて予防接種を行います。
トラベルクリニックで扱うワクチンや予防薬(高山病予防薬・マラリア予防薬など)は、一般のクリニックにないものがほとんどです。輸入ワクチンを常備している医療機関は非常に少なく、広島では広大病院か当院だけだと思います。
同じく飲食物から感染するものとして、【A型肝炎】【腸チフス】があります。どちらも有効なワクチンがあるので、渡航前に予防接種を受けることで予防が可能となります。
海外では飲食物から病気に感染することが多いため、飲食物への注意が大切です。現地では衛生状態が悪いところには行かないようにして、不衛生な屋台などでの飲食は避けましょう。できれば瓶や缶など、栓がしてあるものを飲食する方が安全ですね。飲み物に入っている氷も、氷を作った水が汚染していることがあるので注意してください。
重症化すると死に至る危険がある【マラリア】は、ワクチンはありませんが、有効な予防薬があります。亜熱帯・熱帯地域などの蚊が多い地域に1週間以上滞在する場合は、予防薬を服用した方が安全です。
最近、国内で感染者が出て話題になっている【デング熱】も蚊に刺されて感染しますが、デング熱にはワクチンや予防薬はありません。感染を予防するには、「蚊に刺されないこと」です。
虫よけスプレーや塗り薬を使ったり、夏でも長袖を着るなどして肌の露出をひかえて、蚊に刺されないための対策をしましょう。虫よけスプレーは日本で買うよりも、現地で売られているDEETを含む防虫スプレーの方が、持続性があって効果が高いです。蚊を近づけないために、蚊取り線香や電池式虫よけなどもあるといいですね。
蚊の繁殖する雨季は特に注意して、海外ではできるだけ蚊に刺されないようにしましょう。
犬に噛まれたら必ず発病するというものではないですが、万が一発病してしまうと現在の医学では治療法はなく、致死率100%であることから、十分に注意してもらいたい病気です。
予防法としては、海外では安易に動物に近づかないことです。もし犬に噛まれたら必ず傷の処置をして、直ちに現地の医療機関を受診し、暴露後接種(噛まれた後、発病前のワクチン接種)を受けください。帰国後も継続してワクチンを接種し、全部で5,6回ワクチンを打つことになります。感染しているかどうかを調べることはできないので、発病を確実に防ぐためにも、必ずワクチン接種を完了させることが必要です。
犬に噛まれた後、迅速な処置ができればいいのですが、海外だと病院がすぐ見つからなかったり、国によってはワクチンがすぐに手に入らないこともあります。ですから、野犬が多い地域への渡航や、医療機関のないような地域に行く場合や、滞在先で動物を扱う仕事をする人は、事前に暴露前予防接種(噛まれる前のワクチン接種)を受けておくことをおすすめします。暴露前予防接種を3回受けておくことで、もし犬に噛まれても、傷の処置をして予防接種を数回打つだけで済みます。
狂犬病は今では日本にない病気で馴染みがないですが、狂犬病がない国というのは日本とオーストラリアなどの一部の国だけで、先進国を含む世界のほとんどの国に存在します。国内にいるのと同じ感覚で、むやみに犬に近づくことはやめましょう。
破傷風は子どもの頃に受ける3種混合ワクチンに含まれていますが、抗体が持続するのは20歳台前半くらいまでです。日本脳炎、麻疹、風疹、百日咳なども、子どもの頃に予防接種を受けていても、抗体がなくなっていることがあり、追加接種が必要な場合があります。50歳以上の方では、予防接種を受けていない世代の方もいらっしゃるので、渡航を機会にご自分に抗体があるか見直してみるといいかもしれませんね。
感染率が高いゆえに注意したいのは、飛沫感染、空気感染する病気です。代表的なものは【インフルエンザ】ですね。インフルエンザは話題になると皆さん殺到して、ワクチンが足りなくなってしまうこともありますが、昨年は大流行の年ではなかったので接種率も低かったようです。
インフルエンザの予防接種は毎年受けておくことで基礎免疫ができて、ある程度かかりにくくなり、かかっても重症化しないと言われています。また、日本では季節性のインフルエンザワクチンを接種できるのが10月から2月くらいまでの期間で、その時期以外だと受けたくても受けられません。インフルエンザは必ず周期的に流行がやってきますし、海外では冬だけ流行しているとは限りませんから、国内外の予防を問わず、年に一度インフルエンザの予防接種を受けた方が良いと思います。
また、感染してもすぐには症状が出ないこともありますので、少なくとも帰国して1ヶ月間は、発熱や下痢など体調に異変がないか、注意してもらいたいと思います。
また、海外旅行に行かれる際は、その国や地域の情報をしっかりと調べておくことです。どんな感染症があるのか? 流行っている病気はないか? 衛生面はどうか? 虫よけが必要か?など、今はインターネットを使えば手軽に調べられますから、健康リスクを事前に確認して、旅行前に備えられることはきちんと準備しておきましょう。
●国立国際医療センターで研修
●広島大学大学院医学系研究科(医学博士号取得)
●広島大学保健管理センターにて健康管理に従事
●広島市立安佐市民病院内科勤務(内科専門医取得)
●広島大学原医研、血液内科助手(病棟医長、外来医長歴任)
●広島大学医学部付属病院内科(原医研)講師(医局長)
●社会保険広島市民病院健康管理センター部長
●FACP称号(米国内科学会上級会員)授与
‐資格・所属学会‐
・医学博士
・日本内科学会認定 総合内科専門医
・身体障害者福祉法指定医(免疫)
・日本渡航医学会会員
・日本旅行医学会認定医
・米国内科学会上級会員
Fellow of American College of Physicians(ACP #01043457)
・米国臨床腫瘍学会会員
Member of American Society of Clinical Oncology
小田健司 先生(内科・渡航外来)
海外渡航者の健康をサポートしてくれる「渡航外来(トラベルクリニック)」
おだ内科クリニック
【住所】広島県広島市中区幟町13-4 広島マツダビル2F
【TEL】 082-502-1051

渡航先での健康リスクを考慮して、ワクチン予防接種のアドバイスや健康指導をしてくれる小田先生。
海外滞在中に、最も気を付けたいのは感染症です。国内で感染者が出て話題になっているデング熱も注意したい感染症のひとつで、海外で健康に過ごすためには感染症に対する予防と、事前に渡航先の情報を確認しておくことが大切です。
そんな海外渡航者の強い味方になってくれるのが、渡航外来(トラベルクリニック)です。ワクチン予防接種をはじめ感染症流行情報の提供など、渡航者の健康をサポートしてくれる医療です。
今回は、中区幟町にある「おだ内科クリニック」の小田健司院長に、海外でかかりやすい感染症をいくつか教えて頂き、予防のためのアドバイスを伺いました。渡航予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
「渡航外来」とは何ですか?
グローバル化が進むにつれて、海外赴任・旅行・留学など、様々な目的で海外を訪れる人は年々増加しています。渡航先もかつては欧米が中心でしたが、今では東南アジア・アフリカ・南米など、多方面に渡るようになりました。海外では時差や気候だけでなく、衛生状態や医療事情も日本とは大きく異なります。また日本では見られない感染症もたくさんあり、渡航する際は予防接種を受けるなど、感染症から身を守る予防策も考えねばなりません。
渡航外来(トラベルクリニック)では、日本渡航医学会、日本旅行医学会の資格を持つ専門医が、海外渡航者を対象に、渡航前相談、渡航前予防接種の提供、予防薬の処方、英文診断書・証明書の作成、情報提供などを行っています。
日本とは環境が違う外国で、健康で安全に過ごせるよう、適切なアドバイスと予防医療を提供しています。
渡航前相談ではどんな相談が多いですか?
ワクチン接種や予防薬についての相談が多いですね。国や地域別に推奨するワクチンについては、検疫所のホームページでも調べることができますが、たくさんある予防ワクチンの中から自分に有効なものを選ぶのは難しいです。
同じ国でも都市部と農村部を訪れるのとでは衛生環境が違ってくるし、滞在が長期に渡ればそれだけ感染症にかかるリスクが高くなります。スポーツや仕事で行かれる場合は、渡航先でケガをする可能性もありますから、傷口や輸血が感染経路となる疾患に対しての予防も考えなければなりません。
トラベルクリニックでは、渡航先、滞在期間、渡航目的を考慮して、その人に合った予防接種や予防薬の種類を判断し、スケジュールを立てて予防接種を行います。
トラベルクリニックで扱うワクチンや予防薬(高山病予防薬・マラリア予防薬など)は、一般のクリニックにないものがほとんどです。輸入ワクチンを常備している医療機関は非常に少なく、広島では広大病院か当院だけだと思います。
海外で最もかかりやすい感染症は?
実際に一番多いのは【旅行者下痢症】です。原因は様々ですが、細菌やウイルスによって腹痛や下痢などを発症することが多く、汚染された水や食べ物から感染します。世界中でみられる感染症ですが、東南アジアやアフリカなど衛生状態が劣悪な環境では、感染リスクが高くなります。旅行者下痢症にはワクチン接種はありませんが、ある程度予防が可能な経口ワクチンがあります。同じく飲食物から感染するものとして、【A型肝炎】【腸チフス】があります。どちらも有効なワクチンがあるので、渡航前に予防接種を受けることで予防が可能となります。
海外では飲食物から病気に感染することが多いため、飲食物への注意が大切です。現地では衛生状態が悪いところには行かないようにして、不衛生な屋台などでの飲食は避けましょう。できれば瓶や缶など、栓がしてあるものを飲食する方が安全ですね。飲み物に入っている氷も、氷を作った水が汚染していることがあるので注意してください。
蚊に刺されて感染する病気も多いそうですね。
蚊が媒介する感染症はいくつかありますが、その中でワクチンがあるのは、【日本脳炎】と【黄熱】です。黄熱は予防接種を受けた証明書がなければ入国できない国もあるので、事前に確認して、渡航に合わせて予防接種を受けるようにしましょう。黄熱ワクチンの予防接種は検疫所で行っています。重症化すると死に至る危険がある【マラリア】は、ワクチンはありませんが、有効な予防薬があります。亜熱帯・熱帯地域などの蚊が多い地域に1週間以上滞在する場合は、予防薬を服用した方が安全です。
最近、国内で感染者が出て話題になっている【デング熱】も蚊に刺されて感染しますが、デング熱にはワクチンや予防薬はありません。感染を予防するには、「蚊に刺されないこと」です。
虫よけスプレーや塗り薬を使ったり、夏でも長袖を着るなどして肌の露出をひかえて、蚊に刺されないための対策をしましょう。虫よけスプレーは日本で買うよりも、現地で売られているDEETを含む防虫スプレーの方が、持続性があって効果が高いです。蚊を近づけないために、蚊取り線香や電池式虫よけなどもあるといいですね。
蚊の繁殖する雨季は特に注意して、海外ではできるだけ蚊に刺されないようにしましょう。
動物の咬傷によって感染する狂犬病とは?
【狂犬病】は、犬に噛まれた際に発病する可能性がある病気です。犬に噛まれたら必ず発病するというものではないですが、万が一発病してしまうと現在の医学では治療法はなく、致死率100%であることから、十分に注意してもらいたい病気です。
予防法としては、海外では安易に動物に近づかないことです。もし犬に噛まれたら必ず傷の処置をして、直ちに現地の医療機関を受診し、暴露後接種(噛まれた後、発病前のワクチン接種)を受けください。帰国後も継続してワクチンを接種し、全部で5,6回ワクチンを打つことになります。感染しているかどうかを調べることはできないので、発病を確実に防ぐためにも、必ずワクチン接種を完了させることが必要です。
犬に噛まれた後、迅速な処置ができればいいのですが、海外だと病院がすぐ見つからなかったり、国によってはワクチンがすぐに手に入らないこともあります。ですから、野犬が多い地域への渡航や、医療機関のないような地域に行く場合や、滞在先で動物を扱う仕事をする人は、事前に暴露前予防接種(噛まれる前のワクチン接種)を受けておくことをおすすめします。暴露前予防接種を3回受けておくことで、もし犬に噛まれても、傷の処置をして予防接種を数回打つだけで済みます。
狂犬病は今では日本にない病気で馴染みがないですが、狂犬病がない国というのは日本とオーストラリアなどの一部の国だけで、先進国を含む世界のほとんどの国に存在します。国内にいるのと同じ感覚で、むやみに犬に近づくことはやめましょう。
それ以外の感染経路でかかる病気で注意したいものは?
傷口から感染する【破傷風】や、体液や血液によって人から人へ感染する【B型肝炎】もワクチンを接種することで予防ができますので、スポーツや仕事でケガをしたり、輸血が必要になる可能性があるという方は、予防接種を受けておくことをおすすめします。破傷風は子どもの頃に受ける3種混合ワクチンに含まれていますが、抗体が持続するのは20歳台前半くらいまでです。日本脳炎、麻疹、風疹、百日咳なども、子どもの頃に予防接種を受けていても、抗体がなくなっていることがあり、追加接種が必要な場合があります。50歳以上の方では、予防接種を受けていない世代の方もいらっしゃるので、渡航を機会にご自分に抗体があるか見直してみるといいかもしれませんね。
エボラ出血熱が最近話題になっていますが・・・。
【エボラ出血熱】は40年近く前からある病気で、アフリカ地域で多く発生します。ワクチンや予防薬がないうえ致死率が高く、流行すると大変な病気ですが、接触感染ですから感染率は高くありません。感染率が高いゆえに注意したいのは、飛沫感染、空気感染する病気です。代表的なものは【インフルエンザ】ですね。インフルエンザは話題になると皆さん殺到して、ワクチンが足りなくなってしまうこともありますが、昨年は大流行の年ではなかったので接種率も低かったようです。
インフルエンザの予防接種は毎年受けておくことで基礎免疫ができて、ある程度かかりにくくなり、かかっても重症化しないと言われています。また、日本では季節性のインフルエンザワクチンを接種できるのが10月から2月くらいまでの期間で、その時期以外だと受けたくても受けられません。インフルエンザは必ず周期的に流行がやってきますし、海外では冬だけ流行しているとは限りませんから、国内外の予防を問わず、年に一度インフルエンザの予防接種を受けた方が良いと思います。
帰国後に気を付けたいことは?
飛行機の中などで発熱や下痢がみられた場合は、検疫に申し出てもらえばいいのですが、検疫を通り過ぎて、国内に入ってから何らかの症状が現れた場合ですね。一般の医療機関を受診されると思いますが、その際には必ず医師に渡航歴を話して下さい。また、感染してもすぐには症状が出ないこともありますので、少なくとも帰国して1ヶ月間は、発熱や下痢など体調に異変がないか、注意してもらいたいと思います。
最後に「広島ドクターズ」の読者にアドバイスをお願いします。
ワクチンの種類によっては1回きりで済むものもあれば、接種間隔を数週間あけて、複数回打たないといけないものもあります。海外での滞在期間が長くなる場合は、ワクチンの効果が持続するような打ち方も考えなければなりませんから、渡航の予定が決まったら時間に余裕を持って、計画的にワクチンを接種するようにしましょう。また、海外旅行に行かれる際は、その国や地域の情報をしっかりと調べておくことです。どんな感染症があるのか? 流行っている病気はないか? 衛生面はどうか? 虫よけが必要か?など、今はインターネットを使えば手軽に調べられますから、健康リスクを事前に確認して、旅行前に備えられることはきちんと準備しておきましょう。
医師のプロフィール
小田健司先生
●広島大学医学部 卒業●国立国際医療センターで研修
●広島大学大学院医学系研究科(医学博士号取得)
●広島大学保健管理センターにて健康管理に従事
●広島市立安佐市民病院内科勤務(内科専門医取得)
●広島大学原医研、血液内科助手(病棟医長、外来医長歴任)
●広島大学医学部付属病院内科(原医研)講師(医局長)
●社会保険広島市民病院健康管理センター部長
●FACP称号(米国内科学会上級会員)授与
‐資格・所属学会‐
・医学博士
・日本内科学会認定 総合内科専門医
・身体障害者福祉法指定医(免疫)
・日本渡航医学会会員
・日本旅行医学会認定医
・米国内科学会上級会員
Fellow of American College of Physicians(ACP #01043457)
・米国臨床腫瘍学会会員
Member of American Society of Clinical Oncology
■□■□ 2026年1月によく読まれた記事をCHECK! □■□■
命にかかわる病気ではありませんが、経過観察と言われたら生理の変化に気を付けて。過多月経や月経痛がひどくなるなどの場合は早めに産婦人科に相談しましょう。
実は10代、20代の女性の死因上位に挙げられる摂食障害。
人の価値や美しさは、体型や体重で決まるものではありません。
適切なカウンセリングで過度な痩せ願望やストレスから自分の体を守りましょう。
幼児や児童に感染することが多く、発症すると喉の痛み、熱、発疹などといった風邪と似た症状が起こります。また、痛みはないのですが、舌の表面に赤いぶつぶつができることがあります。
尋常性疣贅は、「ヒト乳頭腫ウイルス」というウイルスの一種が皮膚に感染してできます。手あれや髭剃り後など、目に見えないくらいの小さな傷からでもウイルスが侵入します。どこの部位にもできる可能性があるのです。
咽喉頭異常感症は心理的要因が大きいといわれています。
喉がイガイガする、圧迫感がある、引っ掛かったり、絡んだような感じがするなど
考えれば考えるほど、喉に違和感を抱き、そのストレスが引き金になって症状を引き起こすことも多いようです。
「不安障害」とはその名の通り、不安な気持ちが強くなる病気です。
ある特定の状況や場所で非常に強い不安に襲われ、身体のいろいろな部分に様々な症状が現われたり、不安を避けようとする「回避行動」をとるようになったり、また安心を得るために無意味な行動を反復してしまうといったことが起こり、人によってはそれが原因で社会生活に支障をきたすこともあります。