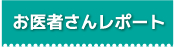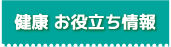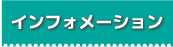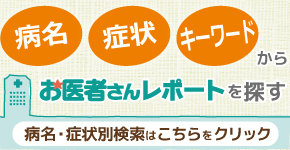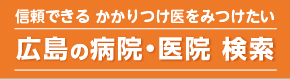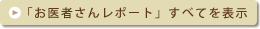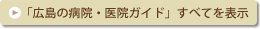広島の頼れるかかりつけ医&病院・医院・クリニックに出会える健康情報サイト
(この記事は2014年9月15日時点の情報です)
こころ・チャイルド・クリニック
【住所】広島市安佐南区伴南1丁目5-18-8 西風新都ゆめビル 3階
【TEL】 082-849-5519

「育てにくい」と感じるのは、間違った子育てをしているから? それとも、こころの発達に問題があるのかしら?
育児を楽しみたいのに、イライラしたり心配してばかりと言う方に、今回は、「こころ・チャイルド・クリニック」の院長で、「子どもの心相談医」の資格をもつ野村真二先生を伺い、上手な子育てのアドバイスを教えてもらいました。
小児科は子どもが病気にかかった時や健診で行くところですが、育児の悩みや心の発達相談にものってくれる、子育てママ・パパの応援団でもあるのですよ。
子育てに正解も不正解もありませんが、今の育児に問題や疑問を感じている方にとって野村先生のお話が少しでも参考になればと思います。
また、最近は発達障害の認知度が高まり、お母さん方も知識が豊富です。お友達にできることが自分の子どもにできないと、発達障害ではないかと不安になります。
できない行動ばかりチェックしてしまう一方で、できた行動は気に留めず、流してしまっていませんか? できたことを見つけて、親が子どもに「できたね」と伝えることは、とても大切なことです。子どもは親に認められたことで自信がつき、ほめられると次のステップを目指そうと頑張るものです。
「ほめて育てたいけど、うちの子はできないことばかりで、ほめるところがないんです」と、おっしゃられるお母さんもいますが、そんなことはありません。昨日できなかったこと、1週間前はできなかったこと、1ヶ月前はできなかったことが、お母さんが気づかない間にいつの間にかできるようになっているはずです。視点を変えるだけで、「できたね」が溢れていることに気付きます。
子どものできない行動ばかり探していたら、イライラして疲れるのは当然です。「できない」ではなく「できた」ことに注目して、できたことを親子でたくさん喜び、さらにはその「できた」の中から、その子の素質を見抜いて伸ばしてあげることを心掛ければ、育児はもっと楽しくなると思います。
例えば片付けができないお子さんだったら、まずは「お母さんも手伝うから一緒に片付けよう」と声を掛けてあげてください。その次は、「1人で片付けをやってごらん。できなかったらお母さんも手伝うね」と少しステップをあげてみる。1人で片付けができたら、「ちゃんとできたね。えらいね」とほめてあげてください。
「できたね」とほめてあげることは、とても大切です。そして、ほめるのと同時に喜んであげることも。「できるようになったら、お母さんはこんなに喜んでくれるんだ」と、子どものやる気を刺激します。
目標に向かって、小さなステップを1つずつクリアしていけば、できる行動はどんどん増えていきます。
また、よくお母さんからの質問で、「できたらご褒美をあげる」というのは、甘やかしていることになりませんか?と聞かれることがありますが、ちょっとしたご褒美ならあってもいいと思います。
目標を設定し、それを子どもに明確に示してあげることは悪いことではありません。できるようになったらお母さんも喜んでくれるし、自分もご褒美がもらえて嬉しいから、「次も頑張ろう!」と意欲向上につながります。ただ、お金がかかるご褒美は良くないので、そこは気を付けて下さいね(笑)
できなかったことに対しては、叱らず、焦らず、放っておかずに、まずはやり方をきちんと教えて、少しずつできるようにサポートしてあげましょう。そして、できたことを認め、しっかりとほめてあげる。ほめて育てることは、しつけや教育のためだけでなく、将来自己評価のしっかりできる大人になることにもつながります。
ですが、子どもの頃から高い目標ばかり目指して、なかなか親にほめてもらえない環境で育つと、小さな達成では満足感が得られず、頑張った自分に対しても厳しい評価をしてしまいます。時には、できなかった自分に対して、ダメな人間だと追いつめてしまうこともあります。
成功体験を実感することで、子どもは「やればできるんだ」と自信がつきます。ほめてあげること、認めてあげることは、自己肯定感を育むための大切な親子のコミュニケーションだといえます。
子どもが将来、自分のダメな部分も含めて自分を好きでいられる人になれるように、親子の心の触れ合いを大切にして欲しいと思います。
叱る時は、まずは子どもの気持ちを安定させてあげることが大切です。場所を変えて、気分を沈めて、落ち着いてから話をしましょう。お母さんも一呼吸置いて、クールダウンしてから。冷静になると、自分の思い通りにならなかったから腹を立てていたり、自分の気分で怒っていたりすることに気付くかもしれません。深呼吸をする、お水を飲むなど、自分に合ったリラックス方法で気分を落ち着かせ、子どもが悪いことをした時は、なぜ悪いかを教えましょう。
指示は怒鳴ったりせず、穏やかに繰り返すようにしましょう。子どもの問題行動には必ず理由があります。「〜したい気持ちはわかるけど、…しようね」のように共感的表現をすると指示が入りやすくなります。
心の発達のためには、語りかけや会話、絵本の読み聞かせがすごく大事です。それと、自然の中で遊ばせて、同年代の子たちとコミュニケーションをとっていくことも。健康のために運動習慣をつけていくことも必要で、遊びの中でできるだけ体を動かすようにすると、食欲が増し、心地よい疲労感から睡眠がもたらされ、骨の成長や成長ホルモンの分泌が促進されます。
お父さんに上の子を任せて、お母さんが下の子の世話をする家庭が多いですが、その逆をやってみてください。お父さんの時間がとれる時には下の子を見てもらい、お母さんは上の子とゆっくり過ごす時間を作って、甘えさせてあげるのです。「あなたはお兄ちゃんだから、お姉ちゃんだから我慢してね」ばかりではなく、「お兄ちゃん、お姉ちゃんだから優先してあげる」ことも必要です。
子育てで行き詰った時は、誰かに助けてもらうようにしましょう。両親、小児科医、幼稚園・保育園・小学校の先生など手をさしのべてくれる人はたくさんいます。役に立つアドバイスをもらえることもあれば、打ち明けたことによって気持ちが落ち着き、自分の中で解決法が見つかることもあります。
お母さんが笑顔でいると、家庭は明るくなり、子どもはそれだけで幸せな気持ちになれます。逆に、お母さんが不機嫌な顔をしていると、子どもは不安になります。「子育てでいっぱいいっぱいなのに笑顔なんてできないわ」と思われるかもしれません。そういう時でも作り笑いをしてみると、「今、楽しいんだ」と脳が勘違いをしてくれて、なんだか楽しい気持ちになってくるんだそうです。朝一日の始まりに、鏡の前で笑顔を作ってみて下さい。それだけで、気分が明るくなり、今日も楽しく頑張れるという気になります。
子育ては確かに大変です。楽しいことばかりではありません。ですが、子どもと向き合える時間は一時に過ぎず、だからこそ子育ての期間を大切に、笑顔を忘れないで過ごしてほしいと思います。
●広島大学医学部医学科卒業
●広島大学医学部附属病院研修医
●厚生連府中総合病院小児科医師
●社会保険広島市民病院小児科医師
●広島市立舟入病院小児科医師
●広島大学医学部附属病院大学院生、医員
●社会保険広島市民病院未熟児新生児センター副部長
●広島市立広島市民病院未熟児新生児センター部長
‐資格・所属学会‐
・医師免許証
・広島大学大学院医学系研究科学位
・日本小児科学会小児科専門医
・新生児蘇生法専門コースインストラクター
・子どものこころの相談医
野村真二 先生(小児科)
お母さんが笑顔になる、育てにくい子どもの上手な育て方
こころ・チャイルド・クリニック
【住所】広島市安佐南区伴南1丁目5-18-8 西風新都ゆめビル 3階
【TEL】 082-849-5519

地域に根付いた専門性の高い小児科医療を提供。心の発達相談にも応じてくれる野村先生
「育てにくい」と感じるのは、間違った子育てをしているから? それとも、こころの発達に問題があるのかしら?
育児を楽しみたいのに、イライラしたり心配してばかりと言う方に、今回は、「こころ・チャイルド・クリニック」の院長で、「子どもの心相談医」の資格をもつ野村真二先生を伺い、上手な子育てのアドバイスを教えてもらいました。
小児科は子どもが病気にかかった時や健診で行くところですが、育児の悩みや心の発達相談にものってくれる、子育てママ・パパの応援団でもあるのですよ。
子育てに正解も不正解もありませんが、今の育児に問題や疑問を感じている方にとって野村先生のお話が少しでも参考になればと思います。
子どもにイライラしてしまうのはなぜ?!
「どうしてできないの?」「できなきゃダメよ!」と、親はつい口を挟んでしまいます。それは、「できて当たり前」という頭で子どもを見ているから、無意識のうちにできない行動ばかりに目がいき、「あれもできない、これもできない」とイライラするのです。また、最近は発達障害の認知度が高まり、お母さん方も知識が豊富です。お友達にできることが自分の子どもにできないと、発達障害ではないかと不安になります。
できない行動ばかりチェックしてしまう一方で、できた行動は気に留めず、流してしまっていませんか? できたことを見つけて、親が子どもに「できたね」と伝えることは、とても大切なことです。子どもは親に認められたことで自信がつき、ほめられると次のステップを目指そうと頑張るものです。
「ほめて育てたいけど、うちの子はできないことばかりで、ほめるところがないんです」と、おっしゃられるお母さんもいますが、そんなことはありません。昨日できなかったこと、1週間前はできなかったこと、1ヶ月前はできなかったことが、お母さんが気づかない間にいつの間にかできるようになっているはずです。視点を変えるだけで、「できたね」が溢れていることに気付きます。
子どものできない行動ばかり探していたら、イライラして疲れるのは当然です。「できない」ではなく「できた」ことに注目して、できたことを親子でたくさん喜び、さらにはその「できた」の中から、その子の素質を見抜いて伸ばしてあげることを心掛ければ、育児はもっと楽しくなると思います。
できない行動に対しては、どうしたら良いですか?
できないことを頭ごなしに叱るのではなく、「こうすればできるようになる」と指示を与え、少しずつステップを作ってあげて、徐々にできるように対処していきます。例えば片付けができないお子さんだったら、まずは「お母さんも手伝うから一緒に片付けよう」と声を掛けてあげてください。その次は、「1人で片付けをやってごらん。できなかったらお母さんも手伝うね」と少しステップをあげてみる。1人で片付けができたら、「ちゃんとできたね。えらいね」とほめてあげてください。
「できたね」とほめてあげることは、とても大切です。そして、ほめるのと同時に喜んであげることも。「できるようになったら、お母さんはこんなに喜んでくれるんだ」と、子どものやる気を刺激します。
目標に向かって、小さなステップを1つずつクリアしていけば、できる行動はどんどん増えていきます。
「ほめる」ことは、「甘やかす」ことにつながりませんか?
ほめて育てるのと甘やかすのとは別です。ほめるというのは、できたことを認めてあげることで、一方、甘やかすのは、できなくても「できないままでいいよ」と許してしまっていることです。できないことを叱らないという点ではいいのですが、できないことをそのままにしてしまっては、子どもは成長しません。また、よくお母さんからの質問で、「できたらご褒美をあげる」というのは、甘やかしていることになりませんか?と聞かれることがありますが、ちょっとしたご褒美ならあってもいいと思います。
目標を設定し、それを子どもに明確に示してあげることは悪いことではありません。できるようになったらお母さんも喜んでくれるし、自分もご褒美がもらえて嬉しいから、「次も頑張ろう!」と意欲向上につながります。ただ、お金がかかるご褒美は良くないので、そこは気を付けて下さいね(笑)
できなかったことに対しては、叱らず、焦らず、放っておかずに、まずはやり方をきちんと教えて、少しずつできるようにサポートしてあげましょう。そして、できたことを認め、しっかりとほめてあげる。ほめて育てることは、しつけや教育のためだけでなく、将来自己評価のしっかりできる大人になることにもつながります。
自己評価ができる人間とは?
頑張っても目標を達成できないことは誰にでもあります。そんな時、自己評価ができる人というのは、目標は達成できなくても頑張った自分を認められる、誇れる、自分が好きだと思えるものです。ですが、子どもの頃から高い目標ばかり目指して、なかなか親にほめてもらえない環境で育つと、小さな達成では満足感が得られず、頑張った自分に対しても厳しい評価をしてしまいます。時には、できなかった自分に対して、ダメな人間だと追いつめてしまうこともあります。
成功体験を実感することで、子どもは「やればできるんだ」と自信がつきます。ほめてあげること、認めてあげることは、自己肯定感を育むための大切な親子のコミュニケーションだといえます。
将来の人格形成にも大きく影響するのですね。
子どもは成長しながら、自分というものを見つけていきますが、その土台になるのが親からの愛され方です。「自分は価値があり、大切な人間なんだ」という自覚は、幼少時期より、親が「あなたは宝物なのよ」と伝えていくことで芽生えていきます。ですが、そこに虐待があったり、愛情が十分に注がれていないと「自分は誰からも必要とされていない」と思う傾向が強くなり、自分自身の存在感を肯定できなくなってしまいます。子どもが将来、自分のダメな部分も含めて自分を好きでいられる人になれるように、親子の心の触れ合いを大切にして欲しいと思います。
つい大声で頭ごなしに叱ってしまう、良くないですよね?
感情的になって、きつい言葉をぶつけてしまう。良くないことだと分かってはいても、ついやってしまいますよね。でも、お母さんがプンプン腹を立てて怒っても、子どもの方は右から左へ受け流すだけです。大声で叱っても心に響きません。特に子どもがかんしゃくを起して、泣いてパニックになっている時は、何を言ってもムダです。そこへお母さんが感情的になって怒りを爆発させてしまっては、しつけどころではありません。怒鳴りつけて、手をあげてしまった後は自己嫌悪に陥るだけです。叱る時は、まずは子どもの気持ちを安定させてあげることが大切です。場所を変えて、気分を沈めて、落ち着いてから話をしましょう。お母さんも一呼吸置いて、クールダウンしてから。冷静になると、自分の思い通りにならなかったから腹を立てていたり、自分の気分で怒っていたりすることに気付くかもしれません。深呼吸をする、お水を飲むなど、自分に合ったリラックス方法で気分を落ち着かせ、子どもが悪いことをした時は、なぜ悪いかを教えましょう。
指示は怒鳴ったりせず、穏やかに繰り返すようにしましょう。子どもの問題行動には必ず理由があります。「〜したい気持ちはわかるけど、…しようね」のように共感的表現をすると指示が入りやすくなります。
叱ることは育児では良くないのですね。
まったく叱らない親がいいのかというと、それは違います。子育ての目標は、責任のある自立した人間になってくれることですから、自分の行動に責任があること、社会にはルールがあること、人の命を大切にすることを伝えていかないといけません。人を傷つけたり迷惑をかけたり、危険な行為に対しては、それが悪いことだと教えるために叱ることはしつけの一環として大切です。「やってはいけないことをすると、お父さんとお母さんはこんなに叱るんだ」と、子どもも気付いてくれます。命に係わるような危ないことをした時は、「こんな恐ろしい親がいるんだ!」と驚くほど、真剣に叱ることも時には必要です。厳しく叱るのは本当に分かってもらいたい時のために、温存しておきましょう。子どもにテレビやビデオを見せるのは良くないですか?
テレビやビデオからの情報は一方通行で入ってきて、その間に子どもが考えて自分の意見を発信することはありません。見終わった後に、お父さんやお母さんと一緒に感想を話し合うようにするといいのですが、お母さんが忙しくて関われないために子ども1人をテレビの前に座らせて、長時間つけっ放しというのはやはり良くないですね。心の発達のためには、語りかけや会話、絵本の読み聞かせがすごく大事です。それと、自然の中で遊ばせて、同年代の子たちとコミュニケーションをとっていくことも。健康のために運動習慣をつけていくことも必要で、遊びの中でできるだけ体を動かすようにすると、食欲が増し、心地よい疲労感から睡眠がもたらされ、骨の成長や成長ホルモンの分泌が促進されます。
上の子の赤ちゃん返りで育児ストレスがピーク、どうすればいい?
赤ちゃんのお世話に手がかかる一方で、上の子が赤ちゃん返りをしたり、異常行動を起こすことはよくあります。「あなたも小さい時そうだったんだから、我慢しなさい」と言っても、子どもは納得できません。育児が2倍しんどくなって、参ってしまうお母さんもいると思います。お父さんに上の子を任せて、お母さんが下の子の世話をする家庭が多いですが、その逆をやってみてください。お父さんの時間がとれる時には下の子を見てもらい、お母さんは上の子とゆっくり過ごす時間を作って、甘えさせてあげるのです。「あなたはお兄ちゃんだから、お姉ちゃんだから我慢してね」ばかりではなく、「お兄ちゃん、お姉ちゃんだから優先してあげる」ことも必要です。
最後に、子育て中のお母さんにアドバイスをお願いします。
発達障害の早期発見のためには、健診をしっかり受けることが大切です。言葉の遅れやコミュニケーション障害などの症状がある場合には、早めにかかりつけ医に相談して下さい。子育てで行き詰った時は、誰かに助けてもらうようにしましょう。両親、小児科医、幼稚園・保育園・小学校の先生など手をさしのべてくれる人はたくさんいます。役に立つアドバイスをもらえることもあれば、打ち明けたことによって気持ちが落ち着き、自分の中で解決法が見つかることもあります。
お母さんが笑顔でいると、家庭は明るくなり、子どもはそれだけで幸せな気持ちになれます。逆に、お母さんが不機嫌な顔をしていると、子どもは不安になります。「子育てでいっぱいいっぱいなのに笑顔なんてできないわ」と思われるかもしれません。そういう時でも作り笑いをしてみると、「今、楽しいんだ」と脳が勘違いをしてくれて、なんだか楽しい気持ちになってくるんだそうです。朝一日の始まりに、鏡の前で笑顔を作ってみて下さい。それだけで、気分が明るくなり、今日も楽しく頑張れるという気になります。
子育ては確かに大変です。楽しいことばかりではありません。ですが、子どもと向き合える時間は一時に過ぎず、だからこそ子育ての期間を大切に、笑顔を忘れないで過ごしてほしいと思います。
医師のプロフィール
野村真二先生
●広島学院高等学校卒業●広島大学医学部医学科卒業
●広島大学医学部附属病院研修医
●厚生連府中総合病院小児科医師
●社会保険広島市民病院小児科医師
●広島市立舟入病院小児科医師
●広島大学医学部附属病院大学院生、医員
●社会保険広島市民病院未熟児新生児センター副部長
●広島市立広島市民病院未熟児新生児センター部長
‐資格・所属学会‐
・医師免許証
・広島大学大学院医学系研究科学位
・日本小児科学会小児科専門医
・新生児蘇生法専門コースインストラクター
・子どものこころの相談医
病名・症状・キーワードからレポートを検索
■□■□ 2025年12月によく読まれた記事をCHECK! □■□■
命にかかわる病気ではありませんが、経過観察と言われたら生理の変化に気を付けて。過多月経や月経痛がひどくなるなどの場合は早めに産婦人科に相談しましょう。
実は10代、20代の女性の死因上位に挙げられる摂食障害。
人の価値や美しさは、体型や体重で決まるものではありません。
適切なカウンセリングで過度な痩せ願望やストレスから自分の体を守りましょう。
幼児や児童に感染することが多く、発症すると喉の痛み、熱、発疹などといった風邪と似た症状が起こります。また、痛みはないのですが、舌の表面に赤いぶつぶつができることがあります。
尋常性疣贅は、「ヒト乳頭腫ウイルス」というウイルスの一種が皮膚に感染してできます。手あれや髭剃り後など、目に見えないくらいの小さな傷からでもウイルスが侵入します。どこの部位にもできる可能性があるのです。
咽喉頭異常感症は心理的要因が大きいといわれています。
喉がイガイガする、圧迫感がある、引っ掛かったり、絡んだような感じがするなど
考えれば考えるほど、喉に違和感を抱き、そのストレスが引き金になって症状を引き起こすことも多いようです。
「不安障害」とはその名の通り、不安な気持ちが強くなる病気です。
ある特定の状況や場所で非常に強い不安に襲われ、身体のいろいろな部分に様々な症状が現われたり、不安を避けようとする「回避行動」をとるようになったり、また安心を得るために無意味な行動を反復してしまうといったことが起こり、人によってはそれが原因で社会生活に支障をきたすこともあります。