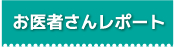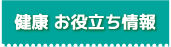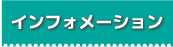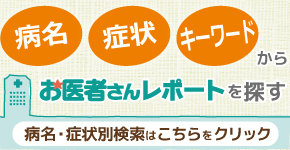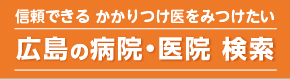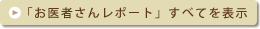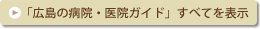広島の頼れるかかりつけ医&病院・医院・クリニックに出会える健康情報サイト
(この記事は2014年11月20日時点の情報です)
いちごこどもクリニック
【住所】広島県広島市安佐南区川内5-14-20
【TEL】 082-870-1115

育児には不安がつきもの。特に、赤ちゃんの様々な症状で悩むお母さんは多いと思います。
今回のレポートは、安佐南区川内に開院したばかりの「いちごこどもクリニック」を訪れ、院長の中村和洋先生に、生後1歳までに多い赤ちゃんの症状と対応についてお話を伺いました。
大学病院では生まれつきの病気や小児がんなど、難治性疾患の診療に携わってこられた中村先生。数多くの乳児健診にも立ち会い、その際、赤ちゃんの臍(へそ)の症状や男の子の陰部の症状、便の色について質問されることが多かったそうです。
そこで、母子手帳や育児書に載っている一般的な症状以外で、赤ちゃんに多い症状について、分かりやすく解説して頂きました。
37℃後半の微熱の多くは、運動や室温、衣服など環境因子によるもので、哺乳や活気、機嫌などが変わりなければ、衣服や室温の調節などで経過をみていてよいかと思います。一方、38℃以上の発熱が持続する場合や、哺乳、元気さ、機嫌など一般状態が不良である場合は、感染症の可能性があります。赤ちゃんはお母さんから胎盤を通じて抗体(抵抗力)をもらっているため、抗体が消える生後半年頃までは、感染症にかかりにくいのですが、感染症にかかった場合は重症化する可能性があり、早めの対応が必要です。
咳、鼻水、鼻づまりも軽度の場合は心配いりません。生後早期は哺乳後などに鼻づまり症状を認めることも多いですが、発熱など感染症状なく、一般状態が良好であれば、経過をみていてよいかと思います。咳や喘鳴(ゼーゼー)が強く、哺乳量や食欲の低下などを認めれば、ウイルス感染症などの可能性があり、病院受診が必要です。
赤ちゃんの便はやわらかく、黄色もしくは緑色です。便の回数も1日数回のことも、数日に1回のこともありますが、機嫌など悪くなければ心配いりません。便が白っぽいときや、便に血液が混じるときは詳しい検査が必要です。
赤ちゃんは様々な原因で黄だん(ビリルビンという物質が体にたまり皮膚や白目などが黄色くなる状態)を合併します。多くは生後1ヶ月頃までに徐々に軽快しますが、母乳栄養の赤ちゃんでは2ヶ月頃まで続くこともあります。体重増加など全身状態がよければ様子を見ていて問題ありません。便が白っぽい場合、1ヶ月以後に黄だんが強くなる場合などは詳しい検査が必要です。
全身の皮膚に出現する赤色や青色の斑点を母斑(ぼはん)といいます。赤ちゃんに多いのは、上まぶた、口と鼻の間などにみられる淡い赤い斑点で、サーモンパッチと呼ばれます。新生児の約1/3にみられますが、治療の必要はなく、数ヶ月で自然に消えます。首の後ろにみられる赤い斑点(ウンナ母斑と呼びます)も特に治療は必要ありません。徐々に薄くなり、半分程度は自然に軽快します。
生後早期に出現するふくらみのある赤色斑点をイチゴ状血管腫と呼びます。乳児期に増大し、6歳頃までには自然に消えますが、はん痕(軽度の皮膚のひきつれ)を残すことがあります。顔面に出現し、目や鼻を塞ぐ場合は、レーザー治療、薬物治療など早期の治療が必要です。最近では顔面以外でも美容的観点から、早期に治療を行うこともあります。腰部に出現する青い斑点を蒙古斑(もうこはん)と呼び、5〜6歳頃までに自然消退します。腰部以外の手背や足首などに出現する蒙古斑は、成人まで残ることがあり、濃い場合は早期レーザー治療の対象となります。
の内部にできもの(臍肉芽)が存在することがあります。症状が持続する場合は病院での処置が必要です。
出べそ(臍ヘルニア)は、腹筋のすき間から腸の一部が脱出した状態で、押さえるとぐしゅっと音がして、お腹の中に戻ります。様子を見るのみで、生後1歳頃までに約90%が自然に治りますが、ガーゼやテープで固定して早く治す方法もあります。
睾丸が陰のう内に入っておらず上にある状態を停留睾丸(ていりゅうこうがん)と呼びます。早産児では30%程度、成熟児でも数%みられ、生後1ヶ月頃までに自然に陰のう内に下降する可能性があります。生後1ヶ月以降も持続する場合は、手術の必要性を含め小児外科での経過観察が必要です。
その他、男児の包茎、女児の一時的な白いおりものなども問題ないことがほとんどです。
まつげが内側に入り込む睫毛内反症(けんもうないはんしょう)もときにみられますが、赤ちゃんの場合はほとんど自然に治ります。
赤ちゃんは分娩時の圧迫により白目の出血(結膜出血)を合併することもありますが、多くは1ヶ月頃までに自然に治ります。
視線が合わないことや眼が動く(眼振)ことが気になることも多いと思います。新生児期は光に反応する程度の視機能であり、追視は2ヶ月以降にしっかりできるようなります。眼が一瞬動くことも、普段の眼の位置が問題なければ心配いらないことが多いです。より目(斜視)が持続する場合や、眼振を繰り返す場合は眼科での精査が必要です。
ます。多くは自然に消失しますので、放置していて問題ありません。
舌や頬の粘膜に、白いミルクのかすのようなものが付着する場合、鵞口瘡(がこうそう)と呼ばれるカンジダ感染症のことがあります。舌のみであれば治療を要しないことも多いですが、頬に認める場合は薬物治療を検討します。
多数の問題ない症状と、少数の対応を急ぐ症状を的確に区別することは、難しいときもあるかと思います。少し気になることは遠慮なく周囲のひとたちや、かかりつけ医などと相談し、不安の少ない、楽しい育児を行っていただければと思います。
「いちごこどもクリニック」は、2014年10月に開院したばかりです。大学病院で勤務していた頃は、生まれつきの病気や小児がんなど、難病に苦しむ子どもたちの力になることに尽力してきましたが、今後は地域に根付いたクリニックとして、子どもたちの健やかな成長を一緒に応援していきたいと思います。
●広島大学医学部附属病院医員(研修医)
●県立重症心身障害者コロニーわかば療育園小児科医師
●東広島医療センター小児科医師
●府中市民病院小児科医師
●広島市民病院小児科医師
●広島市民病院未熟児新生児センター医師
●広島大学大学院医学系研究科博士課程入学
●同上終了(医学博士取得)
●広島大学大学院(大学病院)小児科助手
●広島大学大学院(大学病院)小児科講師
●広島大学大学院(大学病院)小児科准教授
‐資格・所属学会‐
・医学博士
・日本小児科学会認定 小児科専門医
・日本血液学会認定 血液専門医・指導医
・日本人類遺伝学会認定 臨床遺伝専門医・指導医
・新生児蘇生法「専門コース」インストラクター
中村和洋 先生(小児科)
少し気になる赤ちゃんの症状と対応について
いちごこどもクリニック
【住所】広島県広島市安佐南区川内5-14-20
【TEL】 082-870-1115

子どもと親御さんの気持ちに寄り添った、優しくあたたかい医療を提供する中村院長
育児には不安がつきもの。特に、赤ちゃんの様々な症状で悩むお母さんは多いと思います。
今回のレポートは、安佐南区川内に開院したばかりの「いちごこどもクリニック」を訪れ、院長の中村和洋先生に、生後1歳までに多い赤ちゃんの症状と対応についてお話を伺いました。
大学病院では生まれつきの病気や小児がんなど、難治性疾患の診療に携わってこられた中村先生。数多くの乳児健診にも立ち会い、その際、赤ちゃんの臍(へそ)の症状や男の子の陰部の症状、便の色について質問されることが多かったそうです。
そこで、母子手帳や育児書に載っている一般的な症状以外で、赤ちゃんに多い症状について、分かりやすく解説して頂きました。
生後1歳までに多い症状について教えてください。
私は大学病院に勤務する15年間に、複数の産婦人科クリニックで乳児健診を担当してきました。その間、赤ちゃんの少し気になる症状と対応について、たくさんのご質問をいただきましたので、主なものについて解説いたします。赤ちゃんの発熱、咳、鼻水について
赤ちゃんの平熱は36.5℃〜37.5℃であり、一般に38℃を超えると発熱と判断します。37℃後半の微熱の多くは、運動や室温、衣服など環境因子によるもので、哺乳や活気、機嫌などが変わりなければ、衣服や室温の調節などで経過をみていてよいかと思います。一方、38℃以上の発熱が持続する場合や、哺乳、元気さ、機嫌など一般状態が不良である場合は、感染症の可能性があります。赤ちゃんはお母さんから胎盤を通じて抗体(抵抗力)をもらっているため、抗体が消える生後半年頃までは、感染症にかかりにくいのですが、感染症にかかった場合は重症化する可能性があり、早めの対応が必要です。
咳、鼻水、鼻づまりも軽度の場合は心配いりません。生後早期は哺乳後などに鼻づまり症状を認めることも多いですが、発熱など感染症状なく、一般状態が良好であれば、経過をみていてよいかと思います。咳や喘鳴(ゼーゼー)が強く、哺乳量や食欲の低下などを認めれば、ウイルス感染症などの可能性があり、病院受診が必要です。
消化器症状(嘔吐、便の色、黄だんなど)
新生児期や乳児期早期の赤ちゃんの嘔吐は日常的によくみられます。元気があり、体重増加が良好であれば心配いりません。生後1ヶ月前後に激しい噴水状の嘔吐を繰り返す場合、嘔吐物が胆汁の混じった緑色の場合などは、消化管の通過障害の可能性があり詳しい検査が必要です。赤ちゃんの便はやわらかく、黄色もしくは緑色です。便の回数も1日数回のことも、数日に1回のこともありますが、機嫌など悪くなければ心配いりません。便が白っぽいときや、便に血液が混じるときは詳しい検査が必要です。
赤ちゃんは様々な原因で黄だん(ビリルビンという物質が体にたまり皮膚や白目などが黄色くなる状態)を合併します。多くは生後1ヶ月頃までに徐々に軽快しますが、母乳栄養の赤ちゃんでは2ヶ月頃まで続くこともあります。体重増加など全身状態がよければ様子を見ていて問題ありません。便が白っぽい場合、1ヶ月以後に黄だんが強くなる場合などは詳しい検査が必要です。
皮膚の症状(湿疹、母斑など)
新生児や乳児期早期の赤ちゃんは、顔の湿疹がよくみられます。石鹸を泡立てて洗うことで3ヶ月頃までに軽快していきます。脂肪で頑固なかさぶた状になった湿疹(脂漏性湿疹)では、オリーブ油などでふやかして洗うことも有効です。全身の皮膚に出現する赤色や青色の斑点を母斑(ぼはん)といいます。赤ちゃんに多いのは、上まぶた、口と鼻の間などにみられる淡い赤い斑点で、サーモンパッチと呼ばれます。新生児の約1/3にみられますが、治療の必要はなく、数ヶ月で自然に消えます。首の後ろにみられる赤い斑点(ウンナ母斑と呼びます)も特に治療は必要ありません。徐々に薄くなり、半分程度は自然に軽快します。
生後早期に出現するふくらみのある赤色斑点をイチゴ状血管腫と呼びます。乳児期に増大し、6歳頃までには自然に消えますが、はん痕(軽度の皮膚のひきつれ)を残すことがあります。顔面に出現し、目や鼻を塞ぐ場合は、レーザー治療、薬物治療など早期の治療が必要です。最近では顔面以外でも美容的観点から、早期に治療を行うこともあります。腰部に出現する青い斑点を蒙古斑(もうこはん)と呼び、5〜6歳頃までに自然消退します。腰部以外の手背や足首などに出現する蒙古斑は、成人まで残ることがあり、濃い場合は早期レーザー治療の対象となります。
臍(へそ)の症状
臍帯(へその緒)脱落後に、へそが乾燥せずに、じくじくした状態が続く場合は、へその内部にできもの(臍肉芽)が存在することがあります。症状が持続する場合は病院での処置が必要です。
出べそ(臍ヘルニア)は、腹筋のすき間から腸の一部が脱出した状態で、押さえるとぐしゅっと音がして、お腹の中に戻ります。様子を見るのみで、生後1歳頃までに約90%が自然に治りますが、ガーゼやテープで固定して早く治す方法もあります。
陰部の症状
男の子の陰のうに水がたまり腫れることがあり、陰のう水腫と呼びます。生後1歳頃までに約90%が自然に治るため、乳児健診時などに経過観察してもらえればよいかと思います。経過中に痛みや機嫌不良などを認める場合は、感染症やヘルニアなどを合併している可能性があり、病院受診が必要です。睾丸が陰のう内に入っておらず上にある状態を停留睾丸(ていりゅうこうがん)と呼びます。早産児では30%程度、成熟児でも数%みられ、生後1ヶ月頃までに自然に陰のう内に下降する可能性があります。生後1ヶ月以降も持続する場合は、手術の必要性を含め小児外科での経過観察が必要です。
その他、男児の包茎、女児の一時的な白いおりものなども問題ないことがほとんどです。
眼の症状(眼脂、結膜出血、眼の動き)
赤ちゃんの眼脂(目やに)はよくみられますが、時々認める白い眼脂は心配ありません。黄色の量の多い眼脂では、細菌感染症の可能性があり抗生剤点眼などの治療が必要です。涙が鼻につながる鼻涙管の通過障害が、新生児の5〜10%にみられ、主に片眼からの涙、眼脂が持続します。多くは生後数ヶ月で自然に治りますが、生後2ヶ月を過ぎても症状が持続する場合は、眼科での治療が検討されます。まつげが内側に入り込む睫毛内反症(けんもうないはんしょう)もときにみられますが、赤ちゃんの場合はほとんど自然に治ります。
赤ちゃんは分娩時の圧迫により白目の出血(結膜出血)を合併することもありますが、多くは1ヶ月頃までに自然に治ります。
視線が合わないことや眼が動く(眼振)ことが気になることも多いと思います。新生児期は光に反応する程度の視機能であり、追視は2ヶ月以降にしっかりできるようなります。眼が一瞬動くことも、普段の眼の位置が問題なければ心配いらないことが多いです。より目(斜視)が持続する場合や、眼振を繰り返す場合は眼科での精査が必要です。
口の症状(歯肉の異常、カンジダ感染)
赤ちゃんの歯肉に1〜3mmの白い真珠様のものを認めることがあり、上皮真珠と呼びます。多くは自然に消失しますので、放置していて問題ありません。
舌や頬の粘膜に、白いミルクのかすのようなものが付着する場合、鵞口瘡(がこうそう)と呼ばれるカンジダ感染症のことがあります。舌のみであれば治療を要しないことも多いですが、頬に認める場合は薬物治療を検討します。
育児中のお母さんにアドバイスをお願いします。
赤ちゃんの約5%は何らかの治療を必要とする症状を、約50%は治療を必要としない症状を合併して生まれてくることが知られています。様子を見ていて問題ないことも多いため、乳児健診や、かかりつけ医受診の機会に、気になることをしっかり相談してみて下さい。どのような症状においても、機嫌が悪い、元気がない、哺乳量や食欲の低下などを合併する場合は、対応を急ぐ状態の可能性があり、かかりつけ医などを受診ください。多数の問題ない症状と、少数の対応を急ぐ症状を的確に区別することは、難しいときもあるかと思います。少し気になることは遠慮なく周囲のひとたちや、かかりつけ医などと相談し、不安の少ない、楽しい育児を行っていただければと思います。
いちごをモチーフにした外観が印象的ですね
子どもたちが病院を怖がらないようにと考えて、楽しい気分になれるデザインにしました。病院は治療のためだけに行くのではなく、健康診断、健康相談、予防接種など健康に成長するために行く場所でもあるので、子どももお母さんも緊張せずに通える雰囲気にしたかったのです。「いちごこどもクリニック」は、2014年10月に開院したばかりです。大学病院で勤務していた頃は、生まれつきの病気や小児がんなど、難病に苦しむ子どもたちの力になることに尽力してきましたが、今後は地域に根付いたクリニックとして、子どもたちの健やかな成長を一緒に応援していきたいと思います。
医師のプロフィール
中村和洋 先生
●広島大学医学部卒業●広島大学医学部附属病院医員(研修医)
●県立重症心身障害者コロニーわかば療育園小児科医師
●東広島医療センター小児科医師
●府中市民病院小児科医師
●広島市民病院小児科医師
●広島市民病院未熟児新生児センター医師
●広島大学大学院医学系研究科博士課程入学
●同上終了(医学博士取得)
●広島大学大学院(大学病院)小児科助手
●広島大学大学院(大学病院)小児科講師
●広島大学大学院(大学病院)小児科准教授
‐資格・所属学会‐
・医学博士
・日本小児科学会認定 小児科専門医
・日本血液学会認定 血液専門医・指導医
・日本人類遺伝学会認定 臨床遺伝専門医・指導医
・新生児蘇生法「専門コース」インストラクター
病名・症状・キーワードからレポートを検索
■□■□ 2026年1月によく読まれた記事をCHECK! □■□■
命にかかわる病気ではありませんが、経過観察と言われたら生理の変化に気を付けて。過多月経や月経痛がひどくなるなどの場合は早めに産婦人科に相談しましょう。
実は10代、20代の女性の死因上位に挙げられる摂食障害。
人の価値や美しさは、体型や体重で決まるものではありません。
適切なカウンセリングで過度な痩せ願望やストレスから自分の体を守りましょう。
幼児や児童に感染することが多く、発症すると喉の痛み、熱、発疹などといった風邪と似た症状が起こります。また、痛みはないのですが、舌の表面に赤いぶつぶつができることがあります。
尋常性疣贅は、「ヒト乳頭腫ウイルス」というウイルスの一種が皮膚に感染してできます。手あれや髭剃り後など、目に見えないくらいの小さな傷からでもウイルスが侵入します。どこの部位にもできる可能性があるのです。
咽喉頭異常感症は心理的要因が大きいといわれています。
喉がイガイガする、圧迫感がある、引っ掛かったり、絡んだような感じがするなど
考えれば考えるほど、喉に違和感を抱き、そのストレスが引き金になって症状を引き起こすことも多いようです。
「不安障害」とはその名の通り、不安な気持ちが強くなる病気です。
ある特定の状況や場所で非常に強い不安に襲われ、身体のいろいろな部分に様々な症状が現われたり、不安を避けようとする「回避行動」をとるようになったり、また安心を得るために無意味な行動を反復してしまうといったことが起こり、人によってはそれが原因で社会生活に支障をきたすこともあります。