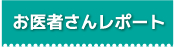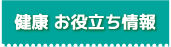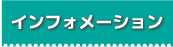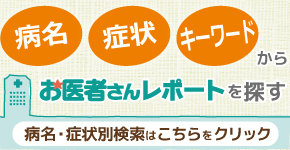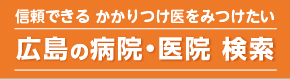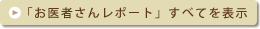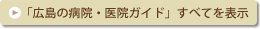広島の頼れるかかりつけ医&病院・医院・クリニックに出会える健康情報サイト
(この記事は2016年2月8日時点の情報です)
土井ファミリー歯科医院
【住所】広島県広島市安佐南区上安3-1-10 古田ビル2F
【TEL】 082-832-7555
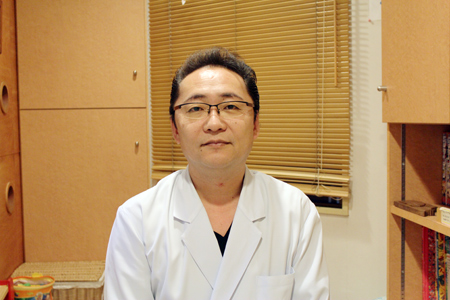
10歳頃になると男女共に罹患率が50%を超えるという「歯肉炎」。
そんな歯肉炎の子どもたちによく見られる「口呼吸」や「お口、ポカン」の弊害はそれだけではありません。
今回は、全身との関わり合いや口腔機能を含めた包括的な診療を行っている「土井ファミリー歯科医院」の土井伸浩院長にお話をうかがいました。
土井先生は日本歯周病学会歯周病 専門医・指導医と日本口腔インプラント学会 インプラント専門医のダブルライセンスを持ち、歯牙移植も数多く手がけるスペシャリストである一方、講演や研究などでお忙しい中、農業にも勤しみ、地域の子どもたちへの啓蒙・普及活動などにも取り組んでおられ、バイタリティと探究心に満ちた、明るく楽しい先生です。
呼吸には鼻で息を吸って吐く「鼻呼吸」と口で息を吸って吐く「口呼吸」の2つがありますが、口呼吸や口を開けている時間が長いと、口の中が乾燥しますよね。唾液の中に含まれる免疫成分が少なくなる事で細菌が活発になり、抵抗力も落ちるので、歯茎がすごく腫れやすくなるんです。歯茎が腫れると口臭も発生しますし、プラーク中の細菌や舌表面の細菌のバランスが崩れて、虫歯・歯周病・カンジダ症・口内炎などになりやすくなります。
また、免疫細胞が集合している舌扁桃や口の奥にあるリンパ組織集団(咽頭扁桃、耳管扁桃、口蓋扁桃、咽頭小扁桃)の全てが乾燥するので、細菌やウィルスが繁殖しやすく、扁桃腺が腫れやすくなったり、インフルエンザや風邪に感染しやすくなります。
あと、口呼吸を繰り返す事で慢性的に細菌やウィルスに曝露されるので、血液中の免疫細胞が減少して、体全体の免疫機能が狂ってしまいます。
はっきりと科学的に証明されていないものもありますけど、口呼吸は、喘息やアトピー性皮膚炎などのアレルギー性疾患や関節リウマチなどの免疫性疾患にかかりやすくなるといわれています。
その他には味覚異常や歯列不正にも関係しますし、顔の筋肉も緩みます。
口は「消化器」、鼻は「呼吸器」の一部なので、蓄膿や鼻炎があれば耳鼻科で治療していただいて、口呼吸から鼻呼吸に治していただきたいなと思いますね。
また、口呼吸だと加湿が不十分で、肺の細胞の粘膜になじみにくいため酸素がスムーズに吸収されないのですが、鼻呼吸だと乾燥した空気が直接喉にいく事なく上顎洞で加湿されて肺に入ってきます。
あとは口呼吸よりも鼻呼吸の方が体内に酸素を多く取り込める事や、「脳の学校」の加藤俊徳先生のCOEという手法によって鼻呼吸の方が記憶力・運動能力が向上するという事も分かってきています。
鼻呼吸になったら鼻が発達して鼻の中の空間が広がりますから、鼻が高くなります。鼻が高くなったら中顔面が引っ張られて発達するので目がパッチリするんですよ。綺麗になったりカッコよくなったりという流れから攻めていけば親御さんが子どもたちの鼻呼吸に興味を持ってくれるのかなと思わなくもないですけど(笑)、系統だってこれをやったらこうなるよっていうところまでいっていないので、その辺が今の課題ですね。
でも本当に鼻が発達してくると顔貌が変わってきますよ。口がポカーンとした子どもたちと口を閉めてキリッとしてる子どもたちはもう顔つきが違うんです。
口呼吸の治し方には以下の方法がありますので、ぜひやってみてくださいね。
うちは歯周病やインプラントがメインですが、実は子どもさんの多い医院で、患者さんとして来られた幼稚園・保育園の先生に依頼されるんですよ。学校医の先生たちに断った上で指導に行ったりしていますね。「虫歯予防戦隊ミガクンジャーvs虫歯菌軍団」という劇をやるのですが、今でこそヒーロー5人vsバイキン5人になっていますけど、10年前は本当に少人数でやっていました。
鬼の仮面をかぶったバイキンマンが子どもたちの中に入り込んでいって、子どもたちも蜘蛛の子を散らすようにバーッと逃げるという、幼稚園や保育園の年間行事の中で一番怖いくらいの劇をやっているそうなのですが(笑)、子どもたちも虫歯の怖さをすごく分かってくれるようで、劇を見た後はすごく歯を磨くそうです。
ちょうどその頃、子どもたちのなりたい職業に「歯医者さん」がなくなったんですよ。
うちらの業界が面白くなくて、リアルな話ですが儲からないというのも年に1〜2回くらい週刊誌に出たりして。
そうすると若い人はなりたがりませんよね。でも、なってほしいじゃないですか。そういうのがあって、今、4年目ですかね、年に1回、病院を閉めてキッザニアをやっています。
私はキッザニアに行った事はないですが、聞くと本物のキッザニアよりリアルらしいですよ。歯医者さんや衛生士さんの体験をしたり、指の模型を作ったり、光で固まるプラスチックを使って虫歯を治す体験をしたりしていますね。
やっぱり子どもがスタートなんです。子どもが歯医者さんに来やすくなる流れを作ってしまうと、その子どもたちは一生虫歯知らず、歯周病知らずなんですよね。
そうなると歯医者さんは要らないという話で、自分らの首を絞めているんじゃないかっていう話でもありますけど(笑)、儲けがどうこうでやっている仕事でもないので、子どもに力を入れています。
あとは若い女性、特に妊婦さんの歯周病は早産になりやすいので、その辺のアプローチもきちっとしますね。そんな風にライフステージに合った形でやっています。
患者さんを何年もみていると、それくらいの年代で口の中が急に変わるんですよ。出血しやすくなったり、噛んだら痛いんです、というような時期が何年かあります。
男性もいますが、そういう原因がはっきりしない症状は女性の方が多くて、6〜7割占めますね。
原因を消しても残る症状なので、もうやりようがないのですが、気分が少しでも和らぐように、例えば3ヶ月に1回来てもらうところを1ヶ月に1回来てもらうとか、毎回親身になって症状をみて何かしらの処置をしてあげるとか、安心感を持ってもらえるような形で対応させてもらっています。
よっぽど「あれ?」って思う人は大学病院や総合病院を紹介しますが、うちでできる事であれば血圧計や心電図をつけての治療も時々あります。
時々入院患者さんも来られますね。ドクターによっては歯周病の治療あるいは口腔ケアをきちんとしておかないと体の治りや傷の治りが悪いっていうのを知っていらっしゃるので、そういう先生たちや市民病院さんなどが歯周病や虫歯の対応に時々送ってこられます。
でもやっぱり高齢者は怖いですね。救急車を呼んだ事も1回2回ありますし。
その方は全身疾患のない80歳の方で、かかりつけの内科の先生に電話を入れて、本当に疾患がない事や薬も飲んでいない事を確認してからオペをしたのですが、オペが終わって「ああよかった、すっきりしました」「じゃあこれで終わりましたね、お疲れ様でした」って椅子を立とうとした時、立てなくなってしまったんです。
手術中はドキドキして血管が収縮しているわけですよ。で、安心するとそれがすーっと緩むわけですよ。たぶん、医者に分かってなかった血栓か何かが詰まったんでしょうね、それで動きが取れなくなってしまって。
脈をとって、うちでは救急薬品でどうこうできるレベルじゃないなと判断して救急車を呼んだんですけどね。しびれが出て5分くらいの結構早い段階で呼んで、救急車も10分以内で来てくれたんですよね。
でも下の駐車場で30分。その方に病気があって、かかりつけの病院に定期的に行ってらっしゃったらいいですけど、まったく病気のない人なので、救急を受け付けてくれる病院がなかなか見つからなかったんですよね。結局脳梗塞みたいな感じでちょっと麻痺が出た、というような事もあって、あれにはちょっと私もびっくりしました。
かといって、そこに病気があるのに治療しないわけにはいかないので、全身疾患との兼ね合いをみながらやっていますね。

たとえば「入れ歯がなくなって噛めないから何とかしてくれ」とか「虫歯が痛い」とかいうのをなんとかしよう、プラス、誤嚥性肺炎の予防ですね。やっぱり口腔ケアが綺麗にできていないとお年寄りさんは誤嚥性肺炎になりやすくなったりするので。
特に避難所での睡眠だと、ちゃんとした睡眠がとれない事で抵抗力が落ちているので余計危ないという事もあって、6割はブラッシングしていました。救急治療は3割4割ですかね。
そんな風に、一つの病院で、あるいは一つの病院を通してすべての処置ができるのが理想です。子どもから老人まで全部の処置ができれば嬉しいですね。医院名の「ファミリー」も、別にうちが家族でやっているわけじゃなく、「おじいさんから赤ちゃんまで」という意味合いで付けた言葉です。
CTのある病院も1割くらいはありますから、CTを撮る事で分からなかった原因が分かる事もあります。
昔は一度行き出したらここに筋を通さなきゃいけないとか義理立てしてここの治療が終わるまでは、とかありましたけど、もうそんな事関係なく、おかしいなと思ったら遠慮なくセカンドオピニオンを活用してもらったらいいと思います。
渡り歩くのはどうかと思いますが、ちょっと相談という意味合いでセカンドオピニオンされるのはおすすめです。
●広島大学歯学部 歯科保存学第二教室(現 歯周病態学分野)入局
●(医)オリーブ・ファミリー・デンタルクリニック勤務
●広島大学歯学部 歯科保存学第二教室(現 歯周病態学分野)同門会 会長
●土井ファミリー歯科医院 院長
●広島大学病院 非常勤講師
●D.S.S会長
‐資格・所属学会‐
・日本歯周病学会 専門医・指導医
・日本口腔インプラント学会 専門医
・日本小児歯科学会
・広島県介護支援専門員
・厚生労働省「協力型 臨床研修施設」指定
土井伸浩 先生(歯科)
気をつけて!「お口、ポカン」と「口呼吸」
土井ファミリー歯科医院
【住所】広島県広島市安佐南区上安3-1-10 古田ビル2F
【TEL】 082-832-7555
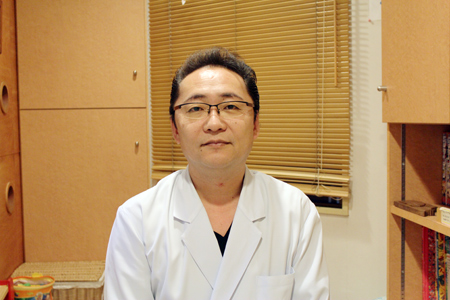
明るく親しみやすいキャラクターと的確なアドバイスで、子どもから大人までみんなに愛される土井院長
10歳頃になると男女共に罹患率が50%を超えるという「歯肉炎」。
そんな歯肉炎の子どもたちによく見られる「口呼吸」や「お口、ポカン」の弊害はそれだけではありません。
今回は、全身との関わり合いや口腔機能を含めた包括的な診療を行っている「土井ファミリー歯科医院」の土井伸浩院長にお話をうかがいました。
土井先生は日本歯周病学会歯周病 専門医・指導医と日本口腔インプラント学会 インプラント専門医のダブルライセンスを持ち、歯牙移植も数多く手がけるスペシャリストである一方、講演や研究などでお忙しい中、農業にも勤しみ、地域の子どもたちへの啓蒙・普及活動などにも取り組んでおられ、バイタリティと探究心に満ちた、明るく楽しい先生です。
「口呼吸」「お口、ポカン」とはどういうものですか?
診断基準というものはないですが、「口を開けて寝ている」「口で息をしている」「口を開けてテレビを見ている」といった状態ですね。呼吸には鼻で息を吸って吐く「鼻呼吸」と口で息を吸って吐く「口呼吸」の2つがありますが、口呼吸や口を開けている時間が長いと、口の中が乾燥しますよね。唾液の中に含まれる免疫成分が少なくなる事で細菌が活発になり、抵抗力も落ちるので、歯茎がすごく腫れやすくなるんです。歯茎が腫れると口臭も発生しますし、プラーク中の細菌や舌表面の細菌のバランスが崩れて、虫歯・歯周病・カンジダ症・口内炎などになりやすくなります。
また、免疫細胞が集合している舌扁桃や口の奥にあるリンパ組織集団(咽頭扁桃、耳管扁桃、口蓋扁桃、咽頭小扁桃)の全てが乾燥するので、細菌やウィルスが繁殖しやすく、扁桃腺が腫れやすくなったり、インフルエンザや風邪に感染しやすくなります。
あと、口呼吸を繰り返す事で慢性的に細菌やウィルスに曝露されるので、血液中の免疫細胞が減少して、体全体の免疫機能が狂ってしまいます。
はっきりと科学的に証明されていないものもありますけど、口呼吸は、喘息やアトピー性皮膚炎などのアレルギー性疾患や関節リウマチなどの免疫性疾患にかかりやすくなるといわれています。
その他には味覚異常や歯列不正にも関係しますし、顔の筋肉も緩みます。
口は「消化器」、鼻は「呼吸器」の一部なので、蓄膿や鼻炎があれば耳鼻科で治療していただいて、口呼吸から鼻呼吸に治していただきたいなと思いますね。
鼻呼吸によって、いろんな事が改善されるのですね。
鼻には空気中の埃を取り除いて浄化する機能が備わっています。空気中に含まれる病原菌の50〜80%は鼻の粘膜に吸着されて処理されるので、綺麗な空気を肺に送り込む事ができます。また、口呼吸だと加湿が不十分で、肺の細胞の粘膜になじみにくいため酸素がスムーズに吸収されないのですが、鼻呼吸だと乾燥した空気が直接喉にいく事なく上顎洞で加湿されて肺に入ってきます。
あとは口呼吸よりも鼻呼吸の方が体内に酸素を多く取り込める事や、「脳の学校」の加藤俊徳先生のCOEという手法によって鼻呼吸の方が記憶力・運動能力が向上するという事も分かってきています。
鼻呼吸になったら鼻が発達して鼻の中の空間が広がりますから、鼻が高くなります。鼻が高くなったら中顔面が引っ張られて発達するので目がパッチリするんですよ。綺麗になったりカッコよくなったりという流れから攻めていけば親御さんが子どもたちの鼻呼吸に興味を持ってくれるのかなと思わなくもないですけど(笑)、系統だってこれをやったらこうなるよっていうところまでいっていないので、その辺が今の課題ですね。
でも本当に鼻が発達してくると顔貌が変わってきますよ。口がポカーンとした子どもたちと口を閉めてキリッとしてる子どもたちはもう顔つきが違うんです。
口呼吸の治し方には以下の方法がありますので、ぜひやってみてくださいね。
●鼻炎や蓄膿症などあれば、先に耳鼻科で治療を受ける
●鼻の通りをよくして普段から口を閉じることを意識する
●就寝時にサージカルテープで口をふさぐ
●鼻腔を広げる器具を使う
●おしゃぶりを使ってみる
●片噛みをやめて両方の歯で咀嚼する
●ガムやグミなど(キシリトール入り)を利用して咀嚼筋を鍛える
●口輪筋などを鍛える
●あいうべ体操(みらいクリニック今井一彰先生考案)
●鼻の通りをよくして普段から口を閉じることを意識する
●就寝時にサージカルテープで口をふさぐ
●鼻腔を広げる器具を使う
●おしゃぶりを使ってみる
●片噛みをやめて両方の歯で咀嚼する
●ガムやグミなど(キシリトール入り)を利用して咀嚼筋を鍛える
●口輪筋などを鍛える
●あいうべ体操(みらいクリニック今井一彰先生考案)
ありがとうございます。先生は他にも子どもたち向けの取り組みをされていますね。
医院外での虫歯予防&ブラッシング指導はもう10年くらいちょこちょこやっていますね。うちは歯周病やインプラントがメインですが、実は子どもさんの多い医院で、患者さんとして来られた幼稚園・保育園の先生に依頼されるんですよ。学校医の先生たちに断った上で指導に行ったりしていますね。「虫歯予防戦隊ミガクンジャーvs虫歯菌軍団」という劇をやるのですが、今でこそヒーロー5人vsバイキン5人になっていますけど、10年前は本当に少人数でやっていました。
戦隊モノを取り入れた劇ですが、医院のスタッフさんが演じられるのですか?
はい。顔が出ている練習の時は恥ずかしがりますが、衣装を着てしまえば顔も見えないので、みんな嬉しそうにやっていますよ。鬼の仮面をかぶったバイキンマンが子どもたちの中に入り込んでいって、子どもたちも蜘蛛の子を散らすようにバーッと逃げるという、幼稚園や保育園の年間行事の中で一番怖いくらいの劇をやっているそうなのですが(笑)、子どもたちも虫歯の怖さをすごく分かってくれるようで、劇を見た後はすごく歯を磨くそうです。
子どもたちが医院で本格的に職場体験できるイベントもされているとか。
最初はうちの子が小学校の修学旅行で神戸のキッザニアへ行く事になって、「キッザニアってなんなん?」というような話から、「ほんなんだったらうちでやろう!」という事になったのがきっかけでした。ちょうどその頃、子どもたちのなりたい職業に「歯医者さん」がなくなったんですよ。
うちらの業界が面白くなくて、リアルな話ですが儲からないというのも年に1〜2回くらい週刊誌に出たりして。
そうすると若い人はなりたがりませんよね。でも、なってほしいじゃないですか。そういうのがあって、今、4年目ですかね、年に1回、病院を閉めてキッザニアをやっています。
私はキッザニアに行った事はないですが、聞くと本物のキッザニアよりリアルらしいですよ。歯医者さんや衛生士さんの体験をしたり、指の模型を作ったり、光で固まるプラスチックを使って虫歯を治す体験をしたりしていますね。
やっぱり子どもがスタートなんです。子どもが歯医者さんに来やすくなる流れを作ってしまうと、その子どもたちは一生虫歯知らず、歯周病知らずなんですよね。
そうなると歯医者さんは要らないという話で、自分らの首を絞めているんじゃないかっていう話でもありますけど(笑)、儲けがどうこうでやっている仕事でもないので、子どもに力を入れています。
あとは若い女性、特に妊婦さんの歯周病は早産になりやすいので、その辺のアプローチもきちっとしますね。そんな風にライフステージに合った形でやっています。
更年期などはどうですか?
更年期さんは不定愁訴が多くなりますね。何も悪いところはないのに、いろんなところが痛い、っていう。一つ一つ原因を消していっても痛みや症状が残る、というような事はお口の症状でも結構あります。患者さんを何年もみていると、それくらいの年代で口の中が急に変わるんですよ。出血しやすくなったり、噛んだら痛いんです、というような時期が何年かあります。
男性もいますが、そういう原因がはっきりしない症状は女性の方が多くて、6〜7割占めますね。
原因を消しても残る症状なので、もうやりようがないのですが、気分が少しでも和らぐように、例えば3ヶ月に1回来てもらうところを1ヶ月に1回来てもらうとか、毎回親身になって症状をみて何かしらの処置をしてあげるとか、安心感を持ってもらえるような形で対応させてもらっています。
高齢の患者さんはいかがですか?
高齢の人は全身疾患との兼ね合いですね。薬の飲み方によっては歯茎が腫れる事もあるし、あるいは血が止まらない事もあるので、そういう副作用に気を付けての治療ですね。よっぽど「あれ?」って思う人は大学病院や総合病院を紹介しますが、うちでできる事であれば血圧計や心電図をつけての治療も時々あります。
時々入院患者さんも来られますね。ドクターによっては歯周病の治療あるいは口腔ケアをきちんとしておかないと体の治りや傷の治りが悪いっていうのを知っていらっしゃるので、そういう先生たちや市民病院さんなどが歯周病や虫歯の対応に時々送ってこられます。
でもやっぱり高齢者は怖いですね。救急車を呼んだ事も1回2回ありますし。
その方は全身疾患のない80歳の方で、かかりつけの内科の先生に電話を入れて、本当に疾患がない事や薬も飲んでいない事を確認してからオペをしたのですが、オペが終わって「ああよかった、すっきりしました」「じゃあこれで終わりましたね、お疲れ様でした」って椅子を立とうとした時、立てなくなってしまったんです。
手術中はドキドキして血管が収縮しているわけですよ。で、安心するとそれがすーっと緩むわけですよ。たぶん、医者に分かってなかった血栓か何かが詰まったんでしょうね、それで動きが取れなくなってしまって。
脈をとって、うちでは救急薬品でどうこうできるレベルじゃないなと判断して救急車を呼んだんですけどね。しびれが出て5分くらいの結構早い段階で呼んで、救急車も10分以内で来てくれたんですよね。
でも下の駐車場で30分。その方に病気があって、かかりつけの病院に定期的に行ってらっしゃったらいいですけど、まったく病気のない人なので、救急を受け付けてくれる病院がなかなか見つからなかったんですよね。結局脳梗塞みたいな感じでちょっと麻痺が出た、というような事もあって、あれにはちょっと私もびっくりしました。
かといって、そこに病気があるのに治療しないわけにはいかないので、全身疾患との兼ね合いをみながらやっていますね。

1階がセブンイレブンのビル2F、木のぬくもりがあたたかい待合室。
受付からメンテナンス・治療まで、気持ちの良い対応は患者さんの評価が高い。
受付からメンテナンス・治療まで、気持ちの良い対応は患者さんの評価が高い。
先生は東日本大震災の時、災害派遣で福島県に行かれたそうですが、そこではどんな事をされたのですか?
たとえば「入れ歯がなくなって噛めないから何とかしてくれ」とか「虫歯が痛い」とかいうのをなんとかしよう、プラス、誤嚥性肺炎の予防ですね。やっぱり口腔ケアが綺麗にできていないとお年寄りさんは誤嚥性肺炎になりやすくなったりするので。
特に避難所での睡眠だと、ちゃんとした睡眠がとれない事で抵抗力が落ちているので余計危ないという事もあって、6割はブラッシングしていました。救急治療は3割4割ですかね。
避難所は高齢の方が多かったですか?
震災が起きて1ヶ月以内の結構早い時期に行ったのですが、やっぱりみんな働くんでしょうね、あるいは家の片付けに行かれていたのかもしれないですね、20代〜50代は何らかの形で仕事に出ているので、日中はいないんですね。そして子どもたちは避難所から学校へ行っているわけです。残っているのはお年寄りと小さい子どもたちなので、お年寄りを多く対象にしていましたが、なんだかんだいって予防の話ですね。予防も治療もしっかりされる先生の目指す歯医者さんの形とは?
強いて言葉を挙げるなら「包括診療」ですかね。包括的に全身疾患も含めて口の中全体をみますよ、という意味合いですが、その中には歯周病治療もインプラントも移植もブリッジも入れ歯も矯正もトータル的にみていきますよ、あるいはそういう手段を持ってますよ、という事ですね。矯正は私も勉強していますが、やっぱり餅は餅屋の方が上手いので、府中町から矯正の開業医さんが来てくれています。そんな風に、一つの病院で、あるいは一つの病院を通してすべての処置ができるのが理想です。子どもから老人まで全部の処置ができれば嬉しいですね。医院名の「ファミリー」も、別にうちが家族でやっているわけじゃなく、「おじいさんから赤ちゃんまで」という意味合いで付けた言葉です。
最後に読者のみなさまへメッセージをお願いします。
この治療でいいのか、この病院でいいのか、悩んでいる方は意外に多いですが、セカンドオピニオンは当たり前のようにされていいと思います。患者が病院を選ぶ時代ですからね。CTのある病院も1割くらいはありますから、CTを撮る事で分からなかった原因が分かる事もあります。
昔は一度行き出したらここに筋を通さなきゃいけないとか義理立てしてここの治療が終わるまでは、とかありましたけど、もうそんな事関係なく、おかしいなと思ったら遠慮なくセカンドオピニオンを活用してもらったらいいと思います。
渡り歩くのはどうかと思いますが、ちょっと相談という意味合いでセカンドオピニオンされるのはおすすめです。
医師のプロフィール
土井伸浩先生
●昭和大学歯学部卒業●広島大学歯学部 歯科保存学第二教室(現 歯周病態学分野)入局
●(医)オリーブ・ファミリー・デンタルクリニック勤務
●広島大学歯学部 歯科保存学第二教室(現 歯周病態学分野)同門会 会長
●土井ファミリー歯科医院 院長
●広島大学病院 非常勤講師
●D.S.S会長
‐資格・所属学会‐
・日本歯周病学会 専門医・指導医
・日本口腔インプラント学会 専門医
・日本小児歯科学会
・広島県介護支援専門員
・厚生労働省「協力型 臨床研修施設」指定
■□■□ 2025年5月によく読まれた記事をCHECK! □■□■
命にかかわる病気ではありませんが、経過観察と言われたら生理の変化に気を付けて。過多月経や月経痛がひどくなるなどの場合は早めに産婦人科に相談しましょう。
実は10代、20代の女性の死因上位に挙げられる摂食障害。
人の価値や美しさは、体型や体重で決まるものではありません。
適切なカウンセリングで過度な痩せ願望やストレスから自分の体を守りましょう。
幼児や児童に感染することが多く、発症すると喉の痛み、熱、発疹などといった風邪と似た症状が起こります。また、痛みはないのですが、舌の表面に赤いぶつぶつができることがあります。
尋常性疣贅は、「ヒト乳頭腫ウイルス」というウイルスの一種が皮膚に感染してできます。手あれや髭剃り後など、目に見えないくらいの小さな傷からでもウイルスが侵入します。どこの部位にもできる可能性があるのです。
咽喉頭異常感症は心理的要因が大きいといわれています。
喉がイガイガする、圧迫感がある、引っ掛かったり、絡んだような感じがするなど
考えれば考えるほど、喉に違和感を抱き、そのストレスが引き金になって症状を引き起こすことも多いようです。
「不安障害」とはその名の通り、不安な気持ちが強くなる病気です。
ある特定の状況や場所で非常に強い不安に襲われ、身体のいろいろな部分に様々な症状が現われたり、不安を避けようとする「回避行動」をとるようになったり、また安心を得るために無意味な行動を反復してしまうといったことが起こり、人によってはそれが原因で社会生活に支障をきたすこともあります。