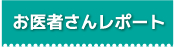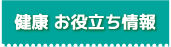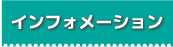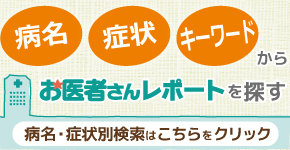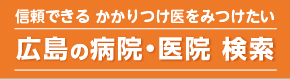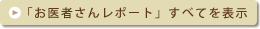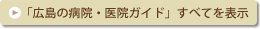広島の頼れるかかりつけ医&病院・医院・クリニックに出会える健康情報サイト
(この記事は2016年4月25日時点の情報です)
池田歯科医院
【住所】広島県呉市阿賀中央2-3-8
【TEL】 0823-71-8226

毎日お口の中で身体の一部として働いてくれるクラウン・ブリッジや入れ歯。違和感やトラブルなく付き合っていきたいですよね。
今回は、呉の閑静な阿賀地区にある「池田歯科医院」の池田敦治院長に、お口の機能回復やクラウン・ブリッジ・入れ歯について、お話をうかがいました。
「ブラッシングってどうすればいいの?」「妊娠中って歯医者さんの治療を受けられるの?」「子どもが歯医者さんを怖がるんだけど…」そんな疑問やお悩みをお持ちの方へのヒントもいただきましたよ。
噛み合わせや失った機能を回復させるには、1本単位だと自分の歯根の上に治療をして被せていくクラウン(冠)・ブリッジ(橋義歯)、歯根ごとなくなったところを部分的に補うパーシャルデンチャー(局部義歯)、もしくは全部歯がなくなった場合のフルデンチャー(総義歯)があります。
自分の歯根がある場合はしっかり根っこの治療をして、歯周病のケアをして、その上で冠を被せて機能を回復します。まず「噛む事」が第一。
奥歯で物を噛む、前歯で物を噛み切る、正しい発音をさせるというのがまず基本で、次に咀噛運動(ローテーション)を考えます。人にはそれぞれ生まれ持った噛み合わせがあって、正常な噛み方にも個性があるので(個性正常咬合)、治療しながら「この人の噛み方はどうだろうか」というのを見ていきます。
「左右均等に噛んでいます」という方も中にはいらっしゃるかもしれないけど、人間というのは左右で7:3であったり6:4であったり必ず噛み癖がありますから。
物を噛む時、横に歯ぎしりする運動だけでも3種類あって、犬歯誘導(ミューチュアリー)、側方歯群で誘導(側方運動)するグループファンクション、義歯などの作られたもので調整するフルバランスオクルージョン。そのような、個人に合った噛み方を探し求めた治療を目標にしています。
耳の前に手を当てて顎を動かすと関節が動くのが分かりますよね。
個性正常咬合を求めて治療していかないと、ここの関節に将来影響が出ます。
顎関節症といいますが、顎がカクカクいったり(クリック音)、口が開かなくなったり。
そうなると今度は耳鳴りがしたり頭痛が起きたり肩こりがきますから、常に噛み合わせを意識しています。
お口の中全体をみながらバランスよく。
たとえば失った前歯に白い冠を被せると、そこでまず「噛む」という機能の回復と発音の回復ができますよね。それに満足すると、人間というのは次の段階を求めます。今度は見た目を良くしたい、よりよい材質でやっていきたい。昔は1種類しかなかったセラミックも今はいろんな種類が出ていますから。
クラウン・ブリッジ、パーシャルデンチャー、フルデンチャーいずれも保険でできますが、保険適用になる材料は厚生省で決められていて、白い冠の場合はプラスチックになります。プラスチックは日焼けもするし吸水性があるので2〜3年経つと色が変わってきます。たとえばカレーをプラスチックの容器にずっと入れていると黄ばんで取れなくなりますよね。でもセラミック(陶器)の容器にカレーを入れ続けても着色しないでしょ?だから前歯など審美的要求がある場合は材料を変えるわけです。
パーシャルデンチャーは保険のものだとバネが見えてしまうので、バネの見えないものや磁石を使ったものが審美を求める場合の入れ歯になります。
また、金属アレルギーの方は金属が使えないので、残された道はセラミックになりますが、陶材にも強度がいろいろあって、じゃあ全部強いのを入れればいいかというとコストの問題もあります。
また、うまく調整して入れないと、反対側の歯が自分の歯だったら、それが削れてくるという症例もあるので、そういった事をよく考えて入れないといけません。
ただ、陶器ですから自分の歯でも欠けるかもしれない強い衝撃が加わるような事故でパリンといったりする事はありますね。
見た目的にボロボロになって「もう変えた方がいいですよ」と思うような方もいらっしゃいますが、噛み合わせそのものは裏面の金属で決めてあって特に問題はないので、「これでいい」とおっしゃる方も中にはおられます。
入れ歯というのは出来上がってから調整して入れますが、うちはその後2〜3回必ず来てもらって調整します。初めて入れられる方と若い頃から入れておられる方では安定するまで全然違う。特に、初めての入れ歯は、あんな異物が入るわけだから難しいに決まっています。とにかく1ヶ月辛抱して使ってみてもらって、入れて1ヶ月くらいは毎週様子をみます。それでダメな方はダメなので他の方法を考えます。
たとえば歯が1本ないだけでも選択肢はたくさんあります。1本の歯がなくなって、あとは全部自分の歯がある場合の選択肢は「そのまま放置する」、歯を削りたくなかったらバネをかける「パーシャルデンチャー」、歯を削っていいのであれば両サイドを削る「ブリッジ」。バネをかける入れ歯は嫌、歯も削りたくない、このまま放置するのも嫌、という事になれば、最近は手術が必要になる「インプラント」というのがあるから、1本だけ人工歯根を植えてそこにインプラントを入れましょう、という風な治療方針です。
症例によってはインプラントが無理な方もおられますが、その場合も一応すべての選択肢を説明して、あなたはこういうものがあるからこれはできませんよと削除していって、残ったものから選んでいく形です。
いずれにしろ「まず機能の回復をしてから次を追求していく」というのが私のやり方です。
冠を入れる時期が早いと、歯と歯茎の境目が黒くなったり、歯茎が腫れぼったい状態で型をとると、歯茎が落ち着いた時に金属部分が見えたりしますから、仮歯を入れてブラッシングの練習をしたりして歯茎を健康な状態に保った状態で型をとっていかないといけない。だから、何をやるにしてもブラッシング指導をします。
その中で私が勧めているスクラビング法というのは、歯と歯茎に対して歯ブラシの先を45度の角度で押し当てて1〜2ミリずつ微振動させます。気持ち的には1本ずつ磨いてください。正常な歯は28本ありますから、上下表裏ずーっとやっていくと大体20〜30分くらいかかります。だからこれは夜だけ頑張ってください。寝ている間は口の中が乾燥して、歯周病や虫歯の菌が繁殖しやすいので、寝る前になるべく菌をとってやるんです。
洗面台の前で自分の顔を見ながらやると飽きるので、ソファに座ってテレビを見ながらでもいいしラジオを聞きながらでもいいから、そういう癖をつけてください、と患者さんに言っています。子どもさんやお風呂に浸かる方はお風呂の中でもいいですね。

麻酔もその間ならほとんどOKですし、飲める抗生剤や痛み止めもありますから、麻酔していいか、抗生剤や痛み止めはどれを処方していいか、かかりつけの産婦人科に必ず許可をもらっています。
放射線を気にされますがレントゲンも撮れます。歯科の場合0.01mSv(ミリシーベルト)、お口全体を撮ると0.02mSv。日本に生活していて普通に浴びる放射線は年間2.1mSvですから、図を見てもらってきちんと説明すると、みなさん安心されます。
妊婦さんの場合は4〜8ヶ月でできるところまでやって、あとは出産して落ち着いたら来てください、という形ですね。
小児歯科の場合はどんな治療でも、子どもさんが泣いて何もできなくても、30分の時間をとっています。お子さんの歯科治療は予防接種のように一瞬で終わるわけではないので、自分の意思でやらないと進みません。
うちでは、どうしても緊急を要する処置が必要でない限り、押さえつける事はしないので、自分の意志で口を開けて「やる」というまでずーっと待ちます。泣き喚いたりする子どもは、とりあえず泣き終わるのを待つし、お母さんに了承を得た上で恐怖心を取り除くために歯磨きだけで帰す事もあります。「痛くないと言われたのに痛い」という事がないよう、痛い時は教えてもらって、治療をやめて次の処置方針を考えていきます。
うちでは治療中、音の出るおもちゃを持ってもらって、痛い時や苦しい時はそれをピーッと鳴らしてもらいます。子どもは特にこういうのを持っているだけで気が紛れたり、「これを鳴らすとやめてもらえる」と安心できますから。
大人でも「痛い時や苦しい時は手をあげてください」といわれても、我慢されたりしてなかなか手があげられませんから、うちでは大人にもこれを持ってもらっています(笑)。
そのうちみんな泣かずに治療できるようになってきますが、虫歯や歯が折れたり欠けたりしないと歯医者さんに来たらいけないと思っている方も結構いらっしゃるので、まずは検診に来て、慣れてもらう事が一番です。検診はいわば予防で、痛くない処置ですからね。
まぁそれだけ言える間柄で信頼関係を持たないといけないですけどね。原点に返るけれども、うちは機能の回復とバランスを基本に、そこから枝葉をのばしていく治療方針です。
私の母校は東京ですが、10月からクラウン・ブリッジの基礎実習というのが始まるので10月から1月の間は数回、診療室を休んで非常勤講師として大学の学生の指導を行っています。東京まで行くのはしんどいけど、何でも基礎が大切。基礎を身につけておかないと応用ができませんからね。
前の診療室の時は18時までの診療でしたが、それだとサラリーマンの方が来られないので、移転した時に19時までにしました。18時40分が最終の予約時間になるのですが、その時間帯の予約から埋まっていきますね。
夜になると見えませんが、診療室の窓から四季折々の山が見えるので患者さんは喜ばれますよ。
山が綺麗っていうのは田舎の特権ですね、秋なんか、すごく綺麗ですよ。
●広島大学大学院 歯学研究科 修了
●池田歯科医院 院長
●東京歯科大学 非常勤講師
‐資格・所属学会‐
・歯学博士
・日本接着歯学学会認定医
・日本補綴歯科学会
・日本歯科理工学会
池田敦治 先生(歯科)
クラウン・ブリッジや入れ歯を快適に。一人一人の噛み癖まで考慮する治療
池田歯科医院
【住所】広島県呉市阿賀中央2-3-8
【TEL】 0823-71-8226

聞き取りやすい低音ボイスと、誠実で話しやすい人柄が印象的な池田院長
毎日お口の中で身体の一部として働いてくれるクラウン・ブリッジや入れ歯。違和感やトラブルなく付き合っていきたいですよね。
今回は、呉の閑静な阿賀地区にある「池田歯科医院」の池田敦治院長に、お口の機能回復やクラウン・ブリッジ・入れ歯について、お話をうかがいました。
「ブラッシングってどうすればいいの?」「妊娠中って歯医者さんの治療を受けられるの?」「子どもが歯医者さんを怖がるんだけど…」そんな疑問やお悩みをお持ちの方へのヒントもいただきましたよ。
先生が診療で重視されていることは何ですか?
大学病院では補綴の研究室にいて、補綴を専門にやっていましたが、補綴科では「機能の回復」、つまり噛み合わせの回復をまず第一に考えます。噛み合わせや失った機能を回復させるには、1本単位だと自分の歯根の上に治療をして被せていくクラウン(冠)・ブリッジ(橋義歯)、歯根ごとなくなったところを部分的に補うパーシャルデンチャー(局部義歯)、もしくは全部歯がなくなった場合のフルデンチャー(総義歯)があります。
自分の歯根がある場合はしっかり根っこの治療をして、歯周病のケアをして、その上で冠を被せて機能を回復します。まず「噛む事」が第一。
機能の回復、噛み合わせの回復というのは重要なことなのですね。
往診に行ったりしても、入れ歯を入れてない方に入れ歯を入れるとしっかりしてきたり、口がずっと動いている方の揺れが止まるというような症例を多々見ています。奥歯で物を噛む、前歯で物を噛み切る、正しい発音をさせるというのがまず基本で、次に咀噛運動(ローテーション)を考えます。人にはそれぞれ生まれ持った噛み合わせがあって、正常な噛み方にも個性があるので(個性正常咬合)、治療しながら「この人の噛み方はどうだろうか」というのを見ていきます。
「左右均等に噛んでいます」という方も中にはいらっしゃるかもしれないけど、人間というのは左右で7:3であったり6:4であったり必ず噛み癖がありますから。
物を噛む時、横に歯ぎしりする運動だけでも3種類あって、犬歯誘導(ミューチュアリー)、側方歯群で誘導(側方運動)するグループファンクション、義歯などの作られたもので調整するフルバランスオクルージョン。そのような、個人に合った噛み方を探し求めた治療を目標にしています。
正常な噛み方でも、使う歯や顎の動かし方は一人一人違うのですね。
噛み合わせが狂うと、今度は口腔内だけでなく関節にくるんです。耳の前に手を当てて顎を動かすと関節が動くのが分かりますよね。
個性正常咬合を求めて治療していかないと、ここの関節に将来影響が出ます。
顎関節症といいますが、顎がカクカクいったり(クリック音)、口が開かなくなったり。
そうなると今度は耳鳴りがしたり頭痛が起きたり肩こりがきますから、常に噛み合わせを意識しています。
お口の中全体をみながらバランスよく。
最近は様々な材質の冠や入れ歯があるようですね。
噛む事ができるようになると、次に人は見た目(審美性)を求めるようになります。たとえば失った前歯に白い冠を被せると、そこでまず「噛む」という機能の回復と発音の回復ができますよね。それに満足すると、人間というのは次の段階を求めます。今度は見た目を良くしたい、よりよい材質でやっていきたい。昔は1種類しかなかったセラミックも今はいろんな種類が出ていますから。
クラウン・ブリッジ、パーシャルデンチャー、フルデンチャーいずれも保険でできますが、保険適用になる材料は厚生省で決められていて、白い冠の場合はプラスチックになります。プラスチックは日焼けもするし吸水性があるので2〜3年経つと色が変わってきます。たとえばカレーをプラスチックの容器にずっと入れていると黄ばんで取れなくなりますよね。でもセラミック(陶器)の容器にカレーを入れ続けても着色しないでしょ?だから前歯など審美的要求がある場合は材料を変えるわけです。
パーシャルデンチャーは保険のものだとバネが見えてしまうので、バネの見えないものや磁石を使ったものが審美を求める場合の入れ歯になります。
また、金属アレルギーの方は金属が使えないので、残された道はセラミックになりますが、陶材にも強度がいろいろあって、じゃあ全部強いのを入れればいいかというとコストの問題もあります。
また、うまく調整して入れないと、反対側の歯が自分の歯だったら、それが削れてくるという症例もあるので、そういった事をよく考えて入れないといけません。
セラミックはどのくらい耐久性があるのですか?
セラミックそのものは不変なので、自分の歯がもてば、壊れない限り一生もちます。ただ、陶器ですから自分の歯でも欠けるかもしれない強い衝撃が加わるような事故でパリンといったりする事はありますね。
プラスチックはどうでしょうか?
プラスチックも一生もつといえばもちます。でも、色が変わったり摩耗で削れて下の金属が透けてくる事はあります。見た目的にボロボロになって「もう変えた方がいいですよ」と思うような方もいらっしゃいますが、噛み合わせそのものは裏面の金属で決めてあって特に問題はないので、「これでいい」とおっしゃる方も中にはおられます。
そのようになった時は作り替えができるのですね。
できるのですが、保険の範囲でする場合は縛りがあって、クラウン・ブリッジは2年以内、入れ歯は半年以内はできません。入れ歯というのは出来上がってから調整して入れますが、うちはその後2〜3回必ず来てもらって調整します。初めて入れられる方と若い頃から入れておられる方では安定するまで全然違う。特に、初めての入れ歯は、あんな異物が入るわけだから難しいに決まっています。とにかく1ヶ月辛抱して使ってみてもらって、入れて1ヶ月くらいは毎週様子をみます。それでダメな方はダメなので他の方法を考えます。
ダメというのは具体的にどういう事でしょうか?
嘔吐反射が激しい、要するに上顎の口蓋や下の歯茎の内側などを触ったらオエッとなる方などは生理的に受け付けないでしょうし、精神的に異物が入っていると思うと頭が痛くなるとか、締め付けられて頭が痛くなるという方もいます。入れて頭が痛くなる方は慎重に対応しています。そのような事も含めて、治療方法や使う材質はどのように決めていくのでしょうか。
何でもそうですが、こちらが強制的に「これですよ」という治療方針を示すのではなく、選択肢をいくつか説明して、その中からどうやっていくか患者さんと話し合って決めていきます。たとえば歯が1本ないだけでも選択肢はたくさんあります。1本の歯がなくなって、あとは全部自分の歯がある場合の選択肢は「そのまま放置する」、歯を削りたくなかったらバネをかける「パーシャルデンチャー」、歯を削っていいのであれば両サイドを削る「ブリッジ」。バネをかける入れ歯は嫌、歯も削りたくない、このまま放置するのも嫌、という事になれば、最近は手術が必要になる「インプラント」というのがあるから、1本だけ人工歯根を植えてそこにインプラントを入れましょう、という風な治療方針です。
症例によってはインプラントが無理な方もおられますが、その場合も一応すべての選択肢を説明して、あなたはこういうものがあるからこれはできませんよと削除していって、残ったものから選んでいく形です。
なぜ無理なのかも含めてじっくり説明いただけると納得して治療が受けられますね。
だからうちは基本的に20分に1人しか診られません。大学の補綴科で1時間に1人診ていた習慣がついているので、20分でもプレッシャーがかかるくらい。いずれにしろ「まず機能の回復をしてから次を追求していく」というのが私のやり方です。
冠を入れる時期が早いと、歯と歯茎の境目が黒くなったり、歯茎が腫れぼったい状態で型をとると、歯茎が落ち着いた時に金属部分が見えたりしますから、仮歯を入れてブラッシングの練習をしたりして歯茎を健康な状態に保った状態で型をとっていかないといけない。だから、何をやるにしてもブラッシング指導をします。
ブラッシングはどのようにするとよいのでしょうか?
染め出し液をつけて、汚れている部分を鏡で見てもらって「ここはこういう風に磨きましょう」と指導しますが、ブラッシングの方法ってたくさんあるんです。その中で私が勧めているスクラビング法というのは、歯と歯茎に対して歯ブラシの先を45度の角度で押し当てて1〜2ミリずつ微振動させます。気持ち的には1本ずつ磨いてください。正常な歯は28本ありますから、上下表裏ずーっとやっていくと大体20〜30分くらいかかります。だからこれは夜だけ頑張ってください。寝ている間は口の中が乾燥して、歯周病や虫歯の菌が繁殖しやすいので、寝る前になるべく菌をとってやるんです。
洗面台の前で自分の顔を見ながらやると飽きるので、ソファに座ってテレビを見ながらでもいいしラジオを聞きながらでもいいから、そういう癖をつけてください、と患者さんに言っています。子どもさんやお風呂に浸かる方はお風呂の中でもいいですね。

休山トンネル東口から北側へ。院長・副院長ともに患者さんとのコミュニケーションを大切にした診療をしている
ところで妊婦さんは歯科治療を受けられるのでしょうか?
うちでは妊婦さんには「安定期である妊娠4ヶ月〜8ヶ月の間は治療しますよ」と説明しています。初診の方には必ず何週目か聞いて、そこから計算して治療できる範囲でやります。麻酔もその間ならほとんどOKですし、飲める抗生剤や痛み止めもありますから、麻酔していいか、抗生剤や痛み止めはどれを処方していいか、かかりつけの産婦人科に必ず許可をもらっています。
放射線を気にされますがレントゲンも撮れます。歯科の場合0.01mSv(ミリシーベルト)、お口全体を撮ると0.02mSv。日本に生活していて普通に浴びる放射線は年間2.1mSvですから、図を見てもらってきちんと説明すると、みなさん安心されます。
妊婦さんの場合は4〜8ヶ月でできるところまでやって、あとは出産して落ち着いたら来てください、という形ですね。
お子さんはどのように治療されていますか?
小児歯科は副院長が担当していますが、お母さんと一緒に入ってもらって、お母さんの前で説明しながら治療します。小児歯科の場合はどんな治療でも、子どもさんが泣いて何もできなくても、30分の時間をとっています。お子さんの歯科治療は予防接種のように一瞬で終わるわけではないので、自分の意思でやらないと進みません。
うちでは、どうしても緊急を要する処置が必要でない限り、押さえつける事はしないので、自分の意志で口を開けて「やる」というまでずーっと待ちます。泣き喚いたりする子どもは、とりあえず泣き終わるのを待つし、お母さんに了承を得た上で恐怖心を取り除くために歯磨きだけで帰す事もあります。「痛くないと言われたのに痛い」という事がないよう、痛い時は教えてもらって、治療をやめて次の処置方針を考えていきます。
うちでは治療中、音の出るおもちゃを持ってもらって、痛い時や苦しい時はそれをピーッと鳴らしてもらいます。子どもは特にこういうのを持っているだけで気が紛れたり、「これを鳴らすとやめてもらえる」と安心できますから。
大人でも「痛い時や苦しい時は手をあげてください」といわれても、我慢されたりしてなかなか手があげられませんから、うちでは大人にもこれを持ってもらっています(笑)。
そのうちみんな泣かずに治療できるようになってきますが、虫歯や歯が折れたり欠けたりしないと歯医者さんに来たらいけないと思っている方も結構いらっしゃるので、まずは検診に来て、慣れてもらう事が一番です。検診はいわば予防で、痛くない処置ですからね。
大人も子どもも定期健診でしっかり予防する事が大切ですね。
1度うちに来た患者さんには、大人の方は最低でも6ヶ月に1回は来院してもらって、よかったらいいし、悪い部位が見つかれば治療に入るのですが、まぁみんな来ない来ない(笑)。2〜3年経って来られて、カルテ見て「あ、3年経ってるの」と思うじゃないですか。「6ヶ月というのはあなたにとって3年なんだね」と私、必ず言うんです(笑)。まぁそれだけ言える間柄で信頼関係を持たないといけないですけどね。原点に返るけれども、うちは機能の回復とバランスを基本に、そこから枝葉をのばしていく治療方針です。
私の母校は東京ですが、10月からクラウン・ブリッジの基礎実習というのが始まるので10月から1月の間は数回、診療室を休んで非常勤講師として大学の学生の指導を行っています。東京まで行くのはしんどいけど、何でも基礎が大切。基礎を身につけておかないと応用ができませんからね。
先生はこのあたりのご出身ですか?
うちは祖父、父、私と同じ歯科大学なんです。祖父が広長浜で歯科医をしていたので、昔は祖父の診療をじーっと見たりしていました。そこからずっと系列でもう100年くらいになるんじゃないかな。父はここのすぐ近くで開業していました。そこに私が入って一緒にやっていたのですが、診療室を一新して充実した設備のもとで治療をしたいという事で、私が院長になって移転して、今12年くらい経ちます。前の診療室の時は18時までの診療でしたが、それだとサラリーマンの方が来られないので、移転した時に19時までにしました。18時40分が最終の予約時間になるのですが、その時間帯の予約から埋まっていきますね。
夜になると見えませんが、診療室の窓から四季折々の山が見えるので患者さんは喜ばれますよ。
山が綺麗っていうのは田舎の特権ですね、秋なんか、すごく綺麗ですよ。
医師のプロフィール
池田敦治先生
●東京歯科大学 卒業●広島大学大学院 歯学研究科 修了
●池田歯科医院 院長
●東京歯科大学 非常勤講師
‐資格・所属学会‐
・歯学博士
・日本接着歯学学会認定医
・日本補綴歯科学会
・日本歯科理工学会
■□■□ 2026年1月によく読まれた記事をCHECK! □■□■
命にかかわる病気ではありませんが、経過観察と言われたら生理の変化に気を付けて。過多月経や月経痛がひどくなるなどの場合は早めに産婦人科に相談しましょう。
実は10代、20代の女性の死因上位に挙げられる摂食障害。
人の価値や美しさは、体型や体重で決まるものではありません。
適切なカウンセリングで過度な痩せ願望やストレスから自分の体を守りましょう。
幼児や児童に感染することが多く、発症すると喉の痛み、熱、発疹などといった風邪と似た症状が起こります。また、痛みはないのですが、舌の表面に赤いぶつぶつができることがあります。
尋常性疣贅は、「ヒト乳頭腫ウイルス」というウイルスの一種が皮膚に感染してできます。手あれや髭剃り後など、目に見えないくらいの小さな傷からでもウイルスが侵入します。どこの部位にもできる可能性があるのです。
咽喉頭異常感症は心理的要因が大きいといわれています。
喉がイガイガする、圧迫感がある、引っ掛かったり、絡んだような感じがするなど
考えれば考えるほど、喉に違和感を抱き、そのストレスが引き金になって症状を引き起こすことも多いようです。
「不安障害」とはその名の通り、不安な気持ちが強くなる病気です。
ある特定の状況や場所で非常に強い不安に襲われ、身体のいろいろな部分に様々な症状が現われたり、不安を避けようとする「回避行動」をとるようになったり、また安心を得るために無意味な行動を反復してしまうといったことが起こり、人によってはそれが原因で社会生活に支障をきたすこともあります。