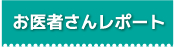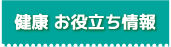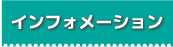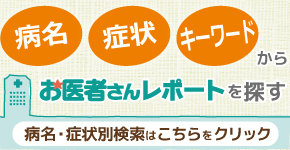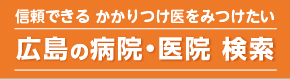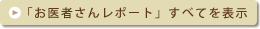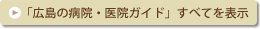広島の頼れるかかりつけ医&病院・医院・クリニックに出会える健康情報サイト
(この記事は2012年11月1日時点の情報です)
医療法人社団 水野皮ふ科
【住所】広島県広島市東区若草町11-1-101 ザ・広島タワー1F
【TEL】 082-263-6775

「おしゃれが大好き」「仕事に夢中」、いつも一生懸命な女性の姿は輝いています。その反面、「近ごろ足に異変が…」と人知れず悩んでいる人も多いのでは。最近は女性の間でも水虫が増加中で、夏場は特に注意が必要だとか。そこで、水野皮ふ科の水野寛先生に水虫について聞きました。
白癬菌はいろいろな場所にいますが、乾いた状態の皮膚に付着しても、皮膚に入り込むまでには24時間から30時間くらいかかるといわれています。その間に足を洗えば菌も流れていくので、感染することはありません。しかし、蒸れた状態だと、わずか3、4時間で入り込んでしまうため、感染しやすくなります。
そのため、水虫は、梅雨の時季から増え始め、8月くらいまでのジメジメした蒸し暑い時期にひどくなります。
基本的には男性に多いのですが、最近は女性にも増えています。働く女性が多くなり、男性同様に革靴などを長時間履いていることが原因とも考えられます。
平均気温が高めの場所にいたり、靴を1日8時間以上履いていたり、家族に水虫の人がいる場合は、かかりやすいといわれています。
爪に発生する爪水虫は、爪が白く濁ったり、分厚くなるのが特徴です。ジュクジュクした状態を放っておくと、二次感染を起こすこともあり、特に糖尿病など基礎疾患のある人は、足の切断に至るケースもあります。
メスのようなもので皮膚の表面をこすって取り、顕微鏡で白癬菌がいるかどうか調べます。
女性の靴は先が細くなっているものが多いので、指と指がくっついて蒸れやすくなっています。ストッキングも蒸れの原因の一つです。
また、同じ靴を履き続けるのもよくありません。ブーツを履く場合、ブーツの中を定期的に乾かすことも大切です。毎日履くうちに菌を繁殖させている可能性があります。
靴は、ある程度風通しのよいものを履くようにしましょう。オフィスではサンダルに履き替えたり、ずっと靴を履いている場合は、休憩時間などに足を洗うのがベストですが、靴を脱いで乾かすだけでも予防効果があります。靴下を履きかえたり、5本指の靴下を履くのもいいでしょう。
●広島大学病院皮膚科入局
●中国労災病院、広島大学病院、県立広島病院、広島市立安佐市民病院で勤務
・日本皮膚科学会 専門医
・日本形成外科学会
・日本皮膚外科学会
・日本臨床皮膚科学会
・日本皮膚悪性腫瘍学会
水野寛 先生(皮膚科)
おしゃれや仕事が原因?! 女性の素足に「水虫」警報!
医療法人社団 水野皮ふ科
【住所】広島県広島市東区若草町11-1-101 ザ・広島タワー1F
【TEL】 082-263-6775

水野先生のもとには、アトピー性皮膚炎に苦しむ子供や、水虫、いぼ、できものなどの皮膚の悩みを抱える幅広い患者が訪れる
「おしゃれが大好き」「仕事に夢中」、いつも一生懸命な女性の姿は輝いています。その反面、「近ごろ足に異変が…」と人知れず悩んでいる人も多いのでは。最近は女性の間でも水虫が増加中で、夏場は特に注意が必要だとか。そこで、水野皮ふ科の水野寛先生に水虫について聞きました。
水虫はどうしたらできるのですか?
水虫は、皮膚の成分である「ケラチン」というタンパク質を栄養源とするカビの一種「白癬菌」が、皮膚に寄生することで発症します。白癬菌はいろいろな場所にいますが、乾いた状態の皮膚に付着しても、皮膚に入り込むまでには24時間から30時間くらいかかるといわれています。その間に足を洗えば菌も流れていくので、感染することはありません。しかし、蒸れた状態だと、わずか3、4時間で入り込んでしまうため、感染しやすくなります。
どんなときに、どんな人がなりやすいですか?
白癬(はくせん)菌が好むのは、高温多湿。そのため、水虫は、梅雨の時季から増え始め、8月くらいまでのジメジメした蒸し暑い時期にひどくなります。
基本的には男性に多いのですが、最近は女性にも増えています。働く女性が多くなり、男性同様に革靴などを長時間履いていることが原因とも考えられます。
平均気温が高めの場所にいたり、靴を1日8時間以上履いていたり、家族に水虫の人がいる場合は、かかりやすいといわれています。
放っておくと、どうなるのでしょうか?
放っておくと、体全体に広がったり、家族にうつしてしまうことも。白癬菌は皮膚に寄生するので、足に限らず、頭や顔、手や尻、爪など、どこにでも発生します。体に発生する場合は輪を描いたような紅斑になります。爪に発生する爪水虫は、爪が白く濁ったり、分厚くなるのが特徴です。ジュクジュクした状態を放っておくと、二次感染を起こすこともあり、特に糖尿病など基礎疾患のある人は、足の切断に至るケースもあります。
もしかして水虫?と思ったら、どうすればいいですか?
水虫の治療を始める前に、診断をはっきりさせることが必要です。汗の管が詰まって起こる湿疹など、水虫と同じような症状が出る別の病気もあるので、自己判断は禁物。検査は外来ですぐ行えるので、まずは皮膚科できちんと検査してもらいましょう。メスのようなもので皮膚の表面をこすって取り、顕微鏡で白癬菌がいるかどうか調べます。
水虫にならないために、日頃から気をつけておくべき事は何ですか?
一番の大敵は蒸れ。足を蒸らさないようにすることが大切です。女性の靴は先が細くなっているものが多いので、指と指がくっついて蒸れやすくなっています。ストッキングも蒸れの原因の一つです。
また、同じ靴を履き続けるのもよくありません。ブーツを履く場合、ブーツの中を定期的に乾かすことも大切です。毎日履くうちに菌を繁殖させている可能性があります。
靴は、ある程度風通しのよいものを履くようにしましょう。オフィスではサンダルに履き替えたり、ずっと靴を履いている場合は、休憩時間などに足を洗うのがベストですが、靴を脱いで乾かすだけでも予防効果があります。靴下を履きかえたり、5本指の靴下を履くのもいいでしょう。
記事提供:広島リビング新聞社
医師のプロフィール
水野寛 先生
●山口大学医学部●広島大学病院皮膚科入局
●中国労災病院、広島大学病院、県立広島病院、広島市立安佐市民病院で勤務
・日本皮膚科学会 専門医
・日本形成外科学会
・日本皮膚外科学会
・日本臨床皮膚科学会
・日本皮膚悪性腫瘍学会
■□■□ 2025年5月によく読まれた記事をCHECK! □■□■
命にかかわる病気ではありませんが、経過観察と言われたら生理の変化に気を付けて。過多月経や月経痛がひどくなるなどの場合は早めに産婦人科に相談しましょう。
実は10代、20代の女性の死因上位に挙げられる摂食障害。
人の価値や美しさは、体型や体重で決まるものではありません。
適切なカウンセリングで過度な痩せ願望やストレスから自分の体を守りましょう。
幼児や児童に感染することが多く、発症すると喉の痛み、熱、発疹などといった風邪と似た症状が起こります。また、痛みはないのですが、舌の表面に赤いぶつぶつができることがあります。
尋常性疣贅は、「ヒト乳頭腫ウイルス」というウイルスの一種が皮膚に感染してできます。手あれや髭剃り後など、目に見えないくらいの小さな傷からでもウイルスが侵入します。どこの部位にもできる可能性があるのです。
咽喉頭異常感症は心理的要因が大きいといわれています。
喉がイガイガする、圧迫感がある、引っ掛かったり、絡んだような感じがするなど
考えれば考えるほど、喉に違和感を抱き、そのストレスが引き金になって症状を引き起こすことも多いようです。
「不安障害」とはその名の通り、不安な気持ちが強くなる病気です。
ある特定の状況や場所で非常に強い不安に襲われ、身体のいろいろな部分に様々な症状が現われたり、不安を避けようとする「回避行動」をとるようになったり、また安心を得るために無意味な行動を反復してしまうといったことが起こり、人によってはそれが原因で社会生活に支障をきたすこともあります。