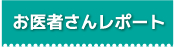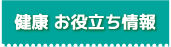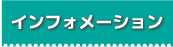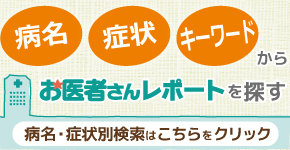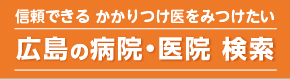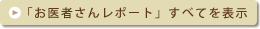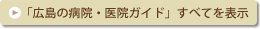広島の頼れるかかりつけ医&病院・医院・クリニックに出会える健康情報サイト
(この記事は2015年8月20日時点の情報です)
いつかいち駅前内科
【住所】広島県広島市佐伯区五日市駅前1-5-18-401
【TEL】 082-943-6022

糖尿病は初期には自覚症状がほとんどなく、気付いた時には重度の合併症を発症しているケースが多い恐ろしい病気です。しかも一度発症すると完治は難しく、血糖値を上手にコントロールしながら合併症の発症を予防し、進行を食い止める必要があります。
一生のお付き合いになる治療だからこそ、患者さんの生活の質QOL(Quality of life)を確保することがとても大切だとおっしゃるのが、佐伯区にあるいつかいち駅前内科の院長、粟屋智一先生です。
今回は糖尿病の合併症について詳しくご説明いただきながら、粟屋先生がいつも大切にしている患者さんとの対話やフットケアなど、患者さんの生活の質QOLを意識した治療についてお話をうかがいました。
糖尿病には、インスリンという人のすい臓から分泌されるホルモンが密接に関わっています。インスリンが働くことで血液中のブドウ糖を全身の臓器に吸収させることができるのですが、糖尿病はこのインスリンが不足、あるいはうまく機能しないことで高血糖になります。
初期に体に出る症状として知られているのは、のどの渇きや頻尿などですが、ほとんどの方には自覚症状がありません。何らかの症状に気付く頃にはすでに合併症が進行しているケースがあります。そのため自覚症状がないからといって放置できない病気、それが糖尿病です。
2013年に血糖のコントロール目標が変わりました。以前は、HbA1cは低いほど良いとされていましたが、厳し過ぎるコントロールで低血糖を生じるとかえって悪い影響を与えるという研究結果が出ました。そのため現在は、合併症予防の観点からHbA1c 7.0%未満を基準に、患者さんそれぞれでコントロール目標を設定することになりました。
もちろん、血糖をしっかり下げれば合併症を予防できます。しかし、例えばご高齢で治療強化が困難な方なら8%を目標にするなど、人それぞれに合うコントロール目標を定めるようになっています。この傾向は日本だけでなく世界的に見られるものです。
まず1型は、インスリンを分泌するすい臓の細胞が何らかの原因で破壊されて、インスリンが分泌されないタイプです。
2型は、体質的な要素に、過食や運動不足などの要因が加わって引き起こされる生活習慣病の1つです。
その他の原因による糖尿病は、遺伝子やホルモンの異常、薬剤の副作用などが原因のものです。
4つ目は、妊娠中の糖尿病で、胎盤が生成するホルモンによってインスリンの作用が抑えられることで起こります。妊娠中は通常よりも血糖値管理が厳しくなるので、産婦人科の医師からの紹介で来院される方が多くいらっしゃいます。
われわれ専門医はこれらすべての糖尿病の診療を行います。
特に気を付けなければいけないのは、高血糖が長く続くことによって発症する慢性合併症です。合併症が進行すれば失明に至ることもありますし、人工透析が必要になるケースもあります。患者さんの生活の質QOL(Quality of life)を落とすばかりか、命をも落としかねない状況を引き起こすことがあるのです。そのため糖尿病はサイレントキラー(沈黙の殺人者)と呼ばれています。
基本的に合併症の症状が出てしまった場合は、進行を完全に止めることは難しくなります。裏を返せば、合併症を発症する前に、高血糖であることに気付いて血糖値を上手にコントロールすることができれば、他の方と同じように生活することが可能です。
糖尿病は、健康診断によって血糖値が高いという結果が出て初めて気付く方が大半ですが、合併症を予防するためには、気付いたらすぐに治療することが重要です。
糖尿病網膜症は、高血糖によって眼の奥の網膜が障害を受け、視力の低下や最悪の場合には失明する恐れがあります。出血が起こると突然光を失うこともあるので気を付けなければいけません。
次に糖尿病腎症は、高血糖によって、体内の老廃物を尿として流す腎臓の働きが悪くなります。症状としては血圧の上昇や、尿にタンパクが出てむくむなどです。進行すると腎不全や尿毒症を引き起こして透析が必要になったり、生命に関わることもあります。
糖尿病神経障害は、知覚神経や自律神経に障害が生じて、手足の痛みやほてり、しびれなどの他、便秘や下痢、立ちくらみ、勃起障害(ED)などを引き起こします。進行すると足の潰瘍(かいよう)や壊疽(えそ)の原因になります。
いずれも病状が進むと患者さんの生活の質QOLに影響しますが、適切な血糖コントロールで進行を抑えることができます。
まず、脳卒中には主に脳梗塞・脳出血・くも膜下出血がありますが、この中で糖尿病患者に多いのは脳梗塞です。手足が動かなくなったり、言葉が出なくなる、物が二重に見えるなどの症状があり、生命に関わることがあります。さらに手足の麻痺や言語障害などの後遺症が出ることもありますので、細心の注意が必要です。
次に心筋梗塞は、心臓に栄養や酸素を送り続けている冠動脈が動脈硬化を起こし、心臓の働き自体が低下してしまう病気です。これも生命に関わることがあります。
そして、末梢動脈性疾患は、足の動脈が硬化することで起こる血流の低下が原因です。進行とともに足のしびれや痛みが出て、歩くことが困難になります。さらに悪化すると潰瘍ができたり、足の一部が腐る壊疽を起こすことがあります。
糖尿病は、合併症を予防することで、生活の質QOLの低下を防ぐことができる病気です。ところがその一方で、予防に固執して食事・運動療法などの治療を厳しくし過ぎると、生活の質QOLを低下させてしまうという一面も持っています。また無理を強いられる治療は長く続きません。
そのため当クリニックでは、糖尿病診療を進めていく上で、生活の質QOLをなるべく低下させない食事療法、運動療法、薬物療法を患者さんと一緒に考えるようにしています。
運動療法では、週に3日以上30分以上歩くことや、プールに行くことを勧めています。ただし、まとまった時間が取れない人も多いので、ひと駅前で電車を降りて歩くことや、会社の昼休憩に歩くなど、できることから始めます。他にも家の中での柔軟運動や足踏みなどでも良いので、まず始めてみて、相談しながら調整していきます。
無理強いをするのではなく、相談しながら治療内容を決め、その方に合った食事療法や運動療法を長く続けていくことが重要だと考えています。
インスリン治療は、1型糖尿病や、食事療法ではコントロールできない妊娠糖尿病、2型糖尿病で著明な高血糖の方や飲み薬でコントロールできない方などに実施します。インスリン注射は難しいと思われていますが、一般的な注射器と違ったペン型なので操作は簡単です。針は本当に細くて短いので、ほとんど痛みは感じません。
クリニックでは、チェックシートや説明書を用いて繰り返し説明し、安心して使用してもらっています。
例えば、2型糖尿病では以前は1日に2〜4回注射していたインスリン治療は、効果が長時間持続する薬剤が登場し、1日に1回の注射をメインに治療しています。
また、インスリンを持続的に皮下に注入できる携帯型インスリンポンプ(CSII)も改良されました。さらに、炭水化物や糖質の量でインスリンを調整できるカーボカウントも普及して来ました。これらを応用すると、食や運動に対する自由度が高まり、血糖値のコントロールを改善して生活の質QOLを高めることができます。そのため、当院でも1型糖尿病患者さんに推奨しています。
患者さんの生活の質QOLを考えながら、患者さんの病状と患者さんにとって最良の治療をしっかり把握して、いろいろな引き出しを持って治療に当たっています。
進行させないためには予防と早期発見が重要です。当院では糖尿病患者さんには診察で足をチェックし、フットケアをするようにしています。
具体的には、足にできた傷が治りにくくなっていないか、白癬(水虫)や巻き爪などがないかをチェックします。そして、爪の切り方、足にあった靴の選び方や清潔にする方法などを説明します。フットケアを通じて日常生活で足に注意してもらい、病変の予防と早期発見に努めています。
糖尿病にはさまざまな合併症があり、診療では血糖のコントロールだけでなく、合併症の管理が不可欠です。そのため、地域の眼科や循環器科など他の科の専門医の方々と協力し合い、いろいろな角度から患者さんをケアできるように連携しています。
もちろん、合併症の検査や栄養指導など糖尿病の専門医が得意とする診療について、他の科の先生から協力を求められれば、できる限り対応します。
例えば、基本的には患者さんの家から通いやすいクリニックで頻繁に診てもらい、そのうえで糖尿病の専門医には治療の初期はもちろん、数ヶ月に1回は定期的に通院するのです。地域が一体となって糖尿病診療を行うことで、患者さんの負担を減らすことができますし、患者さんへ最善の医療を提供できると考えています。
今後も研究会や勉強会などで横のつながりを意識しながら常に研鑽し、患者さんだけでなく、地域の先生方にも頼りにされる存在であり続けたいと考えています。
●広島大学医学部付属病院にて内科の研修医
●北九州総合病院 内科、救急・麻酔科の医師
●厚生労働省 医薬品医療機器審査センター 医系技官
●広島大学大学院 公衆衛生学研究室 大学院生
●広島大学病院 内分泌・糖尿病内科、臨床研究部 助教
●いつかいち駅前内科 院長
‐資格・所属学会‐
・医学博士
・日本内科学会 認定医、専門医
・日本糖尿病学会 専門医
・日本甲状腺学会 専門医
・日本分泌学会 会員
粟屋智一先生(内科)
患者さんのQOL(生活の質)を大切にした糖尿病の治療について
いつかいち駅前内科
【住所】広島県広島市佐伯区五日市駅前1-5-18-401
【TEL】 082-943-6022

一人の患者さんと長いお付き合いになる糖尿病だから、最適な治療方法を提案するためには、その患者さんをよく知り、その環境をよく知ることがとても大切なのです、と粟屋 智一先生
糖尿病は初期には自覚症状がほとんどなく、気付いた時には重度の合併症を発症しているケースが多い恐ろしい病気です。しかも一度発症すると完治は難しく、血糖値を上手にコントロールしながら合併症の発症を予防し、進行を食い止める必要があります。
一生のお付き合いになる治療だからこそ、患者さんの生活の質QOL(Quality of life)を確保することがとても大切だとおっしゃるのが、佐伯区にあるいつかいち駅前内科の院長、粟屋智一先生です。
今回は糖尿病の合併症について詳しくご説明いただきながら、粟屋先生がいつも大切にしている患者さんとの対話やフットケアなど、患者さんの生活の質QOLを意識した治療についてお話をうかがいました。
糖尿病とはどのような病気ですか?
尿に糖が出てしまう病気と認識されている方がいますが、そうではありません。糖尿病の原因は、血液中にブドウ糖という糖分が増えて血糖値が高くなることにあります。血糖値が高くなることを「高血糖」といい、この状態が体へ悪影響を及ぼします。高血糖であれば尿に糖が出ていなくても糖尿病と診断されます。糖尿病には、インスリンという人のすい臓から分泌されるホルモンが密接に関わっています。インスリンが働くことで血液中のブドウ糖を全身の臓器に吸収させることができるのですが、糖尿病はこのインスリンが不足、あるいはうまく機能しないことで高血糖になります。
初期に体に出る症状として知られているのは、のどの渇きや頻尿などですが、ほとんどの方には自覚症状がありません。何らかの症状に気付く頃にはすでに合併症が進行しているケースがあります。そのため自覚症状がないからといって放置できない病気、それが糖尿病です。
診断する上で指標となる数値が変わったそうですね?
糖尿病はあまり症状が出ないので、血液検査をしないと病気をコントロールできているかどうか判断できません。そのコントロールの指標として最も重要視されているのがHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)で、過去1〜2か月分の血糖の平均を表す数値です。2013年に血糖のコントロール目標が変わりました。以前は、HbA1cは低いほど良いとされていましたが、厳し過ぎるコントロールで低血糖を生じるとかえって悪い影響を与えるという研究結果が出ました。そのため現在は、合併症予防の観点からHbA1c 7.0%未満を基準に、患者さんそれぞれでコントロール目標を設定することになりました。
もちろん、血糖をしっかり下げれば合併症を予防できます。しかし、例えばご高齢で治療強化が困難な方なら8%を目標にするなど、人それぞれに合うコントロール目標を定めるようになっています。この傾向は日本だけでなく世界的に見られるものです。
糖尿病にはいくつか種類があるそうが、その種類について教えてください。
糖尿病には1型、2型、その他の原因によるもの、妊娠糖尿病の4種類があり、日本の糖尿病患者の大半を占めるのが2型です。まず1型は、インスリンを分泌するすい臓の細胞が何らかの原因で破壊されて、インスリンが分泌されないタイプです。
2型は、体質的な要素に、過食や運動不足などの要因が加わって引き起こされる生活習慣病の1つです。
その他の原因による糖尿病は、遺伝子やホルモンの異常、薬剤の副作用などが原因のものです。
4つ目は、妊娠中の糖尿病で、胎盤が生成するホルモンによってインスリンの作用が抑えられることで起こります。妊娠中は通常よりも血糖値管理が厳しくなるので、産婦人科の医師からの紹介で来院される方が多くいらっしゃいます。
われわれ専門医はこれらすべての糖尿病の診療を行います。
糖尿病=恐ろしい病気、というイメージがあるのはなぜでしょう?
症状が出にくく、自覚症状が出る頃にはかなり進行しているためです。特に気を付けなければいけないのは、高血糖が長く続くことによって発症する慢性合併症です。合併症が進行すれば失明に至ることもありますし、人工透析が必要になるケースもあります。患者さんの生活の質QOL(Quality of life)を落とすばかりか、命をも落としかねない状況を引き起こすことがあるのです。そのため糖尿病はサイレントキラー(沈黙の殺人者)と呼ばれています。
基本的に合併症の症状が出てしまった場合は、進行を完全に止めることは難しくなります。裏を返せば、合併症を発症する前に、高血糖であることに気付いて血糖値を上手にコントロールすることができれば、他の方と同じように生活することが可能です。
糖尿病は、健康診断によって血糖値が高いという結果が出て初めて気付く方が大半ですが、合併症を予防するためには、気付いたらすぐに治療することが重要です。
合併症について詳しく教えていただけますか?
合併症には細小血管症と大血管症の2種類あり、まず細小血管症について説明します。細小血管症には糖尿病の3大合併症(糖尿病網膜症・糖尿病腎症・糖尿病神経障害)と呼ばれる病気があります。糖尿病網膜症は、高血糖によって眼の奥の網膜が障害を受け、視力の低下や最悪の場合には失明する恐れがあります。出血が起こると突然光を失うこともあるので気を付けなければいけません。
次に糖尿病腎症は、高血糖によって、体内の老廃物を尿として流す腎臓の働きが悪くなります。症状としては血圧の上昇や、尿にタンパクが出てむくむなどです。進行すると腎不全や尿毒症を引き起こして透析が必要になったり、生命に関わることもあります。
糖尿病神経障害は、知覚神経や自律神経に障害が生じて、手足の痛みやほてり、しびれなどの他、便秘や下痢、立ちくらみ、勃起障害(ED)などを引き起こします。進行すると足の潰瘍(かいよう)や壊疽(えそ)の原因になります。
いずれも病状が進むと患者さんの生活の質QOLに影響しますが、適切な血糖コントロールで進行を抑えることができます。
合併症の大血管症についても教えてください。
大血管症は、太い血管が硬化する事で起こる合併症です。それによって脳卒中や心筋梗塞を引き起こし、その発症率は健康な人に比べて2〜4倍にも上ります。また、末梢動脈性疾患によって、足の壊疽や皮膚潰瘍にまで深刻化することがありますまず、脳卒中には主に脳梗塞・脳出血・くも膜下出血がありますが、この中で糖尿病患者に多いのは脳梗塞です。手足が動かなくなったり、言葉が出なくなる、物が二重に見えるなどの症状があり、生命に関わることがあります。さらに手足の麻痺や言語障害などの後遺症が出ることもありますので、細心の注意が必要です。
次に心筋梗塞は、心臓に栄養や酸素を送り続けている冠動脈が動脈硬化を起こし、心臓の働き自体が低下してしまう病気です。これも生命に関わることがあります。
そして、末梢動脈性疾患は、足の動脈が硬化することで起こる血流の低下が原因です。進行とともに足のしびれや痛みが出て、歩くことが困難になります。さらに悪化すると潰瘍ができたり、足の一部が腐る壊疽を起こすことがあります。
糖尿病の治療目標について教えてください。
糖尿病治療の最終目的は、健康な人と変わらない充実した日常生活を送ることと、健康な人と同じように寿命をまっとうすることです。そのためには生涯にわたって血糖、血圧、脂質の良好なコントロールを維持して、糖尿病の合併症(網膜症、腎症、神経障害、動脈硬化)を予防する必要があります。糖尿病は、合併症を予防することで、生活の質QOLの低下を防ぐことができる病気です。ところがその一方で、予防に固執して食事・運動療法などの治療を厳しくし過ぎると、生活の質QOLを低下させてしまうという一面も持っています。また無理を強いられる治療は長く続きません。
そのため当クリニックでは、糖尿病診療を進めていく上で、生活の質QOLをなるべく低下させない食事療法、運動療法、薬物療法を患者さんと一緒に考えるようにしています。
食事療法と運動療法はどのように進めていくのですか?
患者さんによってさまざまです。食事療法ではまず腹八分目や間食を控えることから始めて様子をみます。その他に食べる順番や、ゆっくり食べること、カロリーが低い野菜を多く摂る、油ものを控えるなど、誰にでも実現可能なことを提案して、患者さんができることから始めています。運動療法では、週に3日以上30分以上歩くことや、プールに行くことを勧めています。ただし、まとまった時間が取れない人も多いので、ひと駅前で電車を降りて歩くことや、会社の昼休憩に歩くなど、できることから始めます。他にも家の中での柔軟運動や足踏みなどでも良いので、まず始めてみて、相談しながら調整していきます。
無理強いをするのではなく、相談しながら治療内容を決め、その方に合った食事療法や運動療法を長く続けていくことが重要だと考えています。
薬物療法について具体的に教えてください。
2型糖尿病の場合、治療の両輪を成すのは食事療法と運動療法で、薬物療法は補助的な位置づけです。薬物療法のうち、糖尿病の飲み薬では、副作用に細心の注意を払って患者さんに合う薬を処方しています。インスリン治療は、1型糖尿病や、食事療法ではコントロールできない妊娠糖尿病、2型糖尿病で著明な高血糖の方や飲み薬でコントロールできない方などに実施します。インスリン注射は難しいと思われていますが、一般的な注射器と違ったペン型なので操作は簡単です。針は本当に細くて短いので、ほとんど痛みは感じません。
クリニックでは、チェックシートや説明書を用いて繰り返し説明し、安心して使用してもらっています。
糖尿病治療に関わる器具や薬剤自体も進化し続けているようですね?
さまざまな研究や開発により、糖尿病治療は日々進化しています。専門医としてそれらの最良の治療を採り入れています。例えば、2型糖尿病では以前は1日に2〜4回注射していたインスリン治療は、効果が長時間持続する薬剤が登場し、1日に1回の注射をメインに治療しています。
また、インスリンを持続的に皮下に注入できる携帯型インスリンポンプ(CSII)も改良されました。さらに、炭水化物や糖質の量でインスリンを調整できるカーボカウントも普及して来ました。これらを応用すると、食や運動に対する自由度が高まり、血糖値のコントロールを改善して生活の質QOLを高めることができます。そのため、当院でも1型糖尿病患者さんに推奨しています。
患者さんの生活の質QOLを考えながら、患者さんの病状と患者さんにとって最良の治療をしっかり把握して、いろいろな引き出しを持って治療に当たっています。
糖尿病患者さんにはフットケアをするそうですね?
糖尿病では神経障害で感覚が鈍くなったり、動脈硬化で血液が十分流れなくなったりして、特に足の病気を起こしやすくなります。ところが体の末端にある足に対して、日常あまり気を使うことはありません。そのため病気の発見が遅れ、足の一部が腐る「壊疽(えそ)」にまで進行することもあります。進行させないためには予防と早期発見が重要です。当院では糖尿病患者さんには診察で足をチェックし、フットケアをするようにしています。
具体的には、足にできた傷が治りにくくなっていないか、白癬(水虫)や巻き爪などがないかをチェックします。そして、爪の切り方、足にあった靴の選び方や清潔にする方法などを説明します。フットケアを通じて日常生活で足に注意してもらい、病変の予防と早期発見に努めています。
糖尿病に関する地域医療について、先生の考えを教えてください。
「医師同士の横の連携を強固にして、患者さんの生活の質QOLを守りながら最善の医療を提供すること」これが糖尿病における地域医療の理想的な姿だと考えています。糖尿病にはさまざまな合併症があり、診療では血糖のコントロールだけでなく、合併症の管理が不可欠です。そのため、地域の眼科や循環器科など他の科の専門医の方々と協力し合い、いろいろな角度から患者さんをケアできるように連携しています。
もちろん、合併症の検査や栄養指導など糖尿病の専門医が得意とする診療について、他の科の先生から協力を求められれば、できる限り対応します。
例えば、基本的には患者さんの家から通いやすいクリニックで頻繁に診てもらい、そのうえで糖尿病の専門医には治療の初期はもちろん、数ヶ月に1回は定期的に通院するのです。地域が一体となって糖尿病診療を行うことで、患者さんの負担を減らすことができますし、患者さんへ最善の医療を提供できると考えています。
今後も研究会や勉強会などで横のつながりを意識しながら常に研鑽し、患者さんだけでなく、地域の先生方にも頼りにされる存在であり続けたいと考えています。
医師のプロフィール
粟屋 智一 先生
●東邦大学医学部医学科卒業●広島大学医学部付属病院にて内科の研修医
●北九州総合病院 内科、救急・麻酔科の医師
●厚生労働省 医薬品医療機器審査センター 医系技官
●広島大学大学院 公衆衛生学研究室 大学院生
●広島大学病院 内分泌・糖尿病内科、臨床研究部 助教
●いつかいち駅前内科 院長
‐資格・所属学会‐
・医学博士
・日本内科学会 認定医、専門医
・日本糖尿病学会 専門医
・日本甲状腺学会 専門医
・日本分泌学会 会員
病名・症状・キーワードからレポートを検索
■□■□ 2025年12月によく読まれた記事をCHECK! □■□■
命にかかわる病気ではありませんが、経過観察と言われたら生理の変化に気を付けて。過多月経や月経痛がひどくなるなどの場合は早めに産婦人科に相談しましょう。
実は10代、20代の女性の死因上位に挙げられる摂食障害。
人の価値や美しさは、体型や体重で決まるものではありません。
適切なカウンセリングで過度な痩せ願望やストレスから自分の体を守りましょう。
幼児や児童に感染することが多く、発症すると喉の痛み、熱、発疹などといった風邪と似た症状が起こります。また、痛みはないのですが、舌の表面に赤いぶつぶつができることがあります。
尋常性疣贅は、「ヒト乳頭腫ウイルス」というウイルスの一種が皮膚に感染してできます。手あれや髭剃り後など、目に見えないくらいの小さな傷からでもウイルスが侵入します。どこの部位にもできる可能性があるのです。
咽喉頭異常感症は心理的要因が大きいといわれています。
喉がイガイガする、圧迫感がある、引っ掛かったり、絡んだような感じがするなど
考えれば考えるほど、喉に違和感を抱き、そのストレスが引き金になって症状を引き起こすことも多いようです。
「不安障害」とはその名の通り、不安な気持ちが強くなる病気です。
ある特定の状況や場所で非常に強い不安に襲われ、身体のいろいろな部分に様々な症状が現われたり、不安を避けようとする「回避行動」をとるようになったり、また安心を得るために無意味な行動を反復してしまうといったことが起こり、人によってはそれが原因で社会生活に支障をきたすこともあります。