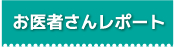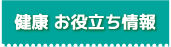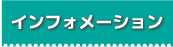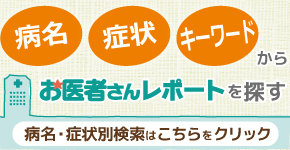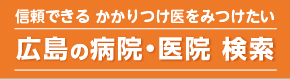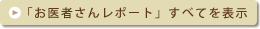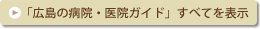広島の頼れるかかりつけ医&病院・医院・クリニックに出会える健康情報サイト
(この記事は2015年10月9日時点の情報です)
もりた心療内科クリニック
【住所】広島市中区大手町2-1-4広島本通りマークビル5F
【TEL】082-243-0038
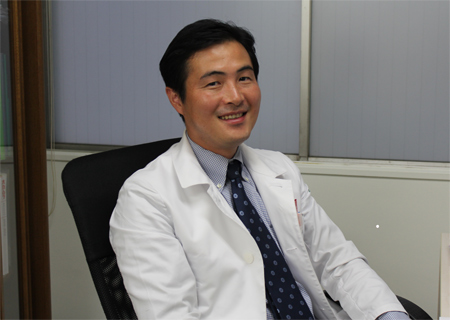
2014年8月に広島市北部を襲った土砂災害。多くの人命が失われ、たくさんの家屋が倒壊しました。そして、今でも、その経験が原因となって心的外傷ストレス(PTSD)に苦しめられている方が広島にはたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は中区にあるもりた心療内科クリニックの院長、森田幸孝先生に心的外傷ストレス(PTSD)を中心に、心の不調についてお話をうかがいました。もりた心療内科にはPTSDの方だけでなく、うつ症状や不眠、不安などの適応障害、統合失調症などいろいろな症状の方が通院されています。街中のクリニックだけあって、患者さんの年代層は10代から90代までと幅広く、症状もさまざまです。そういった方々に対して、先生はどのように接していらっしゃるのでしょう。また、どのように治療は進んでいくのでしょう。
もしご自分やご家族、身近な人が心の病をかかえてしまったら、くよくよ悩んでいないでまずは心療内科を受診してみようと思えるお話ばかりです。
具体的な症状としては、不安や不眠などの過覚醒、恐ろしかった体験を突然思い出すフラッシュバック、事故が起こりそうな場所を避けるような回避といった症状が挙げられます。
ショック体験が起きて6ヶ月未満にこのような症状が現れた場合は、ASD(急性ストレス障害)と診断され、PTSDとは区別して考えられています。6ヶ月以上経ってもそういった症状に悩まされる場合、それがPTSDです。
死を意識するような強烈なショック体験、といってもなかなか想像しづらいかと思いますが、一般的には東北や広島で起こった自然災害、それ以外にも火災、事故、外傷などがきっかけになり得ます。また、男性であれば戦争、女性であればレイプによるトラウマなどが分かり易いでしょうか。
あとは EMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing:眼球運動による脱感作と再処理法)といった特殊な治療法もあります。具体的には目を動かしながらその事故の状況に立ち戻り、今の苦しい考え方を少し柔軟に捉えなおして追体験し、心のダメージを和らげていくのです。これは行動(認知)療法という治療法です。
その上で、先ほども申し上げたような、不安や不眠などの過覚醒、恐ろしかった体験を突然思い出すフラッシュバック、事故が起こりそうな場所を避けるような回避といった症状がみられるかどうか、で診断します。また、それらの症状のために、日常生活をおくることが著しく困難になった場合は、PTSDの可能性が高いと言えるでしょう。
その体験がご本人にとって、とても恐ろしいものだったことは間違いありません。ただ、PTSDの診断基準である「死」に直面したかどうか、といった見方をすると、PTSDとは言えないのではないかと。もう少し慎重に診断せざるを得ない、というのが私の考えです。
と言いますのも、実際にPTSDだと診断を下すと、ある程度原因になった相手が特定される可能性が高くなります。つまり、その診断書がその相手を攻撃する材料になりかねないのです。人間関係にヒビを入れないためにも、診断に関しては専門家ならではの慎重さが求められていると思います。
まずはじっくりと患者さんの話に耳を傾けることですね。何回か来院されて終わり、というのではなくて、そこから治療が始まるスタートラインに立ったばかりです。患者さんとのお付き合いが長くなることが多いのも心療内科の特徴ですから、患者さんに寄り添う形で治療を進めていこうといつも考えています。
通院の頻度ですが、初診の場合には1週間後にもう一度来院していただき、問診によって症状の経過を確認し、薬が合っているかどうかを確認します。落ち着いてこられたら2〜4週間に1回通院していただいたりしますが、頻度はその方の症状次第になります。
あとはご家族の方がいらっしゃれば状況をお聞きしたりして、話を引き出すきっかけにしたりしていますね。少しずつ時間をかけて対話を重ね、信頼関係を築き上げていくことが大切だと思っています。
ただ最近は、神経内科や心療内科の敷居が低くなっているのは感じますね。ちょっと調子が悪い、例えば以前に比べて眠れないといった軽い症状で来院される方も多いですよ。学校の先生や上司に勧められて来院される方、前と比べて家で横になって過ごす時間が増えたと心配して親御さんに付き添われて来院する方などもいらっしゃいます。
また、フラッシュバックなどについては、一定の時間の経過が何よりも必要になります。例えば2014年の広島での土砂災害に限らず、2013年の東北大震災を経験された方々の中にはまだまだPTSDで苦しんでおられる方々が多くいらっしゃることを考えても、治療に必要な期間はご想像いただけるかと思います。もちろん個人差もありますしね。
ただ、どのような症状を抱えている方でも、まずは来院していただいて、話を聞くことで、何らかの症状改善への手助けはできるはずですから、ぜひお越しいただきたいと思います。
ただ最近は「現代型うつ病」などうつの概念が拡がってきているので、これも一概には当てはまらなくなってきました。
分かりやすいように極端な例で言うと、家にいるときには元気で、会社に行くとなるとうつになる、というのが現代型うつ病の症状です。
厳密に言えばうつ病ではないと私は思いますが、診断基準を用いると確かにうつ病という診断になるのです。だから現代型です。
実際には、これも症状次第なのです。不眠の症状があって睡眠薬を処方されていた方でも、秋になって少し涼しくなり、過ごしやすくなることで自然に眠れるようになった、という方もたくさんいらっしゃいます。そのような場合には、薬は必要なくなりますよね。
医療の進歩は日進月歩なので、より依存性の少ない、副作用の少ない薬がどんどん開発されていますから、医師ときちんと相談して、上手な薬の使い方をしてほしいと思いますね。
不眠を例に挙げてみましょう。夜きちんと眠れないと翌日も頭がボーっとして集中力もなく仕事の効率も上がりませんよね。でも、もし薬を服用したことで、しっかり眠れ、翌朝には頭がすっきりするのであれば、どちらを選びますか。
薬なしにこだわるあまりに、眠れないで苦しむよりは、薬を飲んできちんと眠り、きちんと社会復帰を目指すことの方が大切なのではないかと私は思っています。
ご自分で良くなろう、と思う気持ちも大切ですし、薬がどうしても嫌だ、といった思いが強くて空回りしてしまう方もいらっしゃると思いますが、そういった思いにも心療内科の医師はきちんと寄り添いますから安心してください。
なぜならば、健康な方だと特に意識されないと思いますが、世の中には、抗うつ剤を服用しながら会社に勤務していたり、家事をしていたり、通学していたりする方々がたくさんいらっしゃるからです。そういった方々の日々の生活を守ることが、精神科医の大切な役割なのだと思っています。
実際にここであった話ですが、心と体の不調を訴えて来院された方がいらっしゃって。話をよくうかがってみたら、仕事が忙しすぎて睡眠時間があまりにも短く、これはどう診ても過労ですよ、と診断させていただいたこともあります。この方は、きちんと医師の診断を受けたことで、心の病かもしれないというストレスからも解放されたのです。
そのようなケースもありますから、何か心や体に不調をおぼえていらっしゃる方は、ぜひ気軽に心療内科を受診していただきたいと思います。
●岡山大学附属病院、広島市立広島市民病院、精神科病院、認知症専門病院、こども療育センターなどで臨床に携わる
●岡山大学大学院修了
●アメリカのNIH(National Institutes of Health)で2年間客員研究員として精神疾患の研究に従事
●広島市立広島市民病院 元副部長
●もりた心療内科クリニック院長
-資格・所属学会-
・医師
・医学博士
・精神保健指定医
・日本精神神経学会認定精神科専門医・指導医、日本医師会認定産業医
森田 幸孝 先生(精神科)
心的外傷ストレス(PTSD)について
もりた心療内科クリニック
【住所】広島市中区大手町2-1-4広島本通りマークビル5F
【TEL】082-243-0038
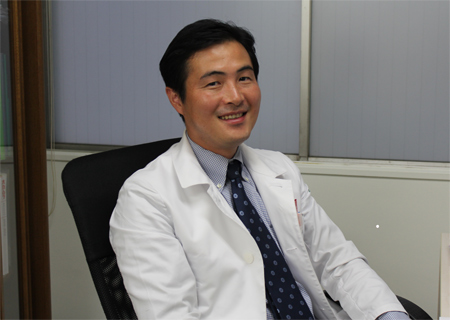
広島市立広島市民病院で副部長も務めた森田先生。同じく精神科医だった父のクリニックを2014年に継承。
2014年8月に広島市北部を襲った土砂災害。多くの人命が失われ、たくさんの家屋が倒壊しました。そして、今でも、その経験が原因となって心的外傷ストレス(PTSD)に苦しめられている方が広島にはたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は中区にあるもりた心療内科クリニックの院長、森田幸孝先生に心的外傷ストレス(PTSD)を中心に、心の不調についてお話をうかがいました。もりた心療内科にはPTSDの方だけでなく、うつ症状や不眠、不安などの適応障害、統合失調症などいろいろな症状の方が通院されています。街中のクリニックだけあって、患者さんの年代層は10代から90代までと幅広く、症状もさまざまです。そういった方々に対して、先生はどのように接していらっしゃるのでしょう。また、どのように治療は進んでいくのでしょう。
もしご自分やご家族、身近な人が心の病をかかえてしまったら、くよくよ悩んでいないでまずは心療内科を受診してみようと思えるお話ばかりです。
PTSD(心的外傷ストレス)の症状にはどのようなものがありますか?
PTSD( Post Traumatic Stress Disorder :心的外傷後ストレス障害)は、危うく死にかけるなど極度のストレスを伴う強烈なショック体験の後で表れる、精神的な不調のことを指します。具体的な症状としては、不安や不眠などの過覚醒、恐ろしかった体験を突然思い出すフラッシュバック、事故が起こりそうな場所を避けるような回避といった症状が挙げられます。
ショック体験が起きて6ヶ月未満にこのような症状が現れた場合は、ASD(急性ストレス障害)と診断され、PTSDとは区別して考えられています。6ヶ月以上経ってもそういった症状に悩まされる場合、それがPTSDです。
いつ頃から注目されているのですか?
PTSDの概念は1970〜1980年頃、比較的最近になって精神医療の中で広がって来たものです。ベトナム戦争の後、本国に帰還した兵士の中に、社会復帰ができないような精神障害を抱えた人がたくさんいたのです。そして、そういった人たちにはある特徴的な精神症状があるということで拡がったのが、PTSDの概念です。死を意識するような強烈なショック体験、といってもなかなか想像しづらいかと思いますが、一般的には東北や広島で起こった自然災害、それ以外にも火災、事故、外傷などがきっかけになり得ます。また、男性であれば戦争、女性であればレイプによるトラウマなどが分かり易いでしょうか。
治療方法にはどのようなものがありますか?
まずカウンセリングや内服治療、精神療法などがありますが、いろいろと話を聞きながら、患者さんとその症状に寄り添いながら治療に当たっていくのが基本になります。あとは EMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing:眼球運動による脱感作と再処理法)といった特殊な治療法もあります。具体的には目を動かしながらその事故の状況に立ち戻り、今の苦しい考え方を少し柔軟に捉えなおして追体験し、心のダメージを和らげていくのです。これは行動(認知)療法という治療法です。
診断はどうやってするのですか?
危うく死にかけるような体験をした後に起こった症状かどうか、が重要な診断基準の1つです。その上で、先ほども申し上げたような、不安や不眠などの過覚醒、恐ろしかった体験を突然思い出すフラッシュバック、事故が起こりそうな場所を避けるような回避といった症状がみられるかどうか、で診断します。また、それらの症状のために、日常生活をおくることが著しく困難になった場合は、PTSDの可能性が高いと言えるでしょう。
最近はPTSDが拡大解釈されているそうですが、詳しく教えてください。
はい。例えば先生や上司に怒鳴られたとか、生徒に暴力を振るわれたといったことでPTSDの診断を求める方が時々いらっしゃいます。その体験がご本人にとって、とても恐ろしいものだったことは間違いありません。ただ、PTSDの診断基準である「死」に直面したかどうか、といった見方をすると、PTSDとは言えないのではないかと。もう少し慎重に診断せざるを得ない、というのが私の考えです。
と言いますのも、実際にPTSDだと診断を下すと、ある程度原因になった相手が特定される可能性が高くなります。つまり、その診断書がその相手を攻撃する材料になりかねないのです。人間関係にヒビを入れないためにも、診断に関しては専門家ならではの慎重さが求められていると思います。
おっしゃる通りですね。では次に、具体的な治療方法について教えていただけますか?
患者さんの訴えに応じて症状を診断し、治療を組み立てていくのが心療内科です。血液検査やCTを使った診断が可能な他の科と違って、患者さんのおっしゃること、訴えてこられることが何よりも重要な診断材料であり、治療への糸口を発見することにつながります。まずはじっくりと患者さんの話に耳を傾けることですね。何回か来院されて終わり、というのではなくて、そこから治療が始まるスタートラインに立ったばかりです。患者さんとのお付き合いが長くなることが多いのも心療内科の特徴ですから、患者さんに寄り添う形で治療を進めていこうといつも考えています。
通院の頻度ですが、初診の場合には1週間後にもう一度来院していただき、問診によって症状の経過を確認し、薬が合っているかどうかを確認します。落ち着いてこられたら2〜4週間に1回通院していただいたりしますが、頻度はその方の症状次第になります。
対話を進めるために、何か心掛けていらっしゃることはありますか?
なかなか初対面で話がスムーズに進むことは少ないのが現実です。そのため、最初はイエスまたはノーで答えられる二択のような、シンプルな質問から始めるようにしています。あとはご家族の方がいらっしゃれば状況をお聞きしたりして、話を引き出すきっかけにしたりしていますね。少しずつ時間をかけて対話を重ね、信頼関係を築き上げていくことが大切だと思っています。
信頼関係は大切そうですね。ところで患者さんは一人で来院されることが多いですか?
自覚症状があってご自分で来院される方、ご家族の方が心配して連れてこられる方など、いろいろなケースがありますが、およそ半々なイメージです。ただ最近は、神経内科や心療内科の敷居が低くなっているのは感じますね。ちょっと調子が悪い、例えば以前に比べて眠れないといった軽い症状で来院される方も多いですよ。学校の先生や上司に勧められて来院される方、前と比べて家で横になって過ごす時間が増えたと心配して親御さんに付き添われて来院する方などもいらっしゃいます。
いろいろなのですね。PTSDの場合、治療期間はどのくらい必要ですか?
患者さんによって症状の重さもさまざまなので一概には言えませんが、不眠や不安感を訴えている方は症状に合わせて抗不安剤や睡眠薬を処方することで、数日から数週間である程度症状の改善は可能です。また、フラッシュバックなどについては、一定の時間の経過が何よりも必要になります。例えば2014年の広島での土砂災害に限らず、2013年の東北大震災を経験された方々の中にはまだまだPTSDで苦しんでおられる方々が多くいらっしゃることを考えても、治療に必要な期間はご想像いただけるかと思います。もちろん個人差もありますしね。
ただ、どのような症状を抱えている方でも、まずは来院していただいて、話を聞くことで、何らかの症状改善への手助けはできるはずですから、ぜひお越しいただきたいと思います。
身近に患者さんがいる場合、接する時に気を付けた方がいいことを教えてください。
例えばうつの患者さんに対して、教科書的には「がんばって」といった声掛けはやめた方がよい、と載っていますよね。ただ最近は「現代型うつ病」などうつの概念が拡がってきているので、これも一概には当てはまらなくなってきました。
現代型うつ病とは何ですか?
若い方に多い傾向があるうつ病の一種です。性格的には逃避型の方に多く見られる症状で、一定数いらっしゃいますね。分かりやすいように極端な例で言うと、家にいるときには元気で、会社に行くとなるとうつになる、というのが現代型うつ病の症状です。
厳密に言えばうつ病ではないと私は思いますが、診断基準を用いると確かにうつ病という診断になるのです。だから現代型です。
ではPTSDの方に対する接し方で気を付けた方がよいことはありますか?
体調を整えやすいような環境を作ってあげるとよいですよね。もちろん症状が改善されるにしたがって最適な環境は変わるので一概には言えませんが、フラッシュバックなどの症状が強いなら、ショック体験についての話題は避けた方がよいでしょうね。テレビでも例えば「今から津波の映像が○分間続きます」などのテロップを流して、PTSDやASDの方々への配慮がなされていたことは記憶に新しいですよね。睡眠薬や精神安定剤は依存性のあるお薬なのですか?
確かに依存性はありません、と言い切れるお薬ばかりではないですね。身体が薬に慣れる、ということは実際にありますし。ただ、きちんと医師が患者さんを診察し、その症状に合わせて、必要な薬だけを処方する訳ですから、ご自分の判断で薬を途中でやめてしまったりというのはあまりお勧めしません。実際には、これも症状次第なのです。不眠の症状があって睡眠薬を処方されていた方でも、秋になって少し涼しくなり、過ごしやすくなることで自然に眠れるようになった、という方もたくさんいらっしゃいます。そのような場合には、薬は必要なくなりますよね。
医療の進歩は日進月歩なので、より依存性の少ない、副作用の少ない薬がどんどん開発されていますから、医師ときちんと相談して、上手な薬の使い方をしてほしいと思いますね。
薬について先生はどのようにお考えですか?
薬を飲まずに日常生活を普段通りにおくれるのであれば、それがベストです。その一方で、薬があることで日常生活を支障なくおくれている方々もいらっしゃるのも事実なのです。不眠を例に挙げてみましょう。夜きちんと眠れないと翌日も頭がボーっとして集中力もなく仕事の効率も上がりませんよね。でも、もし薬を服用したことで、しっかり眠れ、翌朝には頭がすっきりするのであれば、どちらを選びますか。
薬なしにこだわるあまりに、眠れないで苦しむよりは、薬を飲んできちんと眠り、きちんと社会復帰を目指すことの方が大切なのではないかと私は思っています。
ご自分で良くなろう、と思う気持ちも大切ですし、薬がどうしても嫌だ、といった思いが強くて空回りしてしまう方もいらっしゃると思いますが、そういった思いにも心療内科の医師はきちんと寄り添いますから安心してください。
最後に、地域医療における精神科医の役割はどんなところにあるとお考えですか?
私自身、精神科医が地域における精神医療に貢献していく、というのはとても重要なことだと考えています。なぜならば、健康な方だと特に意識されないと思いますが、世の中には、抗うつ剤を服用しながら会社に勤務していたり、家事をしていたり、通学していたりする方々がたくさんいらっしゃるからです。そういった方々の日々の生活を守ることが、精神科医の大切な役割なのだと思っています。
実際にここであった話ですが、心と体の不調を訴えて来院された方がいらっしゃって。話をよくうかがってみたら、仕事が忙しすぎて睡眠時間があまりにも短く、これはどう診ても過労ですよ、と診断させていただいたこともあります。この方は、きちんと医師の診断を受けたことで、心の病かもしれないというストレスからも解放されたのです。
そのようなケースもありますから、何か心や体に不調をおぼえていらっしゃる方は、ぜひ気軽に心療内科を受診していただきたいと思います。
医師のプロフィール
森田 幸孝 先生
●宮崎大学医学部を卒業●岡山大学附属病院、広島市立広島市民病院、精神科病院、認知症専門病院、こども療育センターなどで臨床に携わる
●岡山大学大学院修了
●アメリカのNIH(National Institutes of Health)で2年間客員研究員として精神疾患の研究に従事
●広島市立広島市民病院 元副部長
●もりた心療内科クリニック院長
-資格・所属学会-
・医師
・医学博士
・精神保健指定医
・日本精神神経学会認定精神科専門医・指導医、日本医師会認定産業医
病名・症状・キーワードからレポートを検索
■□■□ 2025年5月によく読まれた記事をCHECK! □■□■
命にかかわる病気ではありませんが、経過観察と言われたら生理の変化に気を付けて。過多月経や月経痛がひどくなるなどの場合は早めに産婦人科に相談しましょう。
実は10代、20代の女性の死因上位に挙げられる摂食障害。
人の価値や美しさは、体型や体重で決まるものではありません。
適切なカウンセリングで過度な痩せ願望やストレスから自分の体を守りましょう。
幼児や児童に感染することが多く、発症すると喉の痛み、熱、発疹などといった風邪と似た症状が起こります。また、痛みはないのですが、舌の表面に赤いぶつぶつができることがあります。
尋常性疣贅は、「ヒト乳頭腫ウイルス」というウイルスの一種が皮膚に感染してできます。手あれや髭剃り後など、目に見えないくらいの小さな傷からでもウイルスが侵入します。どこの部位にもできる可能性があるのです。
咽喉頭異常感症は心理的要因が大きいといわれています。
喉がイガイガする、圧迫感がある、引っ掛かったり、絡んだような感じがするなど
考えれば考えるほど、喉に違和感を抱き、そのストレスが引き金になって症状を引き起こすことも多いようです。
「不安障害」とはその名の通り、不安な気持ちが強くなる病気です。
ある特定の状況や場所で非常に強い不安に襲われ、身体のいろいろな部分に様々な症状が現われたり、不安を避けようとする「回避行動」をとるようになったり、また安心を得るために無意味な行動を反復してしまうといったことが起こり、人によってはそれが原因で社会生活に支障をきたすこともあります。